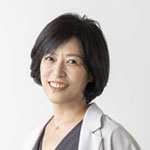第3回
秋の若狭でチャリコと遊ぶ
イノベーションズアイ編集局 編集アドバイザー 鶴田 東洋彦
“5色の湖”の名前に納得
日本地図を広げると、本州で一番狭いあたり。琵琶湖の北部からもそう遠くない福井県西部の三方郡に三方五湖という湖がある。若狭、美浜の両町にまたがるこの湖は、久々子湖、水月湖、菅湖、三方湖、日向湖という連なる5つの湖からなり、水質、水深の違いもあってか、すべてが違う色に見えるという。2005年11月にラムサール条約の指定湿地にも登録されたここは、以前から訪ねたかった場所だ。季節外れの暑さがようやく落ち着いた10月半ば、思い切って出かけてみた。
福井県の嶺南と呼ばれる地域、敦賀の市内から、白砂がまぶしい水晶浜を経由して車で30分ほど。レインボーラインという周遊道路で湖を眺められる山頂まで走り、湖を眺めると、確かに5つの湖の色は微妙に違う。湖の愛称でもある「5色の湖」の名前の由来に納得しながら久々子湖まで下ると、山々の緑が鮮やかな湖畔は訪れる人も少なく、吹く風も心地よい。
この日は敦賀市内に宿を取っていることもあり、午後からは気比の松原や気比神社あたりも回ってみたい思いもあった。しかも、残念ながら釣った魚を持ち帰って料理する機会はない。とにかく竿を出して「どんな魚が釣れるか」だけを確認したいという思いだけが先走って、気持ちは焦り気味。とは言っても、漁港とは違って周囲の状況はさっぱりわからない。
まして、この5つの湖は江戸時代に開削された水路で結ばれ、場所によって淡水、汽水、海水とそれぞれに違う。「どこかいい釣り場はないか」と地元に人に尋ねても、皆、首をかしげるばかりで要領を得ない。淡水のコイ、フナ、ウナギから海水のカレイやタイまで、釣れる場所も魚も全く違うのだから当たり前かもしれないが。
日向湖のチョイ投げで次々とチャリコが

そこで、唯一の海水湖である日向湖に期待して、湖畔に向かう。湖面は深い緑の山々に囲まれて、とても海水湖とは思えないが、湖の奥で何人の釣り人が竿を出している。早速、天秤仕掛けに8号針をつけて、その近くの場所でチョイ投げしてみる。と、驚いたことに、いきなり当たりが。元気よく釣れてきたのは、手のひらほどの小鯛。関西ではチャリコと呼ばれ、「小鯛の笹漬け」に加工されて若狭の名産として全国銘柄になっている魚だ。
その後も、投げるたびに、このチャリコが食いついてくる。そして中国地方ではギザミと呼ばれて珍重されるキュウセンベラや、やや時季外れのキスまでも。あいにく手元にはスカリ(釣った魚を活かしておく網)もないのでリリースを繰り返していたが、数匹だけはこの連載の写真用に並べてみた。

ちなみにチャリコは関東ではカスゴと呼ばれて、キス釣りやサビキ釣りの外道として針にかかることが多い。何センチまでをチャリコと呼ぶかは人によってさまざまだが、だいたい20センチくらいまでを呼ぶことが多いようだ。小さいとは言っても立派な真鯛で、塩焼き、味噌汁、煮付けとなんでも美味しい。笹漬けは酒の肴として最高だし、地元では丸ごと炊き込んで鯛めしにすることも多いとか。この日は残念ながら、皆、海に帰ってもらったが、ちょっと悔やまれる釣果だった。
2時間ほど、このチャリコ釣りを楽しんで、再び水晶浜を経由して気比の松原を通り敦賀市内へ。広島の厳島神社、奈良の春日大社と並ぶ日本3代鳥居で有名な気比神社を拝観、ユダヤ難民を受け入れた唯一の港である敦賀の歴史を紹介する「敦賀ムゼウム」を見学してホテルに入った。
関西で使う電力の半分近くが福井から
ちなみにこの敦賀から若狭湾にかけては廃止措置中の設備も含めて15基の原子力発電所が並ぶ、日本のエネルギー供給の一大拠点である。とくに日本初の軽水炉として稼働した日本原子力発電(日本原電)の敦賀発電所1号機は、先日、閉幕した大阪万博の前、1970年に開かれた日本初の大阪万博の開会式の日に運転を開始、会場に送電したことでも知られている。現在でも関西の電力使用量の半分近くが、福井県からのものだ。
そういえば、釣り帰りの道すがら、水晶浜からは沖合に関西電力の美浜原発が薄っすらと見えた。敦賀半島の先には日本原電の敦賀発電所も立地する。初めて訪れた場所ではあるが、発電所をまじかにすると改めて、エネルギーの大切さを思う。地政学的にも危うい地域にあり、エネルギーの自給率が15%程度しかない日本だからこそ、個人的には「脱炭素エネルギー」として原発の必要性を感じざるを得ない。太陽光などの限界も言われているだけに、なおさらだ。
そんな水晶浜の景色を思い浮かべながら、ホテル近くの小料理屋のカウンターで地元の銘酒「黒龍」を堪能していると、少し離れた席から、自民党の高市新総裁の政策を肴に飲み交わしている二人の声が耳に入ってきた。どうやら電力関係の人らしい。次世代革新炉や核融合炉の実現で、エネルギー自給率100%を訴えてきた高市氏の思いに対する期待は、この町の電力関係者にも多いのだろう。
二人の話を聞くともなく黒龍を傾け、地元名産の鯖の「へしこ」やバイ貝の刺身をつつくうちに酔いが増し、気が付くと時間は11時近く。旅の疲れも出たのか、或いは釣りの疲れも出たのだろう。眠気も増す一方だ。二人の声に刺激されたのか、原子力やエネルギーの問題を取材していた、現役記者のころの様々な出来事を思い浮かべながら、寝静まった敦賀の街を、千鳥足でホテルに向かった。
プロフィール

イノベーションズアイ編集局
編集アドバイザー
鶴田 東洋彦
山梨県甲府市出身。1979年3月立教大学卒業。
産経新聞社編集局経済本部長、編集長、取締役西部代表、常務取締役を歴任。サンケイ総合印刷社長、日本工業新聞(フジサンケイビジネスアイ)社長、産経新聞社コンプライアンス・アドバイザーを経て2024年7月よりイノベーションズアイ編集局編集アドバイザー。立教大学、國學院大學などで「メディア論」「企業の危機管理論」などを講義、講演。現在は主に企業を対象に講演活動を行う。ウイーン国際音楽文化協会理事、山梨県観光大使などを務める。趣味はフライ・フィッシング、音楽鑑賞など。
著書は「天然ガス新時代~機関エネルギーへ浮上~」(にっかん書房)「K字型経済攻略法」(共著・プレジデント社)「コロナに勝つ経営」(共著・産経出版社)「記者会見の方法」(FCG総合研究所)など多数。
- 第3回 秋の若狭でチャリコと遊ぶ
- 第2回 ギンポを味わいながら秀吉の野望を思う
- 第1回 那覇港で熱帯魚を釣って食べる