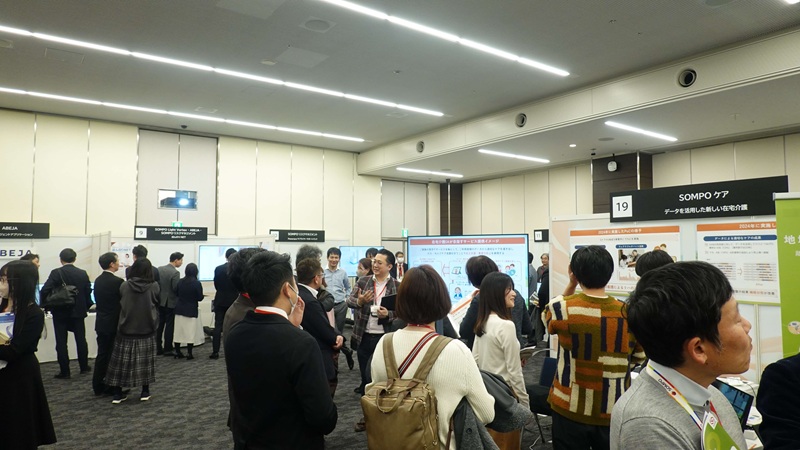SOMPOグループ 再言語化したパーパスの浸透図る ㊦ チャレンジ精神を競う

「チャレンジできる環境を与えてくれた」「地域貢献は本業ではないというが、本業として取り組んできた成果だ」「SOMPOにはチャレンジを支えるマインド、カルチャーがある」
SOMPOアワードでカテゴリー最優秀賞を受賞した3チームの発表者は壇上でこう熱い気持ちで語った。チャレンジ精神が高く評価された取り組み・事業を紹介する。
カスハラから従業員も守る
▷「チャレンジ」 SOMPOリスクマネジメントの「カスハラ対策支援チーム」(写真・左上)
5万1921キロメートルー。顧客からの理不尽な当惑行為であるカスタマーハラスメントから「従業員も守る」にはどんなサービスが必要か。顧客ニーズを知るために要した移動距離だ。
全国行脚して経営者などに困りごとを聞くと「必ず出てくるのがカスハラ。対応困難なハードクレーマーも増加しており、そこで体系的に整理して2024年6月にカスハラ対策支援サービスをローンチした」(コーポレート・リスクコンサルティング部人的資本グループリーダーの西彩菜氏)。人的資本経営の推進という時流もサービスの開発・提供に追い風となり、周りが背中を押してくれたこともチャレンジにつながった。
西氏は「従業員も」の「も」が重要と強調した。企業は事業継続のために収益とともに、取引基盤の強化に向け顧客満足の向上にも力を注ぐ。そのためには顧客の不満・苦情を減らしカスハラを未然に防ぐ必要があり、その担い手が従業員だ。つまり企業も顧客も、そして従業員も守る事業運営がカスハラ対策に求められるわけだ。
メニューは方針・ルールの策定、予防の取り組み、発生後の取り組みの3段階で構成。カスハラの現状分析から対策方針・規定策定、対策マニュアル・ハンドブック作成、苦情対応研修、カスハラ研修、アフターフォロー教育、再発防止コンサル、WEBモニタリングまで網羅した。従業員がカスハラで困ったときに相談できる体制を作り、安心して働ける環境を整えることが重要になるからだ。
カスハラは、消費者を顧客とするBtoC企業で発生することが多いが、かといって企業間取引のBtoB企業が無関係というわけではない。グループ会社など自社とかかわりが深い取引先の場合、要求が過大であってもなかなか断り切れないのが実情だ。BtoB企業もカスハラの被害者になる可能性がある。
相談窓口があっても、顧客の暴言・暴行、理不尽な要求というカスハラ被害を報告できず抱え込むとストレスがたまり業務パフォーマンスが低下、やがてメンタル不全に陥り休職に追い込まれる。職場に戻って来られずそのまま退職を余儀なくされることもある。こんな悲惨な話を聞いた西氏は「カスハラは人の人生を変えることがあると痛感した」という。
だからこそ企業は法改正による義務化を待つのではなく、自主的・自発的に取り組む「攻めのカスハラ対策」が必要と指摘する。人手不足の今、企業にとって優秀な人材確保は喫緊の課題であり、カスハラストレスによる休・退職を防ぐ取り組みは待ったなしだ。従業員を守る、大切にする企業には優秀な人材が集まるのは明らかだ。企業を守ることにもなるという。
学防ッチャで楽しみながら防災知識学ぶ
▷「カルチャー醸成」 損害保険ジャパンの「支店横断プロジェクト地域貢献タスクチーム」
金沢支店小松支社で生まれた「SOMPOで学防ッチャ」は、パラリンピック種目である球技「ボッチャ」をベースに、楽しみながら防災知識を学べるようにアレンジした職員発案のゲームだ。2024年1月に発生した能登半島地震からの復興応援ツールとして使われている。
「ボッチャを知らず、ゼロからのスタートだった」。小松支社の石原まや主任はこう振り返った。ゲームなので会場に「持ち込みやすい、軽い、高齢者も子供も障害者も楽しく防災を学べる」をコンセプトに開発に着手。「防災を学べるボッチャ」から命名した。
ゲームはチーム対抗。1投ずつ交互に、防災リュックに常に入れておくグッズが描かれている的(パネル)を狙ってボールを投げ、止まった的の点数を競う。重要な防災グッズはポイントが高く、リュックに入らなかったり常備できなかったりするグッズはポイントがマイナスされる。こうして防災知識、中でも災害発生から24時間以内に自ら備えることの大切さを身に着ける。
地震からの復興応援活動は、24年8月に開催された七尾市(石川県)のイベントが最初。その後は能美市SDGs、石川県防災訓練といった自治体と連携したり、企業イベントで使いたいという要請にも応えたりしてきた。

学防ッチャへのニーズが高いと判断した同支店はアワードで「今は1セットしかない。これでは全国展開できない」と訴えた。理解者を増やすため東京本社で体験会を実施(写真・右 上部)。多くの社員が参加しチーム対抗で盛り上がったという。アワードでの発表を機に栃木や鹿児島、長崎などの支店から「ほしい」「使いたい」の手が上がった。本社も訴えに応える形で20セットを用意。今後は地域貢献活動の一環として、地域ごとに中核支店を決めて周囲に貸し出すことで、楽しみながら防災を学べる機会を全国で提供するという。石原氏は「社会貢献は自分たちのやりがいであり、そうしたカルチャーがあって開発できた。学防ッチャで元気づけたい」と話した。
タイトケアで患者と医師が抱える課題解決
▷「SOMPOらしい価値創造」 SOMPO Light Vortexのチーム「医療を手のひらに。」
アピールしたのは、国内初というオンライン診療支援「TytoCare(タイトケア)」。ビデオ通話型オンライン診療により患者は病院までの移動負担も病院での待ち時間もなくせる。医師も送られてきたデータを空き時間に診ることができる。両者にとってうれしい事業だ。医療現場が抱える課題をタイトケアが解決できるからだ。
というのは、聴診器や耳鏡などの医療機器を使って患者の肺や心臓などの聴診音、耳道や鼓膜の観察のほか、体温、咽頭画像などを取得でき(写真・右 下部)、記録したデータは遠隔にいる医師に送信して診察に生かす。従来のオンライン診療は問診に限られるが、「タイトケアでは打診は無理でも聴診、視診は可能になる。過去のデータも蓄積できるので体調の変化が分かり医師の判断も正確さを増す」と事業統括部課長代理の門澤香莉氏は指摘する。
患者側は突然の体調不良のとき医師に診てもらえるか気がかりだ。通院が大変、病院が近くにないといった医療アクセスにも不安をもつ。医師や看護師など働く側も都市部の小児救急などのひっ迫や医療過疎地域への医療提供に対する医師や看護師の労力や費用といった課題を抱える。タイトケアは遠隔医療なのでどこにいても診察できるうえ、ビデオ通話では欠ける医療の質も確保できる。
介護施設や大学病院などで実証実験が進む。入居者のほとんどが要介護度4,5の認知症高齢者という特別養護老人ホームは病院受診のためにつきそう看護師・介護士の数が多く、拘束時間も長いとか、そもそも受診を拒否するといった問題を解決するため実証実験に参加した。結果は期待通りで、関連業務を年間約30%削減できた。施設の看護師長は「タイトケアがなかったころにはもう戻れない」と感謝されたという。
タイトケアで医療提供が効率化される場面は地域に多くある。子供のいる家、保育園・幼稚園、介護施設、在宅医療、中山間地、離島などだ。しかし「診療報酬はオンラインのほうが(対面より)低い」(同)。このため普及に向けて診療報酬の改定時に「タイトケアは『使える』医療機器とアピールする必要がある。同時にオンラインと対面のハイブリッドが医療には欠かせないと伝えていく」考えだ。