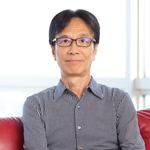第5回
志の高い会社が志の低い会社を食う時代

生物学的には、人間の進化はさまざまな生物よりもずっと下
今回はまず「会社の魅力=ブランド」とは何か、考えていきたいと思います。多摩大学大学院教授の田坂広志氏は、会社の魅力を4段階に区分しています。
(1)知識資本=その人の意義や知恵
(2)関係資本=その人の「人・地域・環境」などの関わり
(3)信頼資本=関わりから生み出されるその人の信頼
(4)評判資本=信頼を基準としての持続的な世の中からの評価
これらは(1)から(4)の順に高まってゆき、最終的にはその企業の「社会資本」となって企業ブランドを形成していくといいます。このことを、目に見える「貨幣資本」とは別に、多様な企業文化形成には欠かせない「つながり資本」と位置づけていきたいと思います。
地球上の生物で一番進化している動物は何でしょうか? 答えは「昆虫」だそうです。人間は、生物学的に言うとずっと下。ちなみに、2位は植物、3位は節足動物とのこと。
ダーウィンは『進化論』で、「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない、唯一生き残るのは、変化できる者である」と説明しています。
再び話を戻しますが、皆さんの会社では、どれくらい人事制度にこのつながり資本を意識して経営を進めていますか? 企業ブランドは人事制度の改革なくして向上しません。企業の多様な文化形成のためにも、目に見えない「信頼」「評判」「承認」といったつながり資本を人事に反映する「トータルリワード」という考え方を念頭において人事制度をつくっていく必要があるのではないでしょうか?。
第一回目にお伝えした「社長のボヤキベスト3」では、お金に直結しなければ社員は行動しない、得られるお金や地位と比べてその仕事が効率的かどうか、という視点で自分の行動を決めてしまうことが背景にあるようです。
ダーウィンの進化論から言えば、「適者生存」、このことをかつてある中小企業の社長は「ダーウィンのいう昆虫こそ、われわれ中小企業だ!!」と喝破しておりました。大きい会社が小さい会社を食う時代から、スピードの速い会社が遅い会社を食う時代へ、そして今は、「志の高い会社が志の低い会社を食う時代」へとなっていくのだということです。
第5回コラム執筆者
【プロフィール】
矢萩大輔

やはぎ・だいすけ 人事・労務代表取締役、日本ES開発協会会長。明治学院大卒。大手ゼネコン勤務を経て1995年、26歳で社会保険労務士として開業。その後、人事・労務を立ち上げ、「人を大切にする経営」を目指す経営者のための日本ES開発協会を主宰。貨幣を超えた新しい時代を生き抜く企業のイノベーションを支えるES(従業員満足)人事制度の導入に力を入れる。
プロフィール

現在社長を務める矢萩大輔が、1995年に26歳の時に東京都内最年少で開設した社労士事務所が母体となり、1998年に人事・労務コンサルタント集団として設立。これまでに390社を超える人事制度・賃金制度、ESコンサルティング、就業規則作成などのコンサルティング実績がある。2004年から社員のES(従業員満足)向上を中心とした取り組みやES向上型人事制度の構築などを支援しており、多くの企業から共感を得ている。最近は「社会によろこばれる会社の組織づくり」を積極的に支援するために、これまでのES(従業員満足)に環境軸、社会軸などのSS(社会的満足)の視点も加え、幅広く企業の活性化のためのコンサルティングを行い、ソーシャル・コンサルティングファームとして企業の社会貢献とビジネスの融合の実現を目指している。
http://www.jinji-roumu.com/inbp.html
http://www.jinji-roumu.com/jinji/
http://www.jinji-roumu.com/es/esr-jinji.html
Webサイト:有限会社 人事・労務