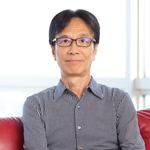第8回
社外の人材・地域とのつながりから新価値創造を

これからは企業のビジョンと個々のミッションの結びつきも重要となる
前回までのコラムで述べてきたように、これからの人事制度は、お金や地位といった"目に見える報酬"だけではなく"目に見えない報酬"を反映させ、ES(従業員満足)という本質に基づいて人が動く仕組みをつくる必要があります。
例えば、目標管理やコンピテンシー評価は、ドラッカーも言っているように、従来は企業のビジョンと個人の目標を結びつけ、社員の自発性を促し、その結果、成果があがるというマネジメントツールでしたが、成果ばかりに焦点があてられ、査定主義、結果主義に陥ってしまいました。ドラッカーの言う「社員の自己の成長を促す」という教育の視点が忘れさられてしまったのです。
今後は、会社の価値観(クレド)と目標管理を結びつけたチャレンジングシートなどのツールを使い、本人の信念を柱に、上司が部下の成長にも積極的に関わり、個人としての業績よりもチームとしての"つながり"を強めるという視点が大切になってきます。そして、「業績に直結するであろう顕在化された行動特性」であるコンピテンシーを指標とした能力評価に関しても「つながりや信頼、評判といった"共感資本"を増やし、社会全体の幸せ・笑顔の創造に直結するであろう顕在化された行動特性」という定義が必要です。
例えば目標管理は、半期ごとの成果を対象としています。しかし、企業ブランドの向上には相当な時間とエネルギーがかかり、他社よりもクリエーティブな商品・サービスをつくるには、ビジネスプロセスそのものを変える必要すらあります。これまでのように半期、長くても1年で成果が出るような単純な仕事では、やればやるほど企業の体力が落ちていくということになりかねません。
今も、定性評価を用いたりマイルストーンを設けるなどして工夫していますが、評価されやすい目先の簡単な目標を立ててしまうといった問題はクリアされません。また、共感資本を高めるには、自社だけでなく、会社以外の人、地域、環境などとのつながりから新たな価値を生み出す取り組みが重要です。そのため、広い視点(空間軸)をもって仕事を創り上げる必要があるのです。
第8回コラム執筆者
【プロフィール】
矢萩大輔

やはぎ・だいすけ 人事・労務代表取締役、日本ES開発協会会長。明治学院大卒。大手ゼネコン勤務を経て1995年、26歳で社会保険労務士として開業。その後、人事・労務を立ち上げ、「人を大切にする経営」を目指す経営者のための日本ES開発協会を主宰。貨幣を超えた新しい時代を生き抜く企業のイノベーションを支えるES(従業員満足)人事制度の導入に力を入れる。
プロフィール

現在社長を務める矢萩大輔が、1995年に26歳の時に東京都内最年少で開設した社労士事務所が母体となり、1998年に人事・労務コンサルタント集団として設立。これまでに390社を超える人事制度・賃金制度、ESコンサルティング、就業規則作成などのコンサルティング実績がある。2004年から社員のES(従業員満足)向上を中心とした取り組みやES向上型人事制度の構築などを支援しており、多くの企業から共感を得ている。最近は「社会によろこばれる会社の組織づくり」を積極的に支援するために、これまでのES(従業員満足)に環境軸、社会軸などのSS(社会的満足)の視点も加え、幅広く企業の活性化のためのコンサルティングを行い、ソーシャル・コンサルティングファームとして企業の社会貢献とビジネスの融合の実現を目指している。
http://www.jinji-roumu.com/inbp.html
http://www.jinji-roumu.com/jinji/
http://www.jinji-roumu.com/es/esr-jinji.html
Webサイト:有限会社 人事・労務