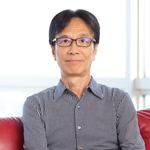第6回
“定番”の商品・サービスは一日にして成らず
“定番”といわれるような商品やサービスには、開発秘話がつきものです。それだけ、定番の創出には創意工夫や試行錯誤が必要だということかもしれません。すばらしいアイデアは重要ですが、それらを受け入れられる商品やサービスへと発展させるためには、長い歳月をかけて磨き上げねばならないケースも少なくありません。
たとえばみなさんご存じの織田信長。彼が「天下布武」というコンセプトを掲げて活動を始めたのは、美濃攻略の後です。それまでに何度も失敗を重ねながらも、兵農分離や長槍の実用化といった施策を次々と実行し、独自の軍団を作っていきました。しかも信長は、この一連の作業に7年もの時間を費やしています。私は、信長が横死する1582年の本能寺の変までの大躍進は、この7年にわたる準備があったからだと思うのです。
では、現代はどうでしょう。思いだけが先行し“7年もかけていられるか”とばかりに猪突(ちょとつ)猛進するケースが散見されます。社長だけが突っ走ってしまい、「こんな素晴らしい理念を掲げているのに、社員も世の中も分かってくれない」「いつかは分かるはずだ。出るくいは打たれない」とばかりにお金を借りまくって破滅するといった例を何件も見ています。それに対するまわりの評価は「世のために頑張っていた素晴らしい人なのに、いい人は成功できないね…」となるわけです。
志の高い社長さんたちには「社長自身が組織の状態を省みることなく理想に突っ走ってしまうことが原因で、会社が立ち行かなくなるケースが非常に多い」ということを忠告したいと思います。これはとても大切な知見だと思います。
弊社は「勤労感謝の日」に日本橋から日光までの143キロを4日間かけて歩き通すイベントを行っていますが、こうしたイベントでさえ2004年に構想を練ってから形になるまでに4年を費やしています。
私がお世話になっている越後湯沢の老舗旅館の一つである「HATAGO井仙」の経営者は「『旅籠(はたご)』というコンセプトを完成させるまでに8年の歳月がかかった」と話してくださいました。
商品サービスを創り上げ、それらが社会に認められるまでには、仮説と検証を繰り返し続けていく必要があるのです。
第6回コラム執筆者
【プロフィール】
矢萩大輔

やはぎ・だいすけ 人事・労務代表取締役、日本ES開発協会会長。明治学院大卒。大手ゼネコン勤務を経て1995年、26歳で社会保険労務士として開業。その後、人事・労務を立ち上げ、「人を大切にする経営」を目指す経営者のための日本ES開発協会を主宰。貨幣を超えた新しい時代を生き抜く企業のイノベーションを支えるES(従業員満足)人事制度の導入に力を入れる。
プロフィール

現在社長を務める矢萩大輔が、1995年に26歳の時に東京都内最年少で開設した社労士事務所が母体となり、1998年に人事・労務コンサルタント集団として設立。これまでに390社を超える人事制度・賃金制度、ESコンサルティング、就業規則作成などのコンサルティング実績がある。2004年から社員のES(従業員満足)向上を中心とした取り組みやES向上型人事制度の構築などを支援しており、多くの企業から共感を得ている。最近は「社会によろこばれる会社の組織づくり」を積極的に支援するために、これまでのES(従業員満足)に環境軸、社会軸などのSS(社会的満足)の視点も加え、幅広く企業の活性化のためのコンサルティングを行い、ソーシャル・コンサルティングファームとして企業の社会貢献とビジネスの融合の実現を目指している。
http://www.jinji-roumu.com/inbp.html
http://www.jinji-roumu.com/jinji/
http://www.jinji-roumu.com/es/esr-jinji.html
Webサイト:有限会社 人事・労務