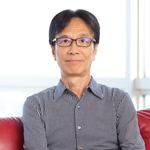第9回
目標管理は運用過程が非常に重要
有限会社 人事・労務 執筆

理念・ビジョンを意識した信条と結びつきがある目標設定を
これまでお伝えしてきた通り、人事評価は成果、発揮能力、執務態度という、大きく3つの視点に分けられます。その中で「成果評価」は、すでにアウトプットされた結果を評価するものです。
一般的には、期初などに上司と部下が会社目標に従って各個人の目標を設定し、その期が終わった段階でどこまでその目標が達成できていたかを確認しあう制度です。点数化された達成度は、賞与などの処遇にかなり直接的に反映されることも多く、成果主義賃金制度とセットで多くの企業で採用されています。
しかし、目標管理制度は本来、社員と会社が同じ目標を持ち、それぞれの役割を認識した上でその達成のために心を一つに努力するためのいわばコミュニケーションツールなのです。もちろん、それぞれが責任を持つために割り当てられた目標が結果として達成された場合に、賞与などに反映させることは重要です。
しかしそれ以上に、会社と社員が目標を共有し、それに向かって努力し、その結果が良かった場合には、それを共に喜び、良くなかった場合には、その原因を一緒になって考え次に生かしていくということが重要なのです。
誰にでも「上司や周囲から承認されたい」という思いがあるものです。また、「上司や周囲から期待されたい、無視されたくない」という思いも同時にあります。目標管理制度はこういった社員の気持ちに応える非常に優れたツールです。目標管理を運用することで、社員は自ら目標をたてて、その実現に向かうことの大切さ、そして、その目標を達成したときの充実感を感じることができるのです。
また、目標達成のためには、上司や同僚とのコミュニケーションは不可欠です(逆にそのような運用をしなければなりません)。そういったことを通じて、社員はチームで一緒に働く楽しさ、つながりを感じるようになっていくのです。目標が達成されたとき、同じ目標をもって努力してきた仲間や上司とともに喜べることで、よりつながりが強化され、強いチームへ成長してゆくことができるのです。
ですから、目標管理は、アウトプットされた「成果」を測る評価制度ではありますが実はその運用過程が非常に重要なのです。
第9回コラム執筆者
【プロフィール】

畑中義雄
はたなか・よしお
社会保険労務士、人事・労務 チーフコンサルタント、東京都社会保険労務士会福支部長。卸売り専門商社の営業職を経て2001年社会保険労務士試験合格。主に中小企業を中心に事業主の立場にたった経営・人事相談を行う。早くから従業員満足(ES)という視点で「ES向上型人事制度」に取り組み、クライアント企業の活性化と業績アップに貢献。
プロフィール

現在社長を務める矢萩大輔が、1995年に26歳の時に東京都内最年少で開設した社労士事務所が母体となり、1998年に人事・労務コンサルタント集団として設立。これまでに390社を超える人事制度・賃金制度、ESコンサルティング、就業規則作成などのコンサルティング実績がある。2004年から社員のES(従業員満足)向上を中心とした取り組みやES向上型人事制度の構築などを支援しており、多くの企業から共感を得ている。最近は「社会によろこばれる会社の組織づくり」を積極的に支援するために、これまでのES(従業員満足)に環境軸、社会軸などのSS(社会的満足)の視点も加え、幅広く企業の活性化のためのコンサルティングを行い、ソーシャル・コンサルティングファームとして企業の社会貢献とビジネスの融合の実現を目指している。
http://www.jinji-roumu.com/inbp.html
http://www.jinji-roumu.com/jinji/
http://www.jinji-roumu.com/es/esr-jinji.html
Webサイト:有限会社 人事・労務