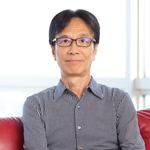第17回
瀬戸際の民主主義と日本に求められる行動 ~レフ・ワレサ氏の説く連帯の重要性~
イノベーションズアイ編集局 編集アドバイザー 鶴田 東洋彦
40年前の水準に後退した民主主義と台頭する権威主義

ロシアが今年を「祖国防衛者の年」と定めたという。ナチス・ドイツに対する戦勝80周年の節目の年と重ね合わせて、プーチン大統領が定めたものだ。そのプーチンはウクライナ侵攻3年目にあたる今年2月、自らが侵略を始めたこの”戦争“を「ネオナチが支配するウクライナ政府が同国東部のロシア系住民を集団殺害し、米欧もロシアの破壊を企てている」と改めて正当化した。
ウクライナに攻め入った時から、常に繰り返してきた言い分で、今さらながら驚く文言でもないが、このプーチンの言葉に象徴される権威主義国家の台頭の背景に民主主義の危機が叫ばれ、米トランプ政権の姿勢が拍車をかけてしまっていることが怖い。
先日、ある雑誌で読んだスウエーデンのシンクタンクの調査によると、現在の民主主義の度合いは約40年前と同じ程度の水準にまで衰退し、その分、権威主義化が進んでしまっているという。北朝鮮しかり、ベラルーシしかり、何よりも中国の習近平の加速度的な独裁化を目の当たりにするにつけても、民主主義の世界的な後退については納得せざるを得ない。
世界の分断に拍車をかけるトランプ政権
トランプ政権が誕生して約4ヶ月、その間に仕掛けた政策、世界主要国を対象とした強硬な相互関税政策、ウクライナ、ロシアとの片務的な停戦交渉、WHO(世界保健機関)や国連人権理事会(UNHRC)をはじめとした主要な国際機関からの脱退など、トランプ氏の行っていることは、明らかに世界の民主化の動きと逆行している。言い換えれば、世界の分断に拍車をかけている。
そんな思いが募る中で、先日4月26日付の朝日新聞に非常に興味深い記事が掲載されていた。共産主義政権下のポーランドで、労組「連帯」を率いて民主化運動を牽引、1989年に社会主義政権で初の非共産党政権を誕生させたレフ・ワレサ元大統領のインタビュー記事である。
後にノーベル平和賞を受賞したワレサ氏の行動が当時の東欧諸国の民主化に弾みをつけ、東西冷戦の象徴でもあった「ベルリンの壁」崩壊につながったことは有名である。ポーランド映画界の巨匠アンジェイ・ワイダ監督によって「ワレサ・連帯の男」のタイトルで映画化もされた。そのインタビューの中でワレサ氏は、社会が独裁化に動いている要因として「人々が現在の民主主義(の在り方)を理解していないし、守ろうともしていないからだ」と断じている。
民主主義後退の背景にあるもの
ワレサ氏の言葉を借りると、民主主義が滑稽な形に後退した背景にあるのは、政治家が自らの選挙区や任期ばかりを気にし、政党も自己利益のためだけに存在するようになり、人々は政治家の一部が「政治マフィア」になっているとみているから信頼も置かない、という。しかも、それは現在進行形でますます悪化しているというのだ。まさに日本の現在の政治にもそのまま当てはまる言葉ではないか。
正直、長くメディアの世界で働いてきた立場にとっては、これほど耳が痛い言葉はない。だが、確かに今の民主主義はただ選挙に行くこと、許容される範囲内だけでの報道の自由があることだけでは成り立たなくなっているのだろう。「従来の民主主義は、もう今の時代では解決方法として合わなくなっている」というワレサ氏の言葉には説得力がある。
この民主主義の後退について、ワレサ氏が示している処方箋は実に明確である。一つ目は2期を超えて政党代表に就くのを禁じること、二つ目は選挙で選ばれた人間を、得票数より多い署名があれば辞めさせるようにすること、三つ目は資金の透明性、という。ワレサ氏の言葉通り、政党代表の任期はそのまま個人の権威増幅に繋がるし、例えば任期を区切ればプーチンの暴挙のような事態は防げたかもしれない。
二つ目の問題を日本の現状に照らし合わせて考えると、現在の兵庫県知事選の問題に当てはまるし、三つ目に至っては自民党が抱え続けている政治資金の不透明な流れ問題そのものではないか。よく我々はウクライナとEUの問題について、ロシアと陸続きにある脅威が「両者を接近させている」と指摘する一方で、「島国の日本は平和ボケだ」と自虐的に語ることは多い。だが、自虐感を語る前に日本の民主主義そのものが後退していることを認識すべきなのだろう。
米国と一緒に後退するな。今こそ連帯を
トランプ政権の姿勢が拍車をかける世界の分断と民主主義の後退。日本の最大の庇護者であり、安全保障も含めて信頼できるパートナーとしてきた米国の後退。日本を突き放すトランプ氏がもたらす損害を最小限に食い止める日本の在り方について、ワレサ氏は明確に言い切っている。
「米国と一緒に後退することは出来ない。(米国に対して)連帯していかねばならない。欧州の連帯に日本も含めて他の国も加わっていく。答えはそこにしかない」。
トランプ政権の強引な手法、MAGA(=アメリカを再び偉大にしよう)という言葉を、長年、米国民に保守的な心の中にある鬱積してきた「不満の暴発」ととらえれば、これはワレサ氏も言うように一時的な病気のようなものかもしれない。事実、過度な関税を戒める動きは共和党内の側近からも出始めている。トランプ氏の強権的手法に陰りも見えてきたのだ。
関税問題だけではない。幸いなことに無謀とも思えたトランプ政権の中からも、民主主義の矜持ともいえる「議論して決めるべき」という意見が萌芽している。日本がここで後退の局面から踏みとどまるためにも、必要なのはワレサ氏の言う欧州や近隣諸国を交えての徹底した“連帯”であり、議論であろう。民主主義が「瀬戸際に立つ」と言われる時代だけに、この連帯という言葉の持つ意味をより重く考え、日本政府も行動すべき時ではないか。
プロフィール

イノベーションズアイ編集局
編集アドバイザー
鶴田 東洋彦
山梨県甲府市出身。1979年3月立教大学卒業。
産経新聞社編集局経済本部長、編集長、取締役西部代表、常務取締役を歴任。サンケイ総合印刷社長、日本工業新聞(フジサンケイビジネスアイ)社長、産経新聞社コンプライアンス・アドバイザーを経て2024年7月よりイノベーションズアイ編集局編集アドバイザー。立教大学、國學院大學などで「メディア論」「企業の危機管理論」などを講義、講演。現在は主に企業を対象に講演活動を行う。ウイーン国際音楽文化協会理事、山梨県観光大使などを務める。趣味はフライ・フィッシング、音楽鑑賞など。
著書は「天然ガス新時代~機関エネルギーへ浮上~」(にっかん書房)「K字型経済攻略法」(共著・プレジデント社)「コロナに勝つ経営」(共著・産経出版社)「記者会見の方法」(FCG総合研究所)など多数。
- 第17回 瀬戸際の民主主義と日本に求められる行動 ~レフ・ワレサ氏の説く連帯の重要性~
- 第16回 今こそ学ぶべき榎本武揚の足跡
- 第15回 企業に求められる“発達障害グレーゾーン”対策
- 第14回 誰がトランプに警鐘を鳴らすのか
- 第13回 山茶花に「新しい年」を思う
- 第12回 “冒険心”を掻き立てられる場所
- 第11回 再び“渚にて”を読んで、現在を思う
- 第10回 エンツォ・フェラーリの“凄み”
- 第9回 久保富夫氏と「ビルマの通り魔」
- 第8回 スコットランドのパブに「サードプレイス」を思う
- 第7回 沖縄戦に散った知事「島田叡(あきら)」
- 第6回 友人宅の藤棚に思うこと
- 第5回 「まちライブラリー」という居場所
- 第4回 樋口一葉と水仙
- 第3回 「ケルン・コンサート」という体験
- 第2回 諫言(かんげん)に耳を傾ける
- 第1回 ”桜の便り”が待ち遠しいこのごろ