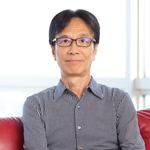第81回
【デジタル給与払い最前線】PayPay“100社突破”が突き付ける 中小企業の選択
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原 京二
1. PayPayの導入企業100社突破が意味するもの
2024年4月11日、PayPay株式会社が提供するデジタル給与払いサービス「PayPay給与受取」の導入企業数が、ついに100社を突破したと発表されました。吉野家、サカイ引越センターといった有名企業だけでなく、中堅・中小企業にも導入が広がりつつあることが注目されています。
さらに、OBCが提供する労務クラウド「奉行Edge」とのAPI連携によって、従業員の口座情報の入力作業が、従来の2分から最短15秒へと大幅に短縮されました。企業にとっては作業の効率化という大きなメリットがあり、従業員にとっては給与の即時受取が可能になるという利便性が加わります。この“企業と従業員の双方にとってのメリット”が、導入を後押しする追い風となっているのです。
中小企業においても「うちにはまだ早い」ではなく、「今こそ検討すべき時期」になってきています。
2. 制度の仕組みと法的背景
このようなデジタル給与払いの仕組みが実現した背景には、2023年4月に施行された労働基準法施行規則の改正があります。これにより、厚生労働大臣が指定した「資金移動業者」(たとえばPayPayやLINE Payなど)が、銀行口座ではなく電子マネー口座へ給与を振り込むことが可能となりました。
ただし、いくつかの条件があります。まず、従業員本人の同意が必要であること。また、電子マネー口座の残高上限は100万円に制限されており、破綻時における保証スキームや、即時払い出しの可否など、一定の要件を満たす必要があります。
つまり、現金払いや銀行振込という従来の支払い手段は残されたままであり、あくまで「選択肢の一つ」として、デジタル給与払いが加わったという位置づけになります。
3. 中小企業が注目すべき三つの理由
デジタル給与払いは、大企業だけのものではありません。むしろ中小企業こそが、次の三つの観点から注目すべきといえるでしょう。
(1) 採用・定着競争の武器に
若年層や外国人労働者にとって、銀行口座の開設は面倒であり、時間もかかります。その点、スマートフォンひとつで給与を受け取れる仕組みは、働き手にとって大きな魅力です。特に、短期雇用やアルバイト層を多く抱える業種では、「即日受取OK」の職場というだけで応募率が高まることが期待できます。
(2) コストと業務効率の改善
通常の銀行振込では、1件ごとに手数料が発生します。一方、PayPay給与受取では、企業側の振込手数料がかからない点が特徴です。さらに、現金の準備や手渡し、振込情報の確認といった事務作業が不要になり、経理や人事部門の負担を大きく減らすことができます。
(3) キャッシュレス化との相乗効果
給与受取後、すぐにPayPay残高を活用できるという特性を活かせば、社内の福利厚生制度とも連携可能です。たとえば、社員食堂や社内売店をキャッシュレス化したり、PayPayで使えるポイントを会社独自で付与することで、従業員満足度を高める施策につなげることができます。
4. 導入メリットとデメリットを天秤にかける
デジタル給与払いの導入には、企業にも従業員にもさまざまなメリットがある一方で、一定のリスクや対応すべき課題も存在します。
まず従業員の立場で見てみると、最大のメリットは、いつでも24時間好きなタイミングで給与を受け取れるという利便性です。急な出費があっても、即時に受け取れることで立替えの必要がなくなり、生活の安定にもつながります。ただし一方で、スマートフォンが紛失したり故障した場合には、ロック解除や再設定といった手間が発生する点には注意が必要です。
次に企業側の視点からは、振込手数料の削減や現金管理の省略、さらにAPI連携による自動化によって、経理・人事の業務が大きく軽減されるというメリットがあります。月に数時間単位の作業削減も見込まれ、コスト効率化に直結します。一方で、導入にあたっては労使協定の締結や従業員からの同意取得が必要であり、その準備や説明対応に一定の手間がかかります。また、新制度に関する社内の問い合わせに対応する体制も整える必要があります。
ガバナンスの面では、PayPayをはじめとした資金移動業者には、万が一破綻した場合でも利用者の資金が保護される保証制度が用意されており、安心して利用できる環境が整っています。しかし、100万円を超える高額の給与支給については、法令により従来どおり銀行振込で行う必要があるため、併用による運用ルールの整理が求められます。
このように、単なる「コスト削減策」として導入を判断するのではなく、従業員の利便性向上や採用競争力の強化といった“複合的な効果”をどう評価するかが、経営判断において重要なポイントとなります。
5. 中小企業版・導入ステップガイド
では、実際に中小企業が導入を進めるには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。以下に、5ステップで整理しました。
ステップ1:社内ヒアリング
まずは、従業員の中に「即時受取」を希望する声がどれほどあるのかを調べましょう。正社員だけでなく、パート・アルバイトも含めてニーズを把握することが大切です。
ステップ2:労使協定案の作成
給与の支払い手段を変えるには、就業規則や賃金規程に明記する必要があります。厚労省が公開しているモデル条文を参考に、資金移動業者口座への支払いを「一部または全部」として記載しましょう。
ステップ3:サービス比較
PayPay以外にも、LINE Pay、楽天ペイ、au PAYなど複数の選択肢があります。手数料の有無、API連携の有無、サポート体制などを比較検討しましょう。
ステップ4:試行導入
いきなり全社員へ導入せず、「希望者のみ」「給与の20%まで」などの条件でテスト運用を行いましょう。これにより、制度運用上の課題を事前に把握できます。
ステップ5:全社展開とフォロー体制
導入後は、従業員向けの操作マニュアル、よくある質問の整理、毎月の残高確認レポートなどを整備し、スムーズな運用を目指しましょう。
6. ケーススタディで見る効果
実際に導入して成果を上げている企業も増えてきました。いくつかの事例をご紹介します。
飲食チェーンA社(従業員200名)
アルバイト向けに給与前払いアプリとデジタル給与払いを併用し、入社1か月以内の離職率が15%から8%に改善。振込手数料も年間で120万円削減できたとのことです。
製造業B社(外国人実習生30名含む)
外国人従業員への給与送金にかかっていた海外送金手数料をPayPay送金に切り替えた結果、年間で100万円以上のコスト削減が実現しました。
ITベンチャーC社(平均年齢28歳)
オンライン社員食堂とPayPay残高を連携させることで、社員のランチをキャッシュレス化。社員の満足度が高まり、エンゲージメントスコアは前年同季比で+12ポイント上昇しました。
7. 他社サービス比較の視点
デジタル給与払いに対応するサービスは、PayPayだけではありません。近年では、LINE Pay、楽天ペイ、au PAYなども厚生労働大臣の指定を受けており、資金移動業者としてデジタル給与市場に続々と参入しています。今後はさらに多くの事業者が参入し、選択肢は広がっていくと考えられます。
そのため、導入を検討する際には、「どのサービスを選ぶか」という視点が非常に重要になります。ここでは、中小企業が比較時にチェックすべき3つの主要ポイントを詳しくご紹介します。
① 企業向けの料金体系
まず確認すべきは、サービスの利用にかかる企業側の料金体系です。大きく分けると以下のような種類があります。
月額固定型:一定の月額料金を支払って利用する方式。従業員数に応じた価格設定の場合もあります。
従量課金型:送金件数や金額に応じて都度料金が発生するタイプ。パート・アルバイトの人数が多い事業所ではコストが読みにくくなることがあります。
無料型:企業側のコスト負担がゼロのサービスも存在します。たとえばPayPay給与受取は、企業がPayPay残高で給与を送る分には原則として手数料が発生しません。
自社の規模や利用頻度に合ったコスト体系を選ぶことで、不要な支出を抑えることができます。
② 勤怠・給与システムとの連携可否
次に大事なのが、自社で使っている勤怠管理・給与計算システムとのAPI連携が可能かどうかという点です。
たとえば、SmartHRやfreeeなどクラウド型の人事労務ソフトを使っている企業であれば、それらと連携できるサービスを選ぶことで、手作業によるデータ入力やミスが大幅に減ります。最近では「奉行Edge」や「ジョブカン」といったシステムとの連携も進んでおり、給与データの出力から送金までを自動化できる仕組みが整いつつあります。
連携の可否は、導入後の業務効率化の度合いを大きく左右するため、見逃せないポイントです。
③ 従業員側の出金利便性とコスト
そして、従業員の立場から見た「使いやすさ」も、サービス選定の際に必ず考慮すべき点です。
具体的には、デジタル給与として受け取ったお金を銀行口座に出金する際に手数料がかかるかどうかが重要になります。サービスによっては、指定口座への出金に手数料が発生する場合があり、従業員にとって不満の原因となることがあります。
また、出金のタイミングや反映速度もサービスごとに異なります。たとえば、即時出金が可能なサービスもあれば、1営業日以上かかるところもあります。スムーズに使えるかどうかは、従業員の利用率や満足度を左右します。
仮に企業が便利な仕組みを導入しても、従業員が「結局、現金化に時間や手数料がかかるなら意味がない」と感じてしまえば、制度は定着しません。
これらの比較ポイントを踏まえると、企業としては「コスト」「業務効率」「従業員満足度」のバランスを見ながら、自社にとって最適なサービスを選ぶことが求められます。
特に中小企業の場合、管理コストを最小限に抑えながらも、従業員にとって不満のない仕組みを導入することが、成功のカギとなります。
8. 今後の展望――リアルタイムファイナンス時代へ
デジタル給与払いの広がりは、月1回払いという“常識”を見直す契機となっています。今後はスポットワークや短期雇用に合わせて、「勤怠→即時集計→日次払い→電子マネー反映」といったリアルタイムな給与支払いの仕組みが普及する可能性があります。
また、日本政府はデジタル円(中央銀行デジタル通貨:CBDC)の実証実験も進めており、公的給付や税金還付も含めたデジタル送金の仕組みが整えば、企業の資金繰りや従業員の生活支援に新たな地平が開けるでしょう。
9. まとめ――“静観”か“追随”か
PayPayが提供する「デジタル給与払い」サービスの導入企業が100社を突破したという事実は、非常に大きな意味を持っています。これは、制度としての枠組みが整ったというだけでなく、実際に現場で運用できる段階に入ったことを明確に示すターニングポイントです。
これまで、多くの企業が「制度としては知っているが、導入に踏み切るのはまだ早いのでは」と様子見の姿勢を取ってきました。しかし、飲食業や製造業、IT企業など、さまざまな業種での実績が出始めている今、もはや“静観”しているだけでは、他社に差をつけられてしまう時代に突入しています。
特に重要なのは、人材確保・定着の観点です。若い世代や外国人労働者を中心に、「すぐに給与を受け取れる職場」が当たり前のニーズになりつつあります。給与の受け取り方法に選択肢を持たせるだけで、「この会社は柔軟で、時代の変化に対応している」と好印象を与えることができ、応募者数の増加や定着率の改善にもつながります。
一方で、制度の導入には慎重な準備も必要です。従業員の同意を得るための説明、就業規則や賃金規程の整備、情報システムの連携など、いくつかの“ハードル”は確かに存在します。しかし、これらは一気に進める必要はなく、段階的に導入していくことで、十分に対応可能です。
成功のカギを握るのは、「社内だけで抱え込まないこと」です。労務に詳しい社会保険労務士、資金移動の仕組みに強い金融機関の担当者、給与システムやクラウドサービスを扱うITベンダーなど、外部の専門家と連携し、一つの“プロジェクト”として進める姿勢が大切です。
実際、社員数十名規模の企業でも、社労士と一緒に就業規則を整備し、ベンダーとAPI連携を実装しながら段階的に展開した成功例が数多く報告されています。難しそうに見える制度も、「やり方さえ間違えなければ、中小企業でもちゃんと運用できる」のです。
今、私たちは、給与という“当たり前すぎて見直す機会のなかった仕組み”に、新しい選択肢が加わった時代にいます。これを単なる技術革新と捉えるのではなく、「社員に寄り添う経営」へと一歩踏み出すためのチャンスと考えることが重要です。
デジタル給与払いの導入は、単なる制度変更ではありません。経営者が“人を大切にする姿勢”をカタチにし、採用や定着、組織の一体感までを変えていく、「給与DX」への第一歩なのです。
ぜひ今こそ、御社の給与の仕組みを見直し、社員の未来、そして会社の未来をより良くする取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。
プロフィール

一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
- 第81回 【デジタル給与払い最前線】PayPay“100社突破”が突き付ける 中小企業の選択
- 第80回 50人未満でも義務化へ──中小企業が取り組むべきメンタルヘルス対策
- 第79回 「『3年以内離職率30%』を逆手に取る!中小企業の新人定着成功術」
- 第78回 「静かな退職」を防ぐ!中小企業ができる5つの具体策
- 第77回 育児介護休業法の改正が中小企業に与える影響
- 第76回 HR分野におけるAIの活用とその課題
- 第75回 変化する採用市場と学生・企業のあるべき姿勢
- 第74回 2025年の採用戦略:中小企業が勝ち抜くための5つの鍵
- 第73回 令和7年度の助成金最新情報
- 第72回 変革の時代:2025年労働基準法改正が描く新しい働き方の未来
- 第71回 法改正に対応!中小企業が知っておくべきカスタマーハラスメント対策のポイント
- 第70回 中小企業経営者のための「賃上げ支援助成金パッケージ活用術」
- 第69回 2025年春闘:中小企業の挑戦と変革の時
- 第68回 定年延長か継続雇用か ? データから見る高齢者雇用の最適解
- 第67回 2025年、退職代行サービス利用が過去最高に ~ 現代の労働環境が映し出す課題とは
- 第66回 2025年育児介護休業法改正と企業が行うべき対応
- 第65回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その3)
- 第64回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その2)
- 第63回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その1)
- 第62回 女性活躍推進法の改正がもたらす未来と企業への影響
- 第61回 大企業でも導入が進む「パーソナル雇用制度」
- 第60回 最低賃金1500円時代における給与の決め方
- 第59回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策(その3)
- 第58回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策(その2)
- 第57回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策
- 第56回 中小企業が注目すべきミドル世代の賃金上昇と転職動向~経験豊富な人材の採用でビジネス成長を加速
- 第55回 中小企業が賃金制度を考えるときに知っておきたい基本ポイント
- 第54回 2024年10月からの社会保険適用拡大、対応はお済みですか?
- 第53回 企業と競業避止契約の今後を考える
- 第52回 令和7年度 賃上げ支援助成金パッケージ:企業の成長と持続的な労働環境改善に向けて
- 第51回 解雇の金銭解決制度とその可能性 〜自民党総裁選における重要テーマ〜
- 第50回 令和7年度予算概算要求:中小企業経営者が注目すべき重要ポイントと支援策
- 第49回 給与のデジタル払いの導入とその背景
- 第48回 最低賃金改定にあたって注意すべきこと
- 第47回 最低賃金50円アップ時代に中小企業がやるべきこと
- 第46回 本当は怖い労働基準監督署の調査その4
- 第45回 本当は怖い労働基準監督署の調査(その3)
- 第44回 本当は怖い労働基準監督署の調査 その2
- 第43回 本当は怖い労働基準監督署の調査
- 第42回 初任給横並びをやめたパナソニックHD子会社の狙い
- 第41回 高齢化社会と労働力不足への対応:エイジフレンドリー補助金の活用
- 第40回 助成金を活用して人事評価制度を整備する方法
- 第39回 採用定着戦略サミット2024を終えて
- 第38回 2025年の年金制度改革が中小企業の経営に与える影響
- 第37回 クリエイティブな働き方の落とし穴:裁量労働制を徹底解説
- 第36回 昭和世代のオジサンとZ世代の若者
- 第35回 時代に合わせた雇用制度の見直し: 転勤と定年の新基準
- 第34回 合意なき配置転換は「違法」:最高裁が問い直す労働契約の本質
- 第33回 経営課題は「現在」「3 年後」「5 年後」のすべてで「人材の強化」が最多
- 第32回 退職代行サービスの増加と入社後すぐ辞める若手社員への対応
- 第31回 中小企業の新たな人材活用戦略:フリーランスの活用と法律対応
- 第30回 「ホワイト」から「プラチナ」へ:働き方改革の未来像
- 第29回 初任給高騰時代に企業が目指すべき人材投資戦略
- 第28回 心理的安全性の力:優秀な人材を定着させる中小企業の秘訣
- 第27回 賃上げラッシュに中小企業はどのように対応すべきか?
- 第26回 若者の間で「あえて非正規」が拡大。その解決策は?
- 第25回 「年収の壁」支援強化パッケージって何?
- 第24回 4月からの法改正によって労務管理はどう変わる?
- 第23回 4月からの法改正によって募集・採用はどう変わる?
- 第22回 人材の確保・定着に活用できる助成金その7
- 第21回 人材の確保・定着に活用できる助成金その6
- 第20回 人材の確保・定着に活用できる助成金その5
- 第19回 人材の確保・定着に活用できる助成金その4
- 第18回 人材の確保・定着に活用できる助成金その3
- 第17回 人材の確保・定着に活用できる助成金その2
- 第16回 人材の確保・定着に活用できる助成金その1
- 第15回 リモートワークと採用戦略の進化
- 第14回 「社員」の概念再考 - 人材シェアの新時代
- 第13回 企業と労働市場の変化の中で
- 第12回 その他大勢の「抽象企業」から脱却する方法
- 第11回 Z世代から選ばれる会社だけが生き残る
- 第10回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(後編)
- 第9回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(前編)
- 第8回 中小企業のための「集めない採用」~ まだ穴のあいたバケツに水を入れ続けますか?
- 第7回 そもそも「正社員」って何ですか? - 新たな雇用形態を模索する時代へ
- 第6回 成功事例から学ぶ!パーソナル雇用制度を導入した企業の変革と成果
- 第5回 大手企業でも「パーソナル雇用制度」導入の流れ?
- 第4回 中小企業の採用は「働きやすさ」で勝負する時代
- 第3回 プロ野球選手の年俸更改を参考にしたパーソナル雇用制度
- 第2回 パーソナル雇用制度とは? 未来を切り開く働き方の提案
- 第1回 「労働供給制約社会」がやってくる!