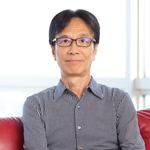第80回
50人未満でも義務化へ──中小企業が取り組むべきメンタルヘルス対策
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原 京二
はじめに
2025年3月14日、政府は「労働安全衛生法」の改正案を発表しました。今国会で成立すれば、公布から3年以内にこれまで50人以上の事業所で義務付けられていたストレスチェック制度を、50人未満の事業所にも適用となり、中小企業への健康管理が大きく変わります。
この改正により、小規模事業所でもメンタルヘルス対策が強化され、労働者の心の健康を守る取り組みがより一層求められることになります。 本コラムでは、今回の改正の背景や内容、事業者や労働者への影響、そしてストレスチェックの重要性について詳しく解説していきます。
1. ストレスチェック制度とは何か?
「ストレスチェック」と聞くと、ただのアンケートや心理テストのように感じる方も多いかもしれません。しかし実際は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐために設計された、非常に重要な制度です。
この制度は、2015年12月に施行された労働安全衛生法の改正によって導入されました。目的は、従業員が自らのストレス状態に気づき、必要に応じて医師のサポートを受けることで、うつ病などの深刻な精神疾患を未然に防ぐこと。つまり、個人の健康を守るだけでなく、企業全体としての健康経営の第一歩でもあるのです。
では、実際にどのような流れで実施されているのでしょうか。
これまでの制度では、「常時50人以上の労働者がいる事業所」に、年1回のストレスチェック実施が義務づけられていました。基本的な流れは以下のとおりです。
・従業員がストレスチェックを受ける(標準的には57項目の質問票を用いた自己評価)
・結果を本人に直接通知(この時点では、事業者側に個人の結果は伝えられません)
・結果が「高ストレス」と判定された従業員が希望した場合、医師との面談を受ける
・医師の意見に基づいて、必要に応じて職場環境の改善や配置転換などの措置が検討される
このように、ストレスチェック制度は、「従業員の気づき」→「希望者への支援」→「職場環境の見直し」という流れを重視しています。
とくに注目したいのは、個人のプライバシーが守られる設計になっているという点です。事業者は、本人の同意がない限り、個々の結果を知ることはできません。これは、従業員が安心してチェックを受けられるよう配慮されたルールです。
これまでは50人以上の事業所のみが義務対象でしたが、それ以下の規模の事業所には努力義務(できるだけ実施してください、という推奨)にとどまっていました。ところが今回の法改正によって、その位置づけが大きく変わろうとしています。
この制度は、やり方を間違えなければ、経営の武器になります。従業員の状態を早期に把握し、適切なフォローや環境改善につなげることで、職場の空気も大きく変わります。まずはこの制度の「基本」を押さえることが、今後の準備の第一歩です。
2. なぜ50人未満にも義務化されるのか
今回の法改正で大きなポイントとなるのが、従来「努力義務」にとどまっていた50人未満の事業所にも、ストレスチェックの義務が拡大されるという点です。これには、国が見過ごせないと判断した社会的な背景があります。以下の3つの観点から、その理由を見ていきましょう。
① 中小企業におけるメンタルヘルス問題の深刻化
ストレスや心の不調は、もはや大企業だけの問題ではありません。むしろ中小企業の現場では、少人数ゆえに1人あたりの業務負荷が重くなりやすく、上司や同僚との関係性も密接で、逃げ場がないという特性があります。
厚生労働省の調査によると、50人未満の小規模事業所における「精神疾患に起因する労災請求」は年々増加傾向にあります。これは、職場のメンタルヘルスが適切に管理されていない環境において、重大な問題が発生している証拠でもあります。
特に中小企業では、人事部門や産業医が常駐していないことが多く、早期対応が遅れやすいという課題もあります。ストレスチェックの義務化は、こうした現場に「心の健康管理の仕組み」を入れるための第一歩なのです。
② 労働力不足と業務過多による心理的負担の増大
日本全体が直面している「少子高齢化」によって、労働力人口は減少し続けています。その結果、どの業界でも人手不足が常態化し、一人の社員が複数の業務を抱える状況が当たり前になっています。
中小企業では特に、「辞められると代わりがいない」「一人休むと業務が回らない」といった事情が重なり、慢性的なプレッシャーが社員を追い詰める構図ができあがっています。
経営者にとっても頭が痛い問題ですが、こうした心理的ストレスが積み重なると、やがてメンタル不調からの休職・離職につながり、さらに人手が足りなくなるという「負の連鎖」が起こります。
③ 精神疾患による休職・退職の増加と経営リスク
精神的な理由による休職や退職は、従業員本人の人生だけでなく、会社経営にも大きな影響を及ぼします。特に中小企業にとっては、たった一人の離脱でもダメージが大きく、取引や納期に支障をきたすこともあります。
さらに、「うつで社員が辞めた」「職場の対応が悪かった」といった情報が、SNSや口コミなどで外部に広がれば、採用活動にも影響を与えるリスクがあります。今の時代、働く側も「メンタルヘルスへの配慮がある会社か」を企業選びのポイントとして重視しているのです。
こうした現状を踏まえ、政府はストレスチェック制度の義務範囲を50人未満の事業所にも拡大する決断を下しました。これは中小企業にとって、単なる法対応ではなく、「人を守る仕組み」そして「人が辞めない職場」をつくるきっかけになる可能性を秘めています。
3. 改正案の内容と今後のスケジュール
政府が発表した「労働安全衛生法の改正案」では、ストレスチェック制度の義務対象を50人未満の事業所にも拡大する方針が打ち出されました。この法案が今国会で成立すれば、公布から3年以内に施行される見込みです。
では実際に、どのような内容が想定されているのでしょうか。ここでは、現時点でわかっている範囲で制度の具体像とスケジュールについて解説します。
<スケジュールの見通し>
現時点でのスケジュールは以下のとおりです。
・2025年春~夏:国会での審議・成立見込み
・2025年内:法案が公布される可能性
・2028年頃までに:改正法の施行、全国すべての事業所が義務対象へ
つまり、50人未満の事業所も遅くとも3年以内に対応が求められることになるということです。対応にあたっては、準備期間があるとはいえ、余裕を持って早めに情報収集や体制整備に着手することが重要です。
<実施方法はどう変わるのか?>
基本的な仕組み自体は、すでに義務化されている50人以上の事業所と同じです。ただし、小規模な事業所にとっても実施しやすいよう、以下のような工夫や柔軟な対応策が検討されているとされています。
・簡易版のストレスチェックの導入
→ 設問数を少なくするなど、負担軽減の工夫がされる見込みです。
・オンラインでの実施を推奨
→ パソコンやスマホで気軽に受けられるようにし、紙の配布・回収といった手間を省けます。
・外部専門家との連携支援の強化
→ 産業医やカウンセラーとの連携が難しい中小企業向けに、自治体や外部団体とつなぐ仕組みが整備される可能性があります。
<負担が増える?事業者の不安への対策>
多くの中小企業経営者にとって、「制度が義務化される」という話を聞けば、真っ先に浮かぶのは「コストや手間がかかるのでは?」という懸念でしょう。たしかに、従業員への説明や実施体制の構築、外部委託費用など、ゼロでは済まないかもしれません。ただし、政府も中小企業の実情を踏まえた支援策の整備を進めているとされています。たとえば以下のような支援策が想定されています。
・ストレスチェック実施のための助成金の整備
・無料または低コストで使える簡易ツールの提供
・労働局や商工会議所によるサポートの強化
つまり、「義務だから仕方なくやる」のではなく、「上手に活用すれば企業にとってプラスになる制度」として取り組むことがポイントになります。
4.ストレスチェック制度がもたらすポジティブな効果
ストレスチェック制度と聞くと、「またひとつ義務が増えるのか」「対応が大変そうだ」といったネガティブな印象を抱く経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際には、正しく導入・活用すれば、企業にも従業員にも多くのメリットがあります。
ここでは、制度導入がもたらすポジティブな効果を、事業者と労働者のそれぞれの立場から整理してみましょう。
【事業者側のメリット】
① メンタルヘルス不調の早期発見
ストレスチェックを実施することで、問題が表面化する前に従業員の不調の兆しに気づくことが可能になります。休職や離職といった“事後対応”になる前に、早期のケアや配置転換、業務調整といった予防的な措置が取れるようになります。
② 休職・退職リスクの低減
メンタル不調による離職は、業務負担の増加や人材の流出といった形で企業に大きなダメージを与えます。ストレスチェックの導入は、定着率の改善や採用コストの抑制といった、経営面での成果にもつながっていきます。
③ 労働生産性の向上
心身ともに健康な従業員は、集中力や判断力、生産性が高く、チームにも好影響をもたらします。職場全体の“空気”が改善され、活気ある現場づくりにもつながります。
④ ハラスメントやトラブルの予防
ストレスの高い職場では、パワハラ・モラハラなどのトラブルが起きやすくなります。ストレスチェックの結果を踏まえて職場環境の課題を可視化し、組織的に対応することで、未然に防ぐことができます。
【労働者側のメリット】
① 自身の状態に気づける
多くの人は、自分のストレス状態を正確に把握できていません。ストレスチェックを通じて、「自分は今、疲れているんだ」「早めにケアが必要かも」と自覚することで、早めの対処が可能になります。
② 正式な相談ルートができる
「誰に相談していいかわからない」「上司に話すのは不安」という社員でも、ストレスチェックから医師面談につながるルートがあることで、安心して相談できる環境が整います。
③ 心のケアが当たり前の文化になる
制度の導入をきっかけに、「心の健康も大事にする職場」というメッセージが社内に広がります。これは、特に若年層の社員にとって、働く職場を選ぶ大きな安心材料にもなります。
以上のように、ストレスチェック制度は導入そのものよりも、「どう使うか」「どう職場に浸透させるか」が鍵です。制度をうまく活かせば、結果として会社の魅力が高まり、社員が辞めにくく、働きがいのある職場づくりにつながるのです。
5. 制度対応をきっかけに、働きやすい職場づくりへ
ストレスチェック制度の義務化は、たしかに“新しい負担”のように見えるかもしれません。しかし、経営者の視点を少し変えてみると、これは単なる「法令対応」ではなく、会社をより良くするチャンスでもあります。
今、多くの中小企業が悩んでいるのは、「人が集まらない」「採用してもすぐ辞める」「職場がギスギスしている」といった“人の問題”ではないでしょうか。ストレスチェックの導入は、まさにそうした課題の根本的な改善のきっかけになり得ます。
<ストレスチェックは“コスト”ではなく“投資”>
制度対応にあたっては、質問票の配布、外部専門家との契約、面談対応など、たしかに一定の手間や費用がかかります。ですが、それによって社員の健康が守られ、離職を防ぎ、生産性が上がるとすれば、それは十分にリターンが見込める“投資”です。
とくに中小企業にとっては、「いかに今いる人材に長く、元気に働いてもらうか」が経営のカギです。ストレスチェックのような制度を上手に活用することは、「働き続けたいと思える職場づくり」に直結します。
<制度は“やらされるもの”ではなく“活かすもの”>
法律だから仕方なくやる、という姿勢では、制度は形骸化します。チェックを受ける社員側にも不信感が生まれ、「どうせ見ても何も変わらない」と思われてしまっては逆効果です。
逆に、「せっかくチェックをするなら、結果をもとに職場環境を良くしよう」「社員の声を聞いて改善につなげよう」と前向きに取り組むことで、職場の風通しが良くなり、社員の信頼感も高まります。
たとえば、ストレスチェックの集計結果をもとに、
・「上司とのコミュニケーション」に課題がある → 管理職研修を実施
・「業務量の偏り」がストレス要因 → 業務分担の見直し
・「評価への不満」が高ストレス要因 → 人事制度の透明化に着手
このように、データを起点とした職場改善ができれば、制度は“使えるツール”になります。
<中小企業だからこそ、できる対応がある>
「うちは小さいからそんなことできない」と思われるかもしれません。でも実は、小規模事業所のほうが、経営者と社員の距離が近く、声が届きやすいという強みがあります。
大企業では制度の運用がマニュアル化しがちですが、中小企業なら、「社長が社員一人ひとりの声を受け止める」「変化にすぐ対応できる」柔軟さがあります。これは、大きなアドバンテージです。
社員のメンタルに耳を傾け、必要な支援をすぐに講じることで、結果として「この会社で働き続けたい」と思ってもらえるような職場づくりが可能になります。
ストレスチェック制度は、会社の未来を変える「きっかけ」になり得ます。この機会に、自社の働き方や人との向き合い方を見直し、制度を“自社らしく”活かす道を考えてみてはいかがでしょうか。
おわりに:義務化はチャンス──小さな企業だからこそできること
2025年の法改正によって、50人未満の事業所にもストレスチェック制度が義務化される流れが現実味を帯びてきました。これまで対象外だった中小企業にとっては、突然降って湧いたような制度に思えるかもしれません。
ですが、この変化は単なる義務の押しつけではなく、“時代に合った働き方”を考えるきっかけでもあります。
今、求職者が企業に求めるのは、単に給与や福利厚生だけではありません。安心して働ける環境、相談できる風土、そして「心の健康も大切にしてくれる会社かどうか」が、企業選びの基準になりつつあります。
中小企業は、大企業のように潤沢な人員や予算があるわけではありませんが、一人ひとりの声を聞き、柔軟に動ける強みがあります。だからこそ、小さな会社こそが「社員の心の健康を本気で守っている会社」として、求職者や既存社員に選ばれる存在になれるのです。
「うちは人数が少ないからできない」ではなく、「少ないからこそ守れる」
この言葉は、これからストレスチェック制度に向き合うすべての中小企業にとっての合言葉になるかもしれません。
誰かが不調を抱えていても見落とされてしまうような職場ではなく、少人数だからこそ「気づける」「声をかけられる」「支え合える」職場。そんな組織を目指すうえで、ストレスチェック制度は確実に力になってくれるはずです。
今回のコラムを通じて、ストレスチェック制度の基本から、背景、実務上の準備、そしてその本当の価値についてお伝えしてきました。ぜひ、この制度を「やらされる義務」ではなく、「使いこなす戦略」としてとらえ、自社の成長と社員の幸せのために活かしていただければと思います。
中小企業だからこそできる心のケア、これからの時代においては、それが企業の競争力になる時代です。
プロフィール

一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
- 第80回 50人未満でも義務化へ──中小企業が取り組むべきメンタルヘルス対策
- 第79回 「『3年以内離職率30%』を逆手に取る!中小企業の新人定着成功術」
- 第78回 「静かな退職」を防ぐ!中小企業ができる5つの具体策
- 第77回 育児介護休業法の改正が中小企業に与える影響
- 第76回 HR分野におけるAIの活用とその課題
- 第75回 変化する採用市場と学生・企業のあるべき姿勢
- 第74回 2025年の採用戦略:中小企業が勝ち抜くための5つの鍵
- 第73回 令和7年度の助成金最新情報
- 第72回 変革の時代:2025年労働基準法改正が描く新しい働き方の未来
- 第71回 法改正に対応!中小企業が知っておくべきカスタマーハラスメント対策のポイント
- 第70回 中小企業経営者のための「賃上げ支援助成金パッケージ活用術」
- 第69回 2025年春闘:中小企業の挑戦と変革の時
- 第68回 定年延長か継続雇用か ? データから見る高齢者雇用の最適解
- 第67回 2025年、退職代行サービス利用が過去最高に ~ 現代の労働環境が映し出す課題とは
- 第66回 2025年育児介護休業法改正と企業が行うべき対応
- 第65回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その3)
- 第64回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その2)
- 第63回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その1)
- 第62回 女性活躍推進法の改正がもたらす未来と企業への影響
- 第61回 大企業でも導入が進む「パーソナル雇用制度」
- 第60回 最低賃金1500円時代における給与の決め方
- 第59回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策(その3)
- 第58回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策(その2)
- 第57回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策
- 第56回 中小企業が注目すべきミドル世代の賃金上昇と転職動向~経験豊富な人材の採用でビジネス成長を加速
- 第55回 中小企業が賃金制度を考えるときに知っておきたい基本ポイント
- 第54回 2024年10月からの社会保険適用拡大、対応はお済みですか?
- 第53回 企業と競業避止契約の今後を考える
- 第52回 令和7年度 賃上げ支援助成金パッケージ:企業の成長と持続的な労働環境改善に向けて
- 第51回 解雇の金銭解決制度とその可能性 〜自民党総裁選における重要テーマ〜
- 第50回 令和7年度予算概算要求:中小企業経営者が注目すべき重要ポイントと支援策
- 第49回 給与のデジタル払いの導入とその背景
- 第48回 最低賃金改定にあたって注意すべきこと
- 第47回 最低賃金50円アップ時代に中小企業がやるべきこと
- 第46回 本当は怖い労働基準監督署の調査その4
- 第45回 本当は怖い労働基準監督署の調査(その3)
- 第44回 本当は怖い労働基準監督署の調査 その2
- 第43回 本当は怖い労働基準監督署の調査
- 第42回 初任給横並びをやめたパナソニックHD子会社の狙い
- 第41回 高齢化社会と労働力不足への対応:エイジフレンドリー補助金の活用
- 第40回 助成金を活用して人事評価制度を整備する方法
- 第39回 採用定着戦略サミット2024を終えて
- 第38回 2025年の年金制度改革が中小企業の経営に与える影響
- 第37回 クリエイティブな働き方の落とし穴:裁量労働制を徹底解説
- 第36回 昭和世代のオジサンとZ世代の若者
- 第35回 時代に合わせた雇用制度の見直し: 転勤と定年の新基準
- 第34回 合意なき配置転換は「違法」:最高裁が問い直す労働契約の本質
- 第33回 経営課題は「現在」「3 年後」「5 年後」のすべてで「人材の強化」が最多
- 第32回 退職代行サービスの増加と入社後すぐ辞める若手社員への対応
- 第31回 中小企業の新たな人材活用戦略:フリーランスの活用と法律対応
- 第30回 「ホワイト」から「プラチナ」へ:働き方改革の未来像
- 第29回 初任給高騰時代に企業が目指すべき人材投資戦略
- 第28回 心理的安全性の力:優秀な人材を定着させる中小企業の秘訣
- 第27回 賃上げラッシュに中小企業はどのように対応すべきか?
- 第26回 若者の間で「あえて非正規」が拡大。その解決策は?
- 第25回 「年収の壁」支援強化パッケージって何?
- 第24回 4月からの法改正によって労務管理はどう変わる?
- 第23回 4月からの法改正によって募集・採用はどう変わる?
- 第22回 人材の確保・定着に活用できる助成金その7
- 第21回 人材の確保・定着に活用できる助成金その6
- 第20回 人材の確保・定着に活用できる助成金その5
- 第19回 人材の確保・定着に活用できる助成金その4
- 第18回 人材の確保・定着に活用できる助成金その3
- 第17回 人材の確保・定着に活用できる助成金その2
- 第16回 人材の確保・定着に活用できる助成金その1
- 第15回 リモートワークと採用戦略の進化
- 第14回 「社員」の概念再考 - 人材シェアの新時代
- 第13回 企業と労働市場の変化の中で
- 第12回 その他大勢の「抽象企業」から脱却する方法
- 第11回 Z世代から選ばれる会社だけが生き残る
- 第10回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(後編)
- 第9回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(前編)
- 第8回 中小企業のための「集めない採用」~ まだ穴のあいたバケツに水を入れ続けますか?
- 第7回 そもそも「正社員」って何ですか? - 新たな雇用形態を模索する時代へ
- 第6回 成功事例から学ぶ!パーソナル雇用制度を導入した企業の変革と成果
- 第5回 大手企業でも「パーソナル雇用制度」導入の流れ?
- 第4回 中小企業の採用は「働きやすさ」で勝負する時代
- 第3回 プロ野球選手の年俸更改を参考にしたパーソナル雇用制度
- 第2回 パーソナル雇用制度とは? 未来を切り開く働き方の提案
- 第1回 「労働供給制約社会」がやってくる!