第64回
大戦略を描いていくことの大切さ
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

4月になり2025年度がスタート、名実共に新しい1年が始まりました。この激動の時代をどう乗り切っていくか、今回は「大戦略を描く」観点から考えていきます。
なぜ失われた10年、20年、30年から脱却できないのか
若干の波風はあったものの戦後から右肩上がりを続けた日本経済は、バブル崩壊で低迷状態に陥りました。国内総生産(GDP)は1997年をピークに下降、2000年以降は低位安定を続けています。
「そのうちに元の成長基調に戻るさ」との期待に反して10年続いたことで「失われた10年」という言葉が生まれたのだと思います。そして更に続いてしまい、危機感をもって「失われた20年」との言葉に引き継がれました。今は半分あきらめも込めの「失われた30年」という表現なのでしょうか。
こういうと「経済成長至上主義が破綻したのだ。もっと穏やかに、現状を充実させる方向性を目指せば良い」との意見が聞こえてきます。その考えが間違っているとは思いません。それができるなら、選びたい選択肢だとも考えます。
しかし日本は、その道を選べない状況にある可能性があると感じています。東京や大阪、名古屋などの大都市圏はもちろん、東北や北陸、中国、四国、九州などの地方でメインとなる都市の充実度は、世界的に見て光っていると思います。
その「居住権」価格が30年前と同じとは、グローバルな視点では考えられず「絶対に買い」となるでしょう。最近、東京23区のマンション平均価格が1億円を超えたのは、この力学が働いたからではないかと考えています。このトレンドが進むと、大半の日本人は都市部に住めなくなってしまうでしょう。
なぜこのような状況に陥ったのか?一つに「大戦略を描いていない」ことが挙げられます。大戦略とは『国家目的を遂行する最高位の観点から、平戦両時に政治的・軍事的・経済的・心理的な国力を効果的に運用する統一的・総合的・全般的な戦略』です(Wikipedia)。
軍事だけでなく政治や経済、心理なども範疇に取り込むという「範囲軸の大きさ」、そして目的達成に必要となる時間や、その効果の持続時間などを踏まえた「時間軸の大きさ」により大戦略と称されていると考えられます。バブル崩壊以降、対処療法的に戦略を描いてしまい、大戦略が欠如していたことが、低迷の理由だと考えられるのです。
国内外の両面で考えていく大戦略
では、どのように大戦略を描いていくか?大戦略を描く第1のアプローチは「この国で、国民がどのような生活を送ることになるか。享受できるメリットと、そのための責任は何か」だと考えられます。
安全な社会の中で平穏な暮らしができ、今も、また将来についても大きな不安のない生活が可能であること、そして税や社会保険などが負担可能で、持続可能であることが中心になるでしょう。国会開幕時に首相が行う「施政方針演説」は、まさにこの点を示していると思われます。
一方で大戦略は(戦略であるからこそ)外に目を向けている必要があり、このためもう一つ「自国が揺らぐことがない、世界の中でのポジションを見極め、そこを確保すること。そして他国に『我が国のポジションを侵してならない。侵させない』と知らしめること」を考えるアプローチが必要です。
この視点で透かして眺めると、アメリカや中国、ヨーロッパ諸国やインド、そしてイスラエルなどの国々がどのような大戦略を描いているのか、伺えると思います(方法論は肯定できないかもしれませんが、大戦略の姿は見えてくると思います)。
ここでのポイントは、定義する「国のポジション」は、国を維持するために必要な大きさであることです。例えばフランスは芸術や観光において飛び抜けたユニークさ、あるいは秀逸性があると言えますが、だからといってそれらだけで大戦略を描くことはできないでしょう。
フランスの大戦略は、まずはヨーロッパにおける自国のポジションを高めること、そしてヨーロッパ全体を世界の中で枢要な地位を占められる存在にすること(激しく競争し合うアメリカと中国を取り巻く「その他大勢」ではなく、ヨーロッパが重要な第3極となること)ではないかと感じられます。
それゆえフランスは芸術や観光を大切にしながらも、経済や軍事などあらゆる面でプレゼンス向上に大きな努力を払っていると感じられます。「フランスにはリーダーシップがある」と考えてもらえるよう、心理的側面も重視しているでしょう。
以上、大戦略を範囲軸、時間軸そして内外軸の3軸で考えてみました。日本が再び飛躍するためには時間軸の長い、世界において占めるべきポジションに目を向けた、そして、そのポジションを確保し確立するための「総力戦」ともいえる大戦略が必要と考えられます。
本コラムの印刷版を用意しています
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、未来を掴んでみてください。
【筆者へのご相談等はこちらから】
https://stratecutions.jp/index.php/contacts/
なお、冒頭の写真は Copilot デザイナー により作成したものです。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた。総合研究所では先進的取組から地道な取組まで様ざまな中小企業を研究した。一方で日本経済を中小企業・大企業そして金融機関、行政などによる相互作用の産物であり、それが環境として中小企業・大企業、金融機関、行政などに影響を与えるエコシステムとして捉え、失われた10年・20年・30年の突破口とする研究を続けてきた。
独立後は中小企業を支える専門家としての一面の他、日本企業をモデルにアメリカで開発されたMCS(マネジメント・コントロール・システム論)をもとにしたマネジメント研修を、大企業も含めた企業向けに実施している。またイノベーションを量産する手法として「イノベーション創造式®」及び「イノベーション創造マップ®」をベースとした研修も実施中。
現在は、中小企業によるイノベーション創造と地域金融機関のコラボレーション形成について研究・支援態勢の形成を目指している。
【落藤伸夫 著書】
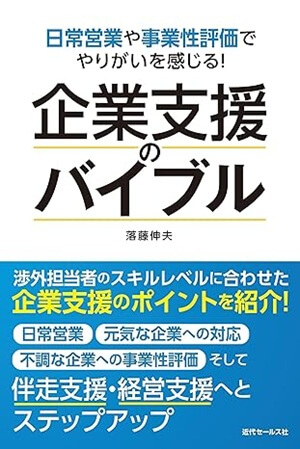
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions
- 第65回 企業が描きたい大戦略
- 第64回 大戦略を描いていくことの大切さ
- 第63回 技術か経営かではなく、技術も経営も
- 第62回 ニッサン・ホンダの破談をどう捉えるか
- 第61回 社会システム変化の軸となる主体性
- 第60回 社会システム視座の必要性
- 第59回 再構築が望まれるエコシステムの姿
- 第58回 突きつけられる課題と、その対応方法
- 第57回 「好ましいインフレ」を目指す取組
- 第56回 「好ましいインフレ」を目指す
- 第55回 地域の未掴をエコシステムとして描く
- 第54回 地域の未掴はどのようにして探すのか
- 第53回 日本の未来を拓く構想と新しい機関
- 第52回 新政権に期待すること
- 第51回 日本ならではの外貨獲得力案
- 第50回 未掴を掴む原動力を歴史的に探る
- 第49回 明治時代の未掴、今の未掴
- 第48回 オリンピック会場から想起した日本の出発点
- 第47回 都知事選ポスターから考える日本の方向性
- 第46回 都知事選ポスター問題で見えたこと
- 第45回 閉塞感を打ち破る原動力となる「気概」
- 第44回 競争力低下を憂いて発展戦略を探る
- 第43回 中小企業の生産性を向上させる方法
- 第42回 中小企業の生産性問題を考える
- 第41回 資本主義が新しくなるのか別の主義が出現するのか
- 第40回 「新しい資本主義」をどのように捉えるか
- 第39回 日本GDPを改善する2つのアプローチ
- 第38回 イノベーションで何を目指すのか?
- 第37回 日本で「失われた〇年」が続く理由
- 第36回 イノベーションは思考法で実現する?!
- 第35回 高付加価値化へのイノベーション
- 第34回 2024年スタートに高付加価値化を誓う
- 第33回 生成AIで新価値を創造できる人になる
- 第32回 生成AIで価値を付け加える
- 第31回 価値を付け足していく方法
- 第30回 新しい資本主義の付加価値付けとは?
- 第29回 新しい資本主義でのマーケティング
- 第28回 新しい資本主義での付加価値生産
- 第27回 新しい資本主義で目指すべき方向性
- 第26回 新しい資本主義に乗じ、対処する
- 第25回 「新しい資本主義」を考える
- 第24回 ChatGPTから5.0社会の「肝」を探る
- 第23回 ChatGPTから垣間見る5.0社会
- 第22回 中小企業がイノベーションのタネを生める「時」
- 第21回 中小企業がイノベーションのタネを生む
- 第20回 イノベーションにおける中小企業の新たな役割
- 第19回 中小企業もイノベーションの主体になれる
- 第18回 横階層がイノベーションを実現する訳
- 第17回 イノベーションが実現する産業構造
- 第16回 ビジネスモデルを戦略的に発展させる
- 第15回 熟したイノベーションを高度利用する
- 第14回 イノベーションを総合力で実現する
- 第13回 日本のイノベーションが低調な一因
- 第12回 ミスコンから学んだ将来の掴み方(2)
- 第11回 ミスコンから学んだ将来の掴み方(1)
- 第10回 Futureを掴む人になる!
- 第9回 新しい世界を掴む年にしましょう
- 第8回 Society5.0・中小企業5.0実践企業
- 第7回 なぜ、中小企業も5.0なのか?
- 第6回 中小企業5.0
- 第5回 第5世代を担う「ティール組織」
- 第4回 「望めば叶う」の破壊力
- 第3回 5次元社会が未掴であること
- 第2回 目の前にある5次元社会
- 第1回 Future は来るものではない、掴むものだ。取り逃がすな!














