第59回
再構築が望まれるエコシステムの姿
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

前回、原材料価格の高騰などに端を発する賃上げトレンドから、今年は生産性の向上が課題と考えました。個々企業として方向性を打ち出し対応することも大切ですが、国全体として方向性も見定めることも必要だと考えられます。
前回ではエコシステムの観点も提案しました。日本経済の復活には社会・産業エコシステムの再構築が必要だと考えられます。今回は、これから日本にどんなエコシステムを築く必要があるか、考えてみます。
2つのイノベーション創出システム
イノベーションには「科学を発展させながら今までにない原理・法則等を発見する最先端イノベーション」と、「最先端イノベーションを活用して実業化する裾野イノベーション」があると考えられます。
国が大学等に投資・推進するのは主に最先端イノベーションですが、日本が今、世界に売っていく製品・システムが少ないのは裾野イノベーション不足が原因と考えられます。これをしっかりエコシステムに取り入れていくことが必要です。
この策は特に、企業現場での業務遂行における合理化策として強力に推進する必要があります。海外と比較して中小企業の生産性が劣るのは、一つは大企業からの分配不足が挙げられますが、もう一つ、生産性を向上させるITシステム等が世に存在するのに活用されていないことが挙げられます。
「中小企業の消極的姿勢が問題だ」との指摘もありますが、中小企業が「これなら使える」と言えるほどのイノベーションが足りていないとも言えます。この側面の強化が望まれています。
第1次産業から第3次産業までの連携
一時は世界的分業により農林水産業などの第1次産業産品については外国に任せ、輸入すれば良いとの風潮があったと感じられますが、それでは社会・産業エコシステムが崩壊してしまいます。国の安全保障の観点からも望ましくありません。
農産物そのものだけでなく醤油や味噌、乳製品、酒、ひいては菓子などの加工品は世界的にユニークで評価が高まっているにもかかわらず承継者がいなかったり事業として成り立たなくなってしまうなどの現象が生じているのは大変残念なことです。
第2次産業(製造業)そして第3次産業(サービス業)と連携して相乗効果を生み出すことが望まれます。
大企業と中小企業の連携
「企業は人間と同様、生まれたての赤ちゃんから成長、大規模化して一人前となる」と考えると中小企業は必要悪ですが、役割に応じた規模に留まる必要があると考えると「必要な存在」です。
例えば新製品開発における狭小専門分野での丁寧な試行錯誤は、株価などの厳しい経済原理にさらされる大企業には行いにくい取組である場合があり、中小企業が真骨頂で活躍できる場面と考えられます。
またネジ等の部品など「産業のコメ」を進化させていけるのは中小企業に他ならず、その存在があってこそ日本のものづくりが成立してきたのです。
需要量が限られる中でも企業として存続でき地域インフラとして機能できるのも中小企業です。
これら中小企業の活躍は、大企業と連携することでより推進されると考えられます。
地域経済の活性化
各地域が活性化して住みやすくて働きやすい、そこに住むことが楽しくなることが、日本全体の活性化に繋がります。
高度成長期には公共施設など、まず大都市圏に整備されたインフラの整備から進められた感がありますが、今や地元産業の振興や観光資源の開発、育児環境の整備、祭りなどイベント開催など、経済や社会、文化など多様な側面を含む包括的な取組が志向されていると感じられます。
一方で、包括性が必要だからこそ、地方行政や住民、そこにある企業等だけでなく、隣接地域や大都市(人・機関・企業等を含む)などとの関係も大切になります。
日本全体のエコシステム形成の観点も織り込みながら、地域の特性を活かした取組が望まれます。
社会や産業の情報プラットフォーム整備
社会や産業を形成する基盤として最近では情報プラットフォームが重要な意味合いを持つようになりました。
国が進めるマイナンバー制度もその一環ですが、内容も普及度も極めて不満足な状況です。
産業のプラットフォームは大企業が個別に推進、傘下や取引先企業だけが恩恵に与れる状況と推察されます。大半の人、企業は情報プラットフォームとは無関係な状況です。
それがどのような形になるのか、どんな機能を果たしメリットを与えるのかは整備と併行して検討・実装することになると考えられますが、まずは「社会や産業の情報プラットフォームの整備が不可欠」との意識醸成が出発点になるので、出発点に立つべく取組が必要と考えられます。
本コラムの印刷版を用意しています
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、未来を掴んでみてください。
なお、冒頭の写真は Copilot デザイナー により作成したものです。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた。総合研究所では先進的取組から地道な取組まで様ざまな中小企業を研究した。一方で日本経済を中小企業・大企業そして金融機関、行政などによる相互作用の産物であり、それが環境として中小企業・大企業、金融機関、行政などに影響を与えるエコシステムとして捉え、失われた10年・20年・30年の突破口とする研究を続けてきた。
独立後は中小企業を支える専門家としての一面の他、日本企業をモデルにアメリカで開発されたMCS(マネジメント・コントロール・システム論)をもとにしたマネジメント研修を、大企業も含めた企業向けに実施している。またイノベーションを量産する手法として「イノベーション創造式®」及び「イノベーション創造マップ®」をベースとした研修も実施中。
現在は、中小企業によるイノベーション創造と地域金融機関のコラボレーション形成について研究・支援態勢の形成を目指している。
【落藤伸夫 著書】
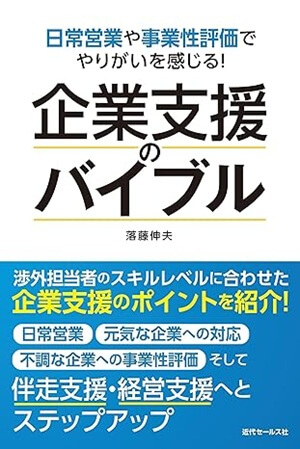
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions













