第8回
Society5.0・中小企業5.0実践企業
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫
日興エボナイト.jpg)
「Society5.0だの中小企業5.0だの言うが、そんなのは絵空事ではないのか。確かに、それを実践している企業もあるのだろう。政府のサイトなどを見ると、そのような企業が紹介されている。しかし、我々のような『普通の』企業とはほど遠い企業ばかりなのではないか?我々とは、関係ないのではないか」そのようなお話を、時々耳にします。でも、Society5.0や中小企業5.0の実践は、実はそんなに常識離れしている訳ではありません。筆者が身近にお会いする企業から、その点について考えてみましょう。
身近な実践企業「株式会社日興エボナイト製造所」
ご紹介したい企業は「株式会社日興エボナイト製造所」です。エボナイトとは、ご存知の方もおられるでしょう、天然ゴムを原料とする世界一古いと称される人工樹脂です。以前は様々な製品がエボナイトから作られていましたが、今やプラスチック等に置き換わり需要が消失した「負け犬」です。戦前は数多くあったエボナイト製造工場は姿を消し、今では世界で2社、日本では1952年に創業した当社だけが生き残っています。
需要が先細っている事業を行う企業をご支援する場合、中小企業診断士としては、中期的な展望を持つようお勧めしています。苦しい時期をどうにかやり過ごして生き残れば、少ないけれど消え去ることはない需要を満たせる数少ない供給者として価格決定権を持てる「金のなる木」に生まれ変われる可能性があるのです。
しかしエボナイトでは、そのような構図は成立しませんでした。酸やアルカリに強く、金属に匹敵するほどの強さ・耐久性があるため、エボナイトはフロート材(ガソリンタンク等の内部で液面に浮く部品。残量計測などに用いる)として根強く使われています。しかし専業メーカーが世界でたった5社となっても、「金のなる木」になれるほどの需要がなかったのです。
とすると撤退しかないのか?当社の3代目である遠藤智久社長は、そうは考えませんでした。エボナイトは、磨くと艶のある光沢が現れ、精密な成形・加工が可能な特性から、ギターのピックや万年筆の軸などの素材としても活用されています。実際、万年筆の軸としては高級素材として認知されながらも、良質な素材を安定して供給できる事業者がいないため、エボナイトを軸とする万年筆は「幻」とも言われる状況でした。
これまでの社会では成立し得ない万年筆事業
「では、自社製品として万年筆を製造すれば良い。」一見では合理的なアイデアですが、Society5.0以前の社会では難しいイノベーションでした。製造に必要なペン先が確保できても、次に問題になるのは販路です。一過性の取組なら、数十本売れれば御の字でしょう。しかしビジネスとして成立させるには一定量を長年にわたってコンスタントに販売できなければなりません。
日興エボナイト製造所自身が繁華街に店を構えて販売しても、価格が3万円以上とあっては売れる数は限られます。「卸売業者を使って全国文具店で販売したら」と言われそうですが、卸売業者も年に何本売れるか分からない商品は取り扱えません。Society5.0前の社会では、万年筆事業はビジネスにならなかったのです。
Society5.0・中小企業5.0が万年筆事業を可能にした
では日興エボナイト製造所はどうしたか?答えは「ECサイトの活用」です。「なんだ、流行に乗っただけではないか」と解釈すると本質を見誤ります。ECサイトは、リアルな店舗や既存の流通網では成立し得ないビジネスを可能にさせる原動力となりました。「今までのパラダイムでは販路が確保できないが、なんとかしたい」と望んだ遠藤社長に、「ECサイトで販路を開拓できる」と天から声があったと解釈できるでしょう。
これはまた、「中小企業の役割5.0」の具現化でもありました。先ほど述べたように、エボナイト万年筆は高級品として認知されていましたが、その製造を大企業が担っている時代には実現しませんでした。大企業が必要とする需要量がなく、必要とする収益(膨大な間接費をペイする利益幅)が取れなかったからです。日興エボナイト製造所が自社製品化し、ECサイトで販売することで、その需要が満足されることとなりました。
今までのパラダイムでは実現不能な事業プランをIT活用等による自働化で実現すること(Society5.0)と、大企業では満たせない需要を中小企業が満たすこと(中小企業の役割5.0)。両者を実現した実例は、多くの中小企業が活路を見出す見本となると考えられます。日興エボナイト製造所は今や地元にリアル店舗を構える他、海外にも販路を広げ、「エボナイト万年筆を取り扱いたい」と打診してくる世界中の企業と連携を模索しています。このような道が開ける可能性が、今、多くの中小企業の目の前に広がっています。
<本コラムの印刷版を用意しています>
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、未来を掴んでみてください。
なお、冒頭の写真は日興エボナイト製造所「笑暮屋」サイトから頂いた写真です。
日興エボナイト製造所「笑暮屋」さん、どうもありがとうございました。
<笑暮屋URL>https://eboya.net/
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた。総合研究所では先進的取組から地道な取組まで様ざまな中小企業を研究した。一方で日本経済を中小企業・大企業そして金融機関、行政などによる相互作用の産物であり、それが環境として中小企業・大企業、金融機関、行政などに影響を与えるエコシステムとして捉え、失われた10年・20年・30年の突破口とする研究を続けてきた。
独立後は中小企業を支える専門家としての一面の他、日本企業をモデルにアメリカで開発されたMCS(マネジメント・コントロール・システム論)をもとにしたマネジメント研修を、大企業も含めた企業向けに実施している。またイノベーションを量産する手法として「イノベーション創造式®」及び「イノベーション創造マップ®」をベースとした研修も実施中。
現在は、中小企業によるイノベーション創造と地域金融機関のコラボレーション形成について研究・支援態勢の形成を目指している。
【落藤伸夫 著書】
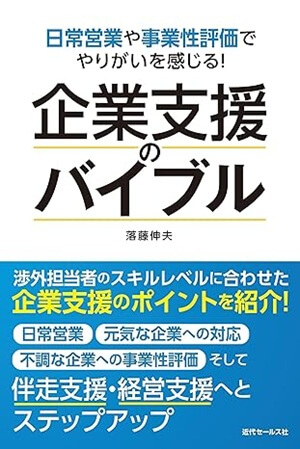
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions














