第21回
中小企業がイノベーションのタネを生む
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

日本がFutureを掴むにはイノベーションが鍵になると考えられます。イノベーションは、以前は重厚長大な研究所でしか生み出せない「技術革新」がメインだと考えられてきましたが、ITやネットワーク(クラウド)などが高度に発達した今では「新結合」つまり今までなかった組合せを実現、「その手があったか!これで私たちの生活が大きく変わる」と皆に受け入れられるという形態も活発化しています。今回は、新結合を生む「イノベーションのタネ」について考えてみます。
イノベーションに必然の「タネの多産」
イノベーションはどのように生まれてくるのか?「すごく良いアイデアが生まれた!これは技術的に革新的だし、人々の生活を変えるに違いない。これがイノベーションになるのは間違いない」との確信のもと、それに専心して取り組んでいるうちにイノベーションになった、という姿をイメージされるかもしれません。エジソンが白熱電球や電話機を開発した伝記(それも少年少女版)を読むと、そんなイメージを持たれる可能性が高いと思われます(筆者も、そんな一人です)。
しかしイノベーションの現場を見てみると、そのような例は少ないと思われます。「これはイノベーションになる」との確信があってもイノベーションに至らない例もあれば、そのような確信がなくてもイノベーションになる例もあります。これはつまりどういうことか?さまざまな試みが大量になされた結果としてイノベーションが生まれるということです。イノベーションはほとんどの場合、数多くの試みがなされた後、結果的にごく一部がイノベーションとして花開き実を結んだという状況なのです。イノベーションのタネの「多産」が必要なのです。
冒頭で、イノベーションは今まで「技術革新」がメインだったが、今は「新結合」の意味合いが高まっていると申しました。この転換期は、筆者の感覚的なものではありますが2010年頃だったと感じています。この頃までにIT技術が十分に発達、それがインターネット(クラウド)により誰でも活用できるようになったので、「我が社の今までの取組にITやネットワークを組み合わせることで、何かイノベーションが生まれないだろうか」と考えて取り組むアプローチが実用的になったのです。
欧米では、このアプローチでのイノベーションが次々と生まれています。日本でもこのような試みが活発になるか否かで、日本が活性化するか否かが決まってくると考えられます。
誰が主人公になれるか
日本が活性化するにはイノベーションがカギとなり、それは一発必中ではなく数多くのトライが必要となるなら、誰が「イノベーション多産の主人公」になれるのでしょうか?「もちろん大企業に決まっている、しっかりしてもらいたい」という声がありそうですが、その考え方が日本のイノベーションを低調にしている可能性があります。大企業にはイノベーションを試そうとする場合に、中小企業よりも高いハードルが課せられているからです。
大企業は、多数の「間接人材」ともいうべき人材を抱えています。一つは経理部や人事部などの間接部門、もう一つは(プレーヤーを兼ねない)管理職で、企業が売上・収益をあげる付加価値生産活動には直接には関わらない人材群です。これら人材は、多数の人材が付加価値生産活動に取り組み、個人や比較的小さなグループには不可能な仕事を成し遂げるために必要不可欠で、それがゆえに大企業が産業を支え、引っ張っていく役割を果たすことができました。
一方で間接人材には膨大な人件費の他、職場スペースや様々な機材等を用意する経費等がかかるので、チャレンジしようとする場合、最終的には間接人材に係る費用を含めたリターンを目指す必要があります。より大きな市場を掴もうとするので「あれも、これも」発想に陥りがちで尖った発想の邪魔になる可能性もあります。また社内人材や機械設備等を活用する方向性で考えがちで、これもコスト上昇やリスク増大要因に繋がり、チャレンジに保守的な傾向が強まるのです。
この点、中小企業は間接人材が少なくそれに係る人件費・経費等が抑えられるのでチャレンジのハードルが低いのです。まずは小さな市場で試せる(小さな市場でしか試せない)ので尖った発想ができる他、市場とのコミュニケーションも円滑にできる可能性も高まるでしょう。人材や機械設備等の資源が十分でないので他に頼ることになり、時には基幹技術等についてさえ大学等との連携が必要になる場合がありますが、それは裏返せば、1社あたりのコスト低減やリスク分散、可能性の拡大に繋がっていると言えます。(他方、協力相手が思ったように動いてくれないという別のリスクは生じますが)。
こう考えると、欧米においてイノベーションの多くが中小企業によって生まれている(技術等が確立、市場性等が確認できた後に大企業に買収される)理由が分かると思います。日本でイノベーションを活発化させたいなら、中小企業の活躍を推進する必要があると考えられます。
本コラムの印刷版を用意しています
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、未来を掴んでみてください。
なお、冒頭の写真は写真ACから bBear さんご提供によるものです。bBear さん、どうもありがとうございました。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた。総合研究所では先進的取組から地道な取組まで様ざまな中小企業を研究した。一方で日本経済を中小企業・大企業そして金融機関、行政などによる相互作用の産物であり、それが環境として中小企業・大企業、金融機関、行政などに影響を与えるエコシステムとして捉え、失われた10年・20年・30年の突破口とする研究を続けてきた。
独立後は中小企業を支える専門家としての一面の他、日本企業をモデルにアメリカで開発されたMCS(マネジメント・コントロール・システム論)をもとにしたマネジメント研修を、大企業も含めた企業向けに実施している。またイノベーションを量産する手法として「イノベーション創造式®」及び「イノベーション創造マップ®」をベースとした研修も実施中。
現在は、中小企業によるイノベーション創造と地域金融機関のコラボレーション形成について研究・支援態勢の形成を目指している。
【落藤伸夫 著書】
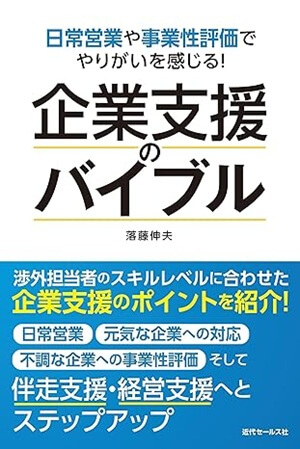
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions
- 第65回 企業が描きたい大戦略
- 第64回 大戦略を描いていくことの大切さ
- 第63回 技術か経営かではなく、技術も経営も
- 第62回 ニッサン・ホンダの破談をどう捉えるか
- 第61回 社会システム変化の軸となる主体性
- 第60回 社会システム視座の必要性
- 第59回 再構築が望まれるエコシステムの姿
- 第58回 突きつけられる課題と、その対応方法
- 第57回 「好ましいインフレ」を目指す取組
- 第56回 「好ましいインフレ」を目指す
- 第55回 地域の未掴をエコシステムとして描く
- 第54回 地域の未掴はどのようにして探すのか
- 第53回 日本の未来を拓く構想と新しい機関
- 第52回 新政権に期待すること
- 第51回 日本ならではの外貨獲得力案
- 第50回 未掴を掴む原動力を歴史的に探る
- 第49回 明治時代の未掴、今の未掴
- 第48回 オリンピック会場から想起した日本の出発点
- 第47回 都知事選ポスターから考える日本の方向性
- 第46回 都知事選ポスター問題で見えたこと
- 第45回 閉塞感を打ち破る原動力となる「気概」
- 第44回 競争力低下を憂いて発展戦略を探る
- 第43回 中小企業の生産性を向上させる方法
- 第42回 中小企業の生産性問題を考える
- 第41回 資本主義が新しくなるのか別の主義が出現するのか
- 第40回 「新しい資本主義」をどのように捉えるか
- 第39回 日本GDPを改善する2つのアプローチ
- 第38回 イノベーションで何を目指すのか?
- 第37回 日本で「失われた〇年」が続く理由
- 第36回 イノベーションは思考法で実現する?!
- 第35回 高付加価値化へのイノベーション
- 第34回 2024年スタートに高付加価値化を誓う
- 第33回 生成AIで新価値を創造できる人になる
- 第32回 生成AIで価値を付け加える
- 第31回 価値を付け足していく方法
- 第30回 新しい資本主義の付加価値付けとは?
- 第29回 新しい資本主義でのマーケティング
- 第28回 新しい資本主義での付加価値生産
- 第27回 新しい資本主義で目指すべき方向性
- 第26回 新しい資本主義に乗じ、対処する
- 第25回 「新しい資本主義」を考える
- 第24回 ChatGPTから5.0社会の「肝」を探る
- 第23回 ChatGPTから垣間見る5.0社会
- 第22回 中小企業がイノベーションのタネを生める「時」
- 第21回 中小企業がイノベーションのタネを生む
- 第20回 イノベーションにおける中小企業の新たな役割
- 第19回 中小企業もイノベーションの主体になれる
- 第18回 横階層がイノベーションを実現する訳
- 第17回 イノベーションが実現する産業構造
- 第16回 ビジネスモデルを戦略的に発展させる
- 第15回 熟したイノベーションを高度利用する
- 第14回 イノベーションを総合力で実現する
- 第13回 日本のイノベーションが低調な一因
- 第12回 ミスコンから学んだ将来の掴み方(2)
- 第11回 ミスコンから学んだ将来の掴み方(1)
- 第10回 Futureを掴む人になる!
- 第9回 新しい世界を掴む年にしましょう
- 第8回 Society5.0・中小企業5.0実践企業
- 第7回 なぜ、中小企業も5.0なのか?
- 第6回 中小企業5.0
- 第5回 第5世代を担う「ティール組織」
- 第4回 「望めば叶う」の破壊力
- 第3回 5次元社会が未掴であること
- 第2回 目の前にある5次元社会
- 第1回 Future は来るものではない、掴むものだ。取り逃がすな!














