第37回
日本で「失われた〇年」が続く理由
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

世界中が成長し、中には飛躍といえる発展を遂げている中で日本はなぜ「失われた〇年」記録を更新中なのか?その理由の一つに「思考法」があると考えられます。今回はこの点について考えていきます。
「失われた〇年」の解決策は適切か?
日本はなぜ「失われた〇年」記録を更新中なのか?「それは答えが出ている。生産性が低いからだ」との声が聞こえてきそうですね。指摘として間違いありません。今、売上・利益不足で困っている企業の生産性を測ると、労働生産性にしろ設備生産性にしろ、非常に低いレベルになっています。
現場を見るとその現実を目の当たりにします。例えば店舗で働く売り子は本来の仕事である接客は行わず、伝票を丁寧に整理し直したりしています。工場の作業員は本来の仕事である生産機械を操作しておらず、在庫棚の整頓などを行っています。
「だから労働生産性の向上を目指すべきだ。日本人の働き方は非効率すぎる。」この指摘も、間違いではないでしょう。しかし売上・利益の低迷に悩んでいる企業に対してコンサルタントは「生産性向上を目指すように」とアドバイスするとは限りません。そのアプローチでは企業を助けられない可能性があるからです。特にコロナ禍のような経済インシデントに見舞われて売上・利益を減らした企業がこのアプローチで再起を図ろうとすると、逆効果になる場合があります。
先ほど挙げた、伝票整理をする売り子に「伝票の整理ばかりしているから生産性が低くなるのだ。接客をしなさい」と言っても意味がありません。店にお客が来ないのであれば接客のしようがないのです。在庫棚の整頓をしている作業員に「機械を操作しなさい」と命じ、彼らがその通りにすればどうなるでしょうか?売り先がない製品や半製品が大量生産されるだけです。
では、どうすれば良いのか?まずは売上を増やす方法を考えなければなりません。商店であれば来店者を増やす方法、工場であれば売れる製品を考える、あるいは我が社に注文を出してくれる取引先を探すのです。通常、この取組は「生産性向上に向けた方策」とはみなされませんが、これが成就すれば生産性は向上します。目指す結果を得るには、考え方を変える必要があるのです。
生産性論議に振り回される日本
一方で日本は生産性を向上させるアプローチに心血を注いでいると感じられます。「日本の問題は生産性の低さにあり、その根本原因は中小企業の多さにある。だから淘汰に任せるのはもちろん、強制的に統廃合を促して中小企業の数を減らせば生産性が高められる、日本は豊かになる」との指摘があり、それを真に受けている政策が執られていると感じられます。また「生産性の高い他国を見習えば生産性が向上する。週休2日では足りず3日にすべきだ。そうすれば余裕ができて良いアイデアが生まれ、生産性が高まる」などと指摘する書物が評判になったりしています。
これらの指摘が間違いだと言っている訳ではありません。正しい指摘です。但し、これらを実践しても日本の「失われた〇年」記録の更新を止めることはできないでしょう。風邪の症状がある人に湿布薬を与えるようなもので、問題・課題に適した処方箋ではないからです。この指摘は「湿布薬が劣悪である」と貶めている訳ではありません。最高の湿布薬をもってしても風邪は治せないと言っているだけです。
海外で売れるイノベーションを目指す
日本の「失われた〇年」記録更新を止めて飛躍を目指すなら「どうしたら日本の製品やサービスが売れるようになるのか」を考えることがポイントになります。「それは難しいだろう。国内市場は少子化で収縮するばかりだから。」ならば海外で売ることを考えれば良いのです。
製品やサービスを国内で販売すると、お金が回転することでGDPが増加しますが(お金の総量としては増えない)、海外で販売すればGDPが増加すると共にお金の総量も増えます。消費に回せる原資が増えるので波及的に国内での販売も増えるでしょう。一石二鳥だと考えられます。
「そんなことは分かっている。みんな輸出を目指して頑張っているが売れないのだ。」その理由は何でしょう?競合製品と比較して突き詰めると「買い手がワクワクするイノベーションが足りない」に行き着くと思われます。
ではなぜ日本にイノベーションが不足しているのか?そもそも追求されていないからではないかと感じられます。「生産性の向上」に躍起になって、イノベーションには注力されていないのです。明るい将来を手にしたいなら、まず最初の考え方を改めて世界に売れるイノベーションを目指す必要があると考えられます。
本コラムの印刷版を用意しています
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、未来を掴んでみてください。
冒頭の写真は写真ACから 自然体 さんご提供によるものです。自然体 さん、どうもありがとうございました。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた。総合研究所では先進的取組から地道な取組まで様ざまな中小企業を研究した。一方で日本経済を中小企業・大企業そして金融機関、行政などによる相互作用の産物であり、それが環境として中小企業・大企業、金融機関、行政などに影響を与えるエコシステムとして捉え、失われた10年・20年・30年の突破口とする研究を続けてきた。
独立後は中小企業を支える専門家としての一面の他、日本企業をモデルにアメリカで開発されたMCS(マネジメント・コントロール・システム論)をもとにしたマネジメント研修を、大企業も含めた企業向けに実施している。またイノベーションを量産する手法として「イノベーション創造式®」及び「イノベーション創造マップ®」をベースとした研修も実施中。
現在は、中小企業によるイノベーション創造と地域金融機関のコラボレーション形成について研究・支援態勢の形成を目指している。
【落藤伸夫 著書】
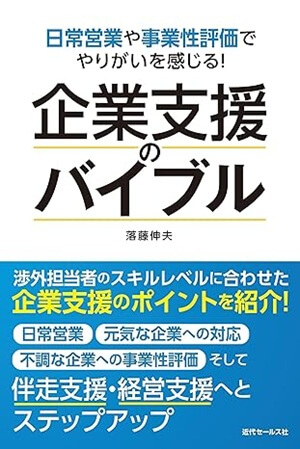
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions
- 第65回 企業が描きたい大戦略
- 第64回 大戦略を描いていくことの大切さ
- 第63回 技術か経営かではなく、技術も経営も
- 第62回 ニッサン・ホンダの破談をどう捉えるか
- 第61回 社会システム変化の軸となる主体性
- 第60回 社会システム視座の必要性
- 第59回 再構築が望まれるエコシステムの姿
- 第58回 突きつけられる課題と、その対応方法
- 第57回 「好ましいインフレ」を目指す取組
- 第56回 「好ましいインフレ」を目指す
- 第55回 地域の未掴をエコシステムとして描く
- 第54回 地域の未掴はどのようにして探すのか
- 第53回 日本の未来を拓く構想と新しい機関
- 第52回 新政権に期待すること
- 第51回 日本ならではの外貨獲得力案
- 第50回 未掴を掴む原動力を歴史的に探る
- 第49回 明治時代の未掴、今の未掴
- 第48回 オリンピック会場から想起した日本の出発点
- 第47回 都知事選ポスターから考える日本の方向性
- 第46回 都知事選ポスター問題で見えたこと
- 第45回 閉塞感を打ち破る原動力となる「気概」
- 第44回 競争力低下を憂いて発展戦略を探る
- 第43回 中小企業の生産性を向上させる方法
- 第42回 中小企業の生産性問題を考える
- 第41回 資本主義が新しくなるのか別の主義が出現するのか
- 第40回 「新しい資本主義」をどのように捉えるか
- 第39回 日本GDPを改善する2つのアプローチ
- 第38回 イノベーションで何を目指すのか?
- 第37回 日本で「失われた〇年」が続く理由
- 第36回 イノベーションは思考法で実現する?!
- 第35回 高付加価値化へのイノベーション
- 第34回 2024年スタートに高付加価値化を誓う
- 第33回 生成AIで新価値を創造できる人になる
- 第32回 生成AIで価値を付け加える
- 第31回 価値を付け足していく方法
- 第30回 新しい資本主義の付加価値付けとは?
- 第29回 新しい資本主義でのマーケティング
- 第28回 新しい資本主義での付加価値生産
- 第27回 新しい資本主義で目指すべき方向性
- 第26回 新しい資本主義に乗じ、対処する
- 第25回 「新しい資本主義」を考える
- 第24回 ChatGPTから5.0社会の「肝」を探る
- 第23回 ChatGPTから垣間見る5.0社会
- 第22回 中小企業がイノベーションのタネを生める「時」
- 第21回 中小企業がイノベーションのタネを生む
- 第20回 イノベーションにおける中小企業の新たな役割
- 第19回 中小企業もイノベーションの主体になれる
- 第18回 横階層がイノベーションを実現する訳
- 第17回 イノベーションが実現する産業構造
- 第16回 ビジネスモデルを戦略的に発展させる
- 第15回 熟したイノベーションを高度利用する
- 第14回 イノベーションを総合力で実現する
- 第13回 日本のイノベーションが低調な一因
- 第12回 ミスコンから学んだ将来の掴み方(2)
- 第11回 ミスコンから学んだ将来の掴み方(1)
- 第10回 Futureを掴む人になる!
- 第9回 新しい世界を掴む年にしましょう
- 第8回 Society5.0・中小企業5.0実践企業
- 第7回 なぜ、中小企業も5.0なのか?
- 第6回 中小企業5.0
- 第5回 第5世代を担う「ティール組織」
- 第4回 「望めば叶う」の破壊力
- 第3回 5次元社会が未掴であること
- 第2回 目の前にある5次元社会
- 第1回 Future は来るものではない、掴むものだ。取り逃がすな!














