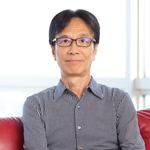第79回
「『3年以内離職率30%』を逆手に取る!中小企業の新人定着成功術」
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原 京二
はじめに:2025年の春、変化の兆しと向き合うとき
2025年の春、新たな一歩を踏み出した新入社員たちが全国の職場に加わりました。毎年この時期は、フレッシュな空気とともに、企業にも“希望”と“責任”の両方が訪れます。
今年の新入社員たちは、大学時代にコロナ禍を経験し、オンライン授業やリモート面接が当たり前だった世代です。社会とのつながりやリアルな職場体験が限られた中で育った彼らは、「安心感」「成長実感」「柔軟な働き方」といったキーワードに敏感で、自分らしさや納得感を重視する傾向がより強まっています。
一方で、2025年の新卒採用では“売り手市場”が続き、中小企業にとっては人材確保そのものが難しくなっています。ようやく迎え入れた貴重な若手人材を、どうすれば「辞めずに育てられるか」という問いは、企業規模に関係なく、今やすべての経営者・人事担当者にとって切実なテーマになっています。
<離職率30%という現実>
厚生労働省のデータによれば、大卒新入社員の約3人に1人が3年以内に離職しているという事実があります。これが俗に言う「3年以内離職率30%」の正体です。
しかしこの数字、果たして一律に「悪」なのでしょうか?
例えば、業界別に見ると違いが際立ちます。
宿泊・飲食サービス業:56.6%
教育・学習支援業:48.9%
小売業:39.5%
製造業:27.0%
情報通信業(IT):22.8%
つまり、「30%」という数字は一つの平均に過ぎず、業界や企業の取り組みによって結果は大きく変わるということ。そして何より重要なのは、この「30%」を脅威として恐れるのではなく、変革のヒントとして活用する視点です。
本コラムでは、若手が離れていく原因を「構造的に」捉え直し、そのうえで中小企業だからこそ実践できる“逆転の定着戦略“を具体的にご紹介していきます。
1.離職要因の構造化分析〜なぜ、若手は会社を去るのか?〜
若手社員の離職には、単一の理由ではなく、いくつもの要因が重なっています。ここでは、特に多く見られる「3大要因」と、その背景にある“ギャップの蓄積”について整理してみましょう。
【要因1】採用時の期待と現実の業務のギャップ
採用段階で抱いた理想やイメージと、実際の業務との間にズレが生じると、早期離職の引き金になります。
「もっとクリエイティブな仕事ができると思っていた」「人と接する仕事と聞いていたが、実際はデスクワークばかりだった」──そうした声はよく耳にします。
このギャップは、「騙された」と感じるほど大きな心理的インパクトを与えるため、最初の数ヶ月が“見極め期間”になりやすいのです。
【要因2】企業文化への適応不全(心理的安全性の不足)
「相談しにくい」「雑談の場がない」「上司が話しかけにくい」など、心理的安全性の低さも大きな要因の一つです。
特にZ世代の若手社員は、「自分の考えや不安を率直に話せる環境」を重視します。上下関係が強く、古い慣習が残る職場ほど、早期に「この職場は合わない」と判断される傾向があります。
【要因3】成長機会の不透明性
「このまま働き続けたら、どんなスキルが身につくのか?」「キャリアはどう開けていくのか?」という疑問に答えられない職場は、若手から見ると“将来が見えない”場所になります。
・キャリアパスが明示されていない
・スキルアップのための研修や指導がない
・評価基準が不明確
こうした不透明感が蓄積し、やがて「もっと成長できる環境へ行きたい」という離職動機に転化していきます。
<働き方の硬直性とワークライフバランスの問題も拍車をかける>
・リモートワークやフレックスタイムといった柔軟な働き方への対応が遅れている
・残業が多く、プライベートとの両立が難しい
・相談しにくい、孤立感がある職場環境
こうした点も、離職率の高さに影響しています。
<「辞めた理由」ではなく「辞める流れ」を見極める>
離職は“ある一言”や“ある出来事”で起きるのではなく、小さなギャップや不満が積み重なった末の決断です。だからこそ、「なぜ辞めたか」ではなく「なぜそうなる流れだったのか」に目を向ける必要があります。
2.中小企業ならではの逆転戦略〜「柔軟性」と「個別最適化」で離職を防ぐ〜
若手が辞める理由は明らかです。しかしそれを防ぐための打ち手は、大企業と中小企業で異なります。人員も制度も潤沢ではない中小企業が勝負するには、“小回りの利く柔軟性”と“一人ひとりに目を配る力”が最大の武器になります。
ここでは、ギャップの解消・成長の可視化・働き方の柔軟化という3つの視点から、実践的な逆転戦略を紹介します。
<戦略1:ギャップ解消の「3段階オンボーディング」>
入社前後の“イメージのズレ”を防ぐために、中小企業こそ丁寧なオンボーディングが重要です。
・入社前の「リアル体験」
1日職場体験を取り入れることで、実際の仕事や雰囲気を事前に把握してもらい、「思っていたのと違う」を防ぎます。
・初日〜3ヶ月の密着サポート
メンター制度を導入するだけでなく、形式的な面談ではなく週1回の雑談ミーティングを取り入れると、若手の本音を引き出せます。業務のサポートよりも“孤立させない”ことを重視しましょう。
・6ヶ月後の振り返り面談
節目である半年後には、「最初の期待と今の現実」を再確認し、期待値の調整と目標の再設定を行います。これにより「ここで成長できそうだ」という納得感を育てます。
<戦略2:成長可視化の「マイクロキャリア設計」>
「今の自分がどう成長しているか」を“見える化”することで、働く意味を実感しやすくなります。
・ 3ヶ月単位の目標設定
「Excel関数を覚える」「顧客対応マニュアルを作成する」など、小さな成功体験の積み上げを評価対象に。評価基準も分かりやすく、上司とのすり合わせがしやすくなります。
・デジタルバッジ制度の導入
スキルの習得ごとに「見える勲章」としてバッジを発行。さらに、クラウド会計ソフトが使えるようになったら1万円奨励金、SNS運用で成果が出たら報奨ポイント、といったインセンティブ設計をすることで、成長意欲が高まります。
<戦略3:働き方の「ハイブリッド最適化」>
柔軟な働き方は、もはや大企業だけの特権ではありません。
・中小企業版リモートワーク
たとえば「週1日在宅勤務+出社コアタイムなし」といった実験的導入は、業務を回しながら効果を検証できます。
・時間対効果を可視化
タスク管理アプリ(例:TrelloやNotion)で業務を“見える化”すれば、「仕事をしている」ではなく「成果を出している」が可視化され、評価の納得感が増します。
これらの戦略は、大規模な制度改革ではありません。しかし、一つひとつの施策が「自分のために考えてくれている」と若手に伝わることで、離職率を確実に下げる力になります。
3.実践事例から学ぶ成功パターン〜制度よりも“工夫”が人をつなぎとめる〜
新人の定着に成功している中小企業には、決して大掛かりな制度や多額の予算があるわけではありません。共通しているのは、「現場の工夫」と「若手目線の配慮」です。ここでは、実際の企業事例を3つご紹介します。
まずご紹介するのは、従業員20名の製造業の企業です。ここでは、若手社員が週替わりでメンターとランチを共にする「ランチローテーション制度」を取り入れています。仕事の相談ではなく、雑談を通じて日常的にメンターとの距離を縮めることで、若手社員が悩みをため込まずにすむ環境をつくりました。その結果、2年連続で若手の離職者ゼロという成果を出しています。制度自体はシンプルですが、孤立を防ぐ仕組みとして非常に有効です。
次に、複数店舗を展開する飲食チェーンの事例です。この企業では、新人教育の属人化を防ぐため、接客スキルを動画マニュアル化しました。新人はタブレットで接客の流れや注意点を繰り返し学べるため、現場に出る前に安心感を得られます。その結果、新人教育にかかる時間が従来の半分に短縮され、教育負担の重かった店長からも「助かった」という声が上がっています。
最後は、ITベンチャー企業の取り組みです。この会社では、「スキルを習得すればどれだけ給与が上がるか」を具体的に提示する制度を導入しました。たとえば、クラウド会計ソフトを使えるようになれば月給が1万円アップ、顧客向けの企画書作成ができるようになればさらに昇給、というように、スキルアップと報酬の関係が“見える化”されているのです。社員は「自分がこの会社にいる意味」が明確になり、3年定着率は85%にまで向上しています。
これらの事例に共通しているのは、「本人の成長実感を育てる」「気軽に相談できる関係性をつくる」「キャリアの見通しを明確にする」という工夫です。制度の立派さではなく、“どう伝わるか”“どう実感されるか”が、離職率を左右しているのです。
4.失敗回避のチェックリスト〜「やってはいけないこと」と「やるべきこと」を見極める〜
ここまで紹介してきた成功事例の裏には、数多くの試行錯誤と失敗も存在します。中小企業が新人定着を目指すうえで陥りがちな落とし穴を事前に回避するために、ここでは「やってはいけない3つの過ち」と「最低限確認すべきチェックポイント」を整理しておきましょう。
<やってはいけない「3つの過ち」>
(1) マニュアル教育のみに依存する
教育担当が不在だったり、OJTにバラつきがある現場では、「とりあえずマニュアルだけ渡しておく」という対応になりがちです。しかし、マニュアルだけでは新人は動けません。リアルな現場では、書かれていない“文脈”が重要です。マニュアルは“補助資料”であって、教育の主役にはなり得ません。
(2) 評価基準を年功序列のまま維持する
若手社員にとって、評価の納得感はモチベーションの源泉です。しかし、「何年働いたか」「年齢が上かどうか」が評価の軸となっている職場では、自分の努力が正当に認められていないと感じ、離職の要因になります。スキルや成果が正当に反映される仕組みが必要です。
(3)フィードバックを年1回のみに限定する
年に1回の人事評価面談だけでは、若手の不安や疑問にリアルタイムで応えることができません。特に入社半年〜1年の間は、変化の激しい時期です。月1回、または四半期ごとのフィードバック面談を設け、こまめに方向性を確認することが定着支援の鍵となります。
<必須確認項目チェックリスト>
・メンター制度を導入しているか?
→ 単なる「制度」ではなく、「雑談できる関係性」を築く工夫があるか。
・メンター自身に雑談力があるか?
→ メンター向けに“雑談力”や“聞く力”を育てる研修を実施しているか。
・デジタルツールの導入前に、社内ITリテラシーを把握しているか?
→ 新しいツールを導入する前に、現場がどの程度デジタルに対応できるか診断しているか。
・新人との1on1ミーティングの頻度が適切か?
→ 最低でも月1回、理想は週1回の簡易的な接点があるか。
・成長や貢献が可視化されているか?
→ 小さなスキルアップでも、明確に評価されている仕組みがあるか。
新人が辞めてしまったとき、「本人の根性が足りない」と片づけてしまうのは簡単です。しかし、本当に見るべきなのは、職場側が変化に対応できていたかという視点です。
おわりに:離職率を「組織強化の指標」へ
3年以内離職率30%──この数字は、確かに一見するとネガティブな響きを持ちます。
しかしこの数字は、裏を返せば「自社に何が足りなかったのか」「何を変えればもっと人が育つのか」というヒントをくれる、組織強化の指標でもあるのです。
<「離職」をPDCAで回す視点>
離職が起きたとき、そこから目を背けるのではなく、原因を分析して改善につなげるマネジメントサイクル(PDCA)を回すことが重要です。
Plan(計画):オンボーディングやキャリア設計、働き方の方針を立てる
Do(実行):実際に施策を導入し、現場で運用する
Check(評価):離職者の傾向や定着率を定期的に分析する
Action(改善):分析結果をもとに制度や支援内容を修正する
このPDCAを毎年着実に回していくことで、「なぜ辞めたか?」ではなく、「次はどうすれば残れるか?」という前向きな経営姿勢が生まれます。
<中小企業が持つ最大の武器>
人材定着の戦いにおいて、中小企業の最大の武器は“変化への対応力”と“個人への注目度”です。大企業のように制度や評価が画一的ではないからこそ、社員一人ひとりの状況に合わせて対応を柔軟に変えられる。この個別最適化の力が、これからの時代の人材マネジメントにおいてますます重要になります。
離職率は、恐れるものではありません。向き合い、見直し、育て直すための貴重なシグナルです。
「3年以内離職率30%」という現実を、“仕方がない”で済ませず、“チャンス”に変えていく。
そんな前向きな一歩を踏み出す企業が増えれば、中小企業はもっと働きやすく、成長しやすい場所になっていくはずです。
プロフィール

一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
- 第79回 「『3年以内離職率30%』を逆手に取る!中小企業の新人定着成功術」
- 第78回 「静かな退職」を防ぐ!中小企業ができる5つの具体策
- 第77回 育児介護休業法の改正が中小企業に与える影響
- 第76回 HR分野におけるAIの活用とその課題
- 第75回 変化する採用市場と学生・企業のあるべき姿勢
- 第74回 2025年の採用戦略:中小企業が勝ち抜くための5つの鍵
- 第73回 令和7年度の助成金最新情報
- 第72回 変革の時代:2025年労働基準法改正が描く新しい働き方の未来
- 第71回 法改正に対応!中小企業が知っておくべきカスタマーハラスメント対策のポイント
- 第70回 中小企業経営者のための「賃上げ支援助成金パッケージ活用術」
- 第69回 2025年春闘:中小企業の挑戦と変革の時
- 第68回 定年延長か継続雇用か ? データから見る高齢者雇用の最適解
- 第67回 2025年、退職代行サービス利用が過去最高に ~ 現代の労働環境が映し出す課題とは
- 第66回 2025年育児介護休業法改正と企業が行うべき対応
- 第65回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その3)
- 第64回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その2)
- 第63回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その1)
- 第62回 女性活躍推進法の改正がもたらす未来と企業への影響
- 第61回 大企業でも導入が進む「パーソナル雇用制度」
- 第60回 最低賃金1500円時代における給与の決め方
- 第59回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策(その3)
- 第58回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策(その2)
- 第57回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策
- 第56回 中小企業が注目すべきミドル世代の賃金上昇と転職動向~経験豊富な人材の採用でビジネス成長を加速
- 第55回 中小企業が賃金制度を考えるときに知っておきたい基本ポイント
- 第54回 2024年10月からの社会保険適用拡大、対応はお済みですか?
- 第53回 企業と競業避止契約の今後を考える
- 第52回 令和7年度 賃上げ支援助成金パッケージ:企業の成長と持続的な労働環境改善に向けて
- 第51回 解雇の金銭解決制度とその可能性 〜自民党総裁選における重要テーマ〜
- 第50回 令和7年度予算概算要求:中小企業経営者が注目すべき重要ポイントと支援策
- 第49回 給与のデジタル払いの導入とその背景
- 第48回 最低賃金改定にあたって注意すべきこと
- 第47回 最低賃金50円アップ時代に中小企業がやるべきこと
- 第46回 本当は怖い労働基準監督署の調査その4
- 第45回 本当は怖い労働基準監督署の調査(その3)
- 第44回 本当は怖い労働基準監督署の調査 その2
- 第43回 本当は怖い労働基準監督署の調査
- 第42回 初任給横並びをやめたパナソニックHD子会社の狙い
- 第41回 高齢化社会と労働力不足への対応:エイジフレンドリー補助金の活用
- 第40回 助成金を活用して人事評価制度を整備する方法
- 第39回 採用定着戦略サミット2024を終えて
- 第38回 2025年の年金制度改革が中小企業の経営に与える影響
- 第37回 クリエイティブな働き方の落とし穴:裁量労働制を徹底解説
- 第36回 昭和世代のオジサンとZ世代の若者
- 第35回 時代に合わせた雇用制度の見直し: 転勤と定年の新基準
- 第34回 合意なき配置転換は「違法」:最高裁が問い直す労働契約の本質
- 第33回 経営課題は「現在」「3 年後」「5 年後」のすべてで「人材の強化」が最多
- 第32回 退職代行サービスの増加と入社後すぐ辞める若手社員への対応
- 第31回 中小企業の新たな人材活用戦略:フリーランスの活用と法律対応
- 第30回 「ホワイト」から「プラチナ」へ:働き方改革の未来像
- 第29回 初任給高騰時代に企業が目指すべき人材投資戦略
- 第28回 心理的安全性の力:優秀な人材を定着させる中小企業の秘訣
- 第27回 賃上げラッシュに中小企業はどのように対応すべきか?
- 第26回 若者の間で「あえて非正規」が拡大。その解決策は?
- 第25回 「年収の壁」支援強化パッケージって何?
- 第24回 4月からの法改正によって労務管理はどう変わる?
- 第23回 4月からの法改正によって募集・採用はどう変わる?
- 第22回 人材の確保・定着に活用できる助成金その7
- 第21回 人材の確保・定着に活用できる助成金その6
- 第20回 人材の確保・定着に活用できる助成金その5
- 第19回 人材の確保・定着に活用できる助成金その4
- 第18回 人材の確保・定着に活用できる助成金その3
- 第17回 人材の確保・定着に活用できる助成金その2
- 第16回 人材の確保・定着に活用できる助成金その1
- 第15回 リモートワークと採用戦略の進化
- 第14回 「社員」の概念再考 - 人材シェアの新時代
- 第13回 企業と労働市場の変化の中で
- 第12回 その他大勢の「抽象企業」から脱却する方法
- 第11回 Z世代から選ばれる会社だけが生き残る
- 第10回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(後編)
- 第9回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(前編)
- 第8回 中小企業のための「集めない採用」~ まだ穴のあいたバケツに水を入れ続けますか?
- 第7回 そもそも「正社員」って何ですか? - 新たな雇用形態を模索する時代へ
- 第6回 成功事例から学ぶ!パーソナル雇用制度を導入した企業の変革と成果
- 第5回 大手企業でも「パーソナル雇用制度」導入の流れ?
- 第4回 中小企業の採用は「働きやすさ」で勝負する時代
- 第3回 プロ野球選手の年俸更改を参考にしたパーソナル雇用制度
- 第2回 パーソナル雇用制度とは? 未来を切り開く働き方の提案
- 第1回 「労働供給制約社会」がやってくる!