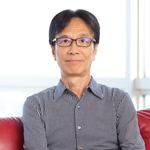第64回
「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その2)
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原 京二
3. 労働時間の壁を管理する重要性
(1) 労働時間管理の新たな役割
「労働時間の壁」が社会保険適用の新しい基準となる中で、企業にとって労働時間の管理がますます重要になっています。具体的には、以下の理由から、適切な管理が不可欠です。
・社会保険適用の正確な判断
週20時間以上の労働が基準となるため、労働者の労働時間を正確に把握することが、適用の可否を判断する基本となります。
・労使トラブルの防止
労働時間の記録が不十分であったり、契約内容と実働時間が一致しない場合、社会保険の適用に関するトラブルが発生するリスクがあります。
・コンプライアンスの確保
法令遵守の観点からも、正確な勤怠記録と労働時間管理は企業の信頼性を高めるために必要不可欠です。
(2) 労働時間管理の具体的な手法
労働時間の管理を徹底するためには、以下の手法が有効です。
<労働契約の徹底管理>
・入社時に労働契約書における所定労働時間を明確に設定し、それを厳格に記録します。
・契約内容が変更された場合は速やかに更新し、労働者に再確認を行うことで、透明性を保ちます。
<勤怠管理システムの導入>
・労働時間を正確に記録するための勤怠管理システムを導入します。
・リアルタイムで労働時間を把握できるツールは、管理の効率化と正確性の向上に寄与します。
<定期的なデータの分析>
・労働時間データを定期的に分析し、社会保険適用の基準を超える労働者を把握します。
・この分析により、契約内容や運用状況の見直しが必要な場合も即座に対応できます。
<従業員とのコミュニケーション>
・労働時間や契約内容について、従業員と定期的に話し合いを行い、相互理解を深めます。
・特に、社会保険適用のメリットを説明し、従業員が正しい情報をもとに選択できる環境を整えます。
(3) 労働時間管理の課題と対応策
適切な管理を行う上で、いくつかの課題もあります。
<中小企業のリソース不足>
・勤怠管理システムの導入や労働契約の更新作業に対する負担が大きい。
・対応策: 外部の専門家やサービスを活用して、労務管理の効率化を図る。
<管理ミスによるトラブル>
・記録漏れやデータ誤入力がトラブルの原因となる場合がある。
・対応策: 定期的な内部監査を行い、記録の正確性を確保する。
(4) 管理の徹底がもたらす効果
労働時間の壁を正確に管理することは、企業にとって以下のようなプラスの効果をもたらします。
・法令遵守の促進
コンプライアンスを確保し、企業の社会的信頼を向上させます。
・労働環境の改善
正確な管理により、労働者に適切な社会保険を提供できる環境を整え、従業員満足度を向上させます。
・経営リスクの軽減
労使トラブルのリスクを減らし、安定した経営基盤を確立します。
4. 社会保険適用拡大の未来
(1) 社会保険適用拡大の背景
社会保険適用拡大は、働き方の多様化や少子高齢化の進展を背景に進められています。特に、短時間労働者の増加や非正規雇用の広がりに対応するため、従来の年収や企業規模に依存した基準から、より公平で現実的な基準への転換が求められています。
政府は、以下のような目的を掲げて適用拡大を推進しています。
・公平な社会保障の実現
働き方にかかわらず、すべての労働者が等しく社会保険に加入できる環境を整える。
・高齢者の生活基盤の安定化
将来の年金受給額を確保することで、老後の生活基盤を強化する。
・労働市場の活性化
働く意欲を阻害していた「年収の壁」を撤廃し、多様な働き方を可能にする。
(2) 未来の労働環境への影響
適用拡大が進むことで、以下のような変化が予想されます。
<短時間労働者の増加>
社会保険の適用対象が広がることで、短時間労働者が安心して働ける環境が整います。これにより、特に育児や介護を抱える人々が労働市場に参画しやすくなるでしょう。
<企業の労務管理の高度化>
適用基準が統一されることで、企業は全従業員の労働時間を一元的に管理する必要が生じます。これに伴い、労務管理のデジタル化や外部支援の活用が進むと考えられます。
<人材確保競争の激化>
社会保険適用が拡大する中で、企業は労働条件の改善や柔軟な働き方の提供を通じて、優秀な人材を確保する競争が激化すると予想されます。
(3) 社会保険適用拡大を機会とする企業戦略
企業にとって、適用拡大は負担だけでなく、新たなチャンスでもあります。以下のような戦略を取ることで、適用拡大を活用できます。
<人材戦略の見直し>
・社会保険加入が進むことで、従業員の安心感と定着率が向上します。
・福利厚生やキャリア支援を強化することで、魅力的な職場環境を提供します。
<労務管理体制の整備>
・デジタル化やクラウド型勤怠管理システムを導入し、効率的で正確な管理を実現します。
<コスト構造の最適化>
・社会保険料の負担増に対応するため、労働時間の最適化や助成金の活用を検討します。
(4) 長期的なビジョン
社会保険適用の拡大は、短期的には負担や変革を伴うものの、長期的には日本全体の労働環境を改善し、持続可能な社会を実現するための重要な施策です。
・働き方改革との連携
働き方改革と連動し、多様な働き方が許容される柔軟な労働環境の実現を目指します。
・社会保障制度の安定化
適用拡大により、社会保険の財政基盤が強化され、将来の世代にも持続可能な制度を引き継ぐことが可能となります。
プロフィール

一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
- 第84回 フリーランスも守られる時代へ~労働安全衛生法改正のポイント
- 第83回 【中小企業経営者のための人手不足対策と外国人雇用のポイント】
- 第82回 賃上げに負けない会社をつくる!令和7年度 業務改善助成金 活用ガイド
- 第81回 【デジタル給与払い最前線】PayPay“100社突破”が突き付ける 中小企業の選択
- 第80回 50人未満でも義務化へ──中小企業が取り組むべきメンタルヘルス対策
- 第79回 「『3年以内離職率30%』を逆手に取る!中小企業の新人定着成功術」
- 第78回 「静かな退職」を防ぐ!中小企業ができる5つの具体策
- 第77回 育児介護休業法の改正が中小企業に与える影響
- 第76回 HR分野におけるAIの活用とその課題
- 第75回 変化する採用市場と学生・企業のあるべき姿勢