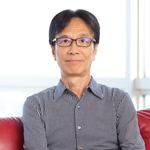第72回
変革の時代:2025年労働基準法改正が描く新しい働き方の未来
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原 京二
1.はじめに
1985年以来、実に40年ぶりとなる労働基準法の大改正が、2025年に予定されています。この改正は、単なる法律の変更にとどまらず、日本の労働環境と働き方に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。
近年、急速なテクノロジーの進化とグローバル化の波は、私たちの働き方を根本から変えつつあります。AIやロボティクスの発展、リモートワークの普及、そしてギグエコノミーの台頭。これらの変化は、従来の「会社員」という概念を超えた、多様な働き方を生み出しています。
しかし、現行の労働基準法は、このような新しい働き方に十分に対応できていないのが現状です。プラットフォームワーカーの権利保護や、副業・兼業の労働時間管理など、現代の労働環境に即した法整備が急務となっています。
2025年の改正は、こうした課題に正面から取り組み、新しい時代にふさわしい労働環境を整備することを目指しています。本コラムでは、この歴史的な改正の主要なポイントを解説し、それが私たちの働き方にどのような影響を与えるのかを考察していきます。
2. プラットフォームワーカーの法的位置づけ
デジタル技術の発展に伴い、ウーバーイーツやクラウドソーシングなどのプラットフォームを通じて働く人々、いわゆる「プラットフォームワーカー」が急増しています。しかし、現行の労働法制では、これらの働き手の多くが「労働者」として認められず、労働基準法や社会保険制度の保護から外れているのが現状です。
今回の改正では、「労働者」の定義を見直し、プラットフォームワーカーを含む新しい働き方をする人々を労働法制の枠組みに取り込むことが検討されています。具体的には、仕事の依頼元との関係性や働き方の実態を考慮し、従来の雇用関係に縛られない新たな「労働者」概念の導入が議論されています。
この改正が実現すれば、プラットフォームワーカーにも最低賃金や労働時間規制、有給休暇などの権利が適用される可能性があります。また、労災保険や雇用保険などの社会保障制度の恩恵を受けられるようになるかもしれません。
一方で、このような変更は企業側にとっては人件費の増加や管理コストの上昇につながる可能性があります。また、プラットフォームワーカー自身の中にも、柔軟な働き方が制限されることを懸念する声もあります。
法改正に当たっては、労働者の保護と企業の競争力維持、そして働き方の多様性確保のバランスをどう取るかが大きな課題となるでしょう。
3.副業・兼業に関する労働時間通算ルールの見直し
近年、キャリアの多様化や収入増加を目的として副業・兼業を行う労働者が増加しています。しかし、現行の労働基準法では、複数の事業場で働く場合、それぞれの労働時間を通算して管理することが求められています。これにより、企業側の管理負担が大きくなるだけでなく、労働者の副業・兼業の機会が制限されるという問題が生じています。
2025年の改正では、この労働時間通算ルールの大幅な見直しが予定されています。新制度では、主たる勤務先での労働時間のみを基準とし、副業・兼業先での労働時間は別個に管理するという方向性が示されています。
この改正により、以下のような効果が期待されます:
・企業の管理負担の軽減
・労働者の副業・兼業の機会拡大
・多様な働き方の促進
一方で、労働者の健康管理や過重労働防止の観点から、新たな課題も浮上しています。例えば、複数の職場での労働時間を合計すると長時間労働になるケースへの対応や、副業・兼業による疲労蓄積のリスク管理などが挙げられます。
改正に向けては、労働者の権利保護と柔軟な働き方の両立を図るため、慎重な議論と制度設計が必要となるでしょう。
4.労働安全衛生法の改正
2025年の労働基準法改正に合わせて、労働安全衛生法の改正も予定されています。この改正は、多様化する働き方や社会のニーズに対応し、より広範な労働者の安全と健康を守ることを目的としています。主な改正点は以下の通りです:
・フリーランスの労災報告義務化
これまで労働者として扱われてこなかったフリーランスにも、労災報告を義務付ける動きがあります。これにより、フリーランスの労働環境の実態把握と安全性向上が期待されます。
・小規模企業へのストレスチェック義務化
現在50人以上の事業場に義務付けられているストレスチェックを、より小規模な企業にも拡大する方針です。これにより、中小企業で働く労働者のメンタルヘルス対策が強化されます。
・高齢者に配慮した作業環境整備の努力義務化
高齢労働者の増加に伴い、彼らの身体的特性に配慮した作業環境の整備を企業に求める動きがあります。これは、高齢者の安全な就労継続を支援するものです。
・女性特有の健康課題への対応
女性労働者の増加と活躍推進に伴い、妊娠・出産・更年期などの女性特有の健康課題に対する職場での支援や配慮を強化する方針です。
・病気の治療と仕事の両立支援
がんなどの疾病を抱える労働者が働き続けられるよう、企業に対して両立支援の取り組みを求める内容が盛り込まれる見込みです。
これらの改正は、従来の労働者像にとどまらない幅広い働き手の安全と健康を守ることを目指しています。一方で、企業にとっては新たな負担増となる可能性もあり、導入に当たっては十分な準備期間と支援策が必要となるでしょう。
5.その他の重要な議論点
2025年の労働基準法改正に向けては、上記の主要な項目以外にも、いくつかの重要な議論点が浮上しています。
・連続勤務制限
現在、議論されている重要な点の一つに、13日を超える連続勤務の禁止があります。この規制は、労働者の健康保護と過重労働防止を目的としています。しかし、医療や介護など、人手不足が深刻な業界からは懸念の声も上がっており、どのように実施するかが課題となっています。
・テレワークとAIによる労務管理
コロナ禍を経て普及が進んだテレワークに関する規定の整備も重要な議題です。労働時間管理や業務効率の評価方法など、テレワーク特有の課題に対応する法整備が求められています。また、AIを活用した労務管理システムの導入が進む中、そのような技術の使用に関するガイドラインの策定も検討されています。
・国際基準との調和
グローバル化が進む中、日本の労働法制を国際基準に合わせていく必要性も指摘されています。特に、労働時間規制や有給休暇取得に関しては、欧米諸国と比べて日本の基準が緩いとの指摘があり、より厳格な規制の導入が検討されています。
これらの議論点は、変化する労働環境や社会のニーズに対応するためのものですが、その実施には慎重な検討が必要です。労働者の権利保護と企業の競争力維持のバランスを取りながら、どのような形で法制化されるかが注目されています。
6. 改正がもたらす影響
2025年の労働基準法改正は、日本の労働市場全体に広範な影響を及ぼすことが予想されます。主な影響として以下が考えられます:
<企業の人事労務管理への影響>
・コンプライアンス対応の強化
新たな規制に適合するため、企業は人事制度や労務管理システムの大幅な見直しが必要となるでしょう。
・人件費の増加
プラットフォームワーカーの保護強化などにより、一部の企業では人件費の増加が見込まれます。
・柔軟な働き方への対応
副業・兼業の促進や多様な働き方に対応するため、より柔軟な勤務体系の導入が求められます。
<労働者のキャリア形成と働き方の変化>
・多様なキャリアパスの実現
副業・兼業の規制緩和により、複数の仕事を組み合わせたキャリア形成が容易になります。
・労働者の権利意識の向上
法改正により労働者の権利が強化されることで、より良い労働条件を求める動きが活発化する可能性があります。
・ワークライフバランスの改善
連続勤務制限などにより、労働者の健康と私生活の質の向上が期待されます。
<日本の労働市場全体への影響>
・労働市場の流動性向上
副業・兼業の促進により、労働市場の流動性が高まる可能性があります。
・国際競争力への影響
労働法制の国際標準化により、グローバル企業にとっては日本での事業展開がしやすくなる一方、一部の日本企業にとっては負担増となる可能性があります。
・新しい雇用形態の創出
プラットフォームワーカーの法的位置づけの明確化により、新たな雇用形態が生まれる可能性があります。
これらの影響は、日本の労働市場を大きく変革する可能性を秘めています。企業と労働者の双方が、この変化に適応し、新たな機会を活かすことが求められるでしょう。
プロフィール

一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
- 第80回 50人未満でも義務化へ──中小企業が取り組むべきメンタルヘルス対策
- 第79回 「『3年以内離職率30%』を逆手に取る!中小企業の新人定着成功術」
- 第78回 「静かな退職」を防ぐ!中小企業ができる5つの具体策
- 第77回 育児介護休業法の改正が中小企業に与える影響
- 第76回 HR分野におけるAIの活用とその課題
- 第75回 変化する採用市場と学生・企業のあるべき姿勢
- 第74回 2025年の採用戦略:中小企業が勝ち抜くための5つの鍵
- 第73回 令和7年度の助成金最新情報
- 第72回 変革の時代:2025年労働基準法改正が描く新しい働き方の未来
- 第71回 法改正に対応!中小企業が知っておくべきカスタマーハラスメント対策のポイント
- 第70回 中小企業経営者のための「賃上げ支援助成金パッケージ活用術」
- 第69回 2025年春闘:中小企業の挑戦と変革の時
- 第68回 定年延長か継続雇用か ? データから見る高齢者雇用の最適解
- 第67回 2025年、退職代行サービス利用が過去最高に ~ 現代の労働環境が映し出す課題とは
- 第66回 2025年育児介護休業法改正と企業が行うべき対応
- 第65回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その3)
- 第64回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その2)
- 第63回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その1)
- 第62回 女性活躍推進法の改正がもたらす未来と企業への影響
- 第61回 大企業でも導入が進む「パーソナル雇用制度」
- 第60回 最低賃金1500円時代における給与の決め方
- 第59回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策(その3)
- 第58回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策(その2)
- 第57回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策
- 第56回 中小企業が注目すべきミドル世代の賃金上昇と転職動向~経験豊富な人材の採用でビジネス成長を加速
- 第55回 中小企業が賃金制度を考えるときに知っておきたい基本ポイント
- 第54回 2024年10月からの社会保険適用拡大、対応はお済みですか?
- 第53回 企業と競業避止契約の今後を考える
- 第52回 令和7年度 賃上げ支援助成金パッケージ:企業の成長と持続的な労働環境改善に向けて
- 第51回 解雇の金銭解決制度とその可能性 〜自民党総裁選における重要テーマ〜
- 第50回 令和7年度予算概算要求:中小企業経営者が注目すべき重要ポイントと支援策
- 第49回 給与のデジタル払いの導入とその背景
- 第48回 最低賃金改定にあたって注意すべきこと
- 第47回 最低賃金50円アップ時代に中小企業がやるべきこと
- 第46回 本当は怖い労働基準監督署の調査その4
- 第45回 本当は怖い労働基準監督署の調査(その3)
- 第44回 本当は怖い労働基準監督署の調査 その2
- 第43回 本当は怖い労働基準監督署の調査
- 第42回 初任給横並びをやめたパナソニックHD子会社の狙い
- 第41回 高齢化社会と労働力不足への対応:エイジフレンドリー補助金の活用
- 第40回 助成金を活用して人事評価制度を整備する方法
- 第39回 採用定着戦略サミット2024を終えて
- 第38回 2025年の年金制度改革が中小企業の経営に与える影響
- 第37回 クリエイティブな働き方の落とし穴:裁量労働制を徹底解説
- 第36回 昭和世代のオジサンとZ世代の若者
- 第35回 時代に合わせた雇用制度の見直し: 転勤と定年の新基準
- 第34回 合意なき配置転換は「違法」:最高裁が問い直す労働契約の本質
- 第33回 経営課題は「現在」「3 年後」「5 年後」のすべてで「人材の強化」が最多
- 第32回 退職代行サービスの増加と入社後すぐ辞める若手社員への対応
- 第31回 中小企業の新たな人材活用戦略:フリーランスの活用と法律対応
- 第30回 「ホワイト」から「プラチナ」へ:働き方改革の未来像
- 第29回 初任給高騰時代に企業が目指すべき人材投資戦略
- 第28回 心理的安全性の力:優秀な人材を定着させる中小企業の秘訣
- 第27回 賃上げラッシュに中小企業はどのように対応すべきか?
- 第26回 若者の間で「あえて非正規」が拡大。その解決策は?
- 第25回 「年収の壁」支援強化パッケージって何?
- 第24回 4月からの法改正によって労務管理はどう変わる?
- 第23回 4月からの法改正によって募集・採用はどう変わる?
- 第22回 人材の確保・定着に活用できる助成金その7
- 第21回 人材の確保・定着に活用できる助成金その6
- 第20回 人材の確保・定着に活用できる助成金その5
- 第19回 人材の確保・定着に活用できる助成金その4
- 第18回 人材の確保・定着に活用できる助成金その3
- 第17回 人材の確保・定着に活用できる助成金その2
- 第16回 人材の確保・定着に活用できる助成金その1
- 第15回 リモートワークと採用戦略の進化
- 第14回 「社員」の概念再考 - 人材シェアの新時代
- 第13回 企業と労働市場の変化の中で
- 第12回 その他大勢の「抽象企業」から脱却する方法
- 第11回 Z世代から選ばれる会社だけが生き残る
- 第10回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(後編)
- 第9回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(前編)
- 第8回 中小企業のための「集めない採用」~ まだ穴のあいたバケツに水を入れ続けますか?
- 第7回 そもそも「正社員」って何ですか? - 新たな雇用形態を模索する時代へ
- 第6回 成功事例から学ぶ!パーソナル雇用制度を導入した企業の変革と成果
- 第5回 大手企業でも「パーソナル雇用制度」導入の流れ?
- 第4回 中小企業の採用は「働きやすさ」で勝負する時代
- 第3回 プロ野球選手の年俸更改を参考にしたパーソナル雇用制度
- 第2回 パーソナル雇用制度とは? 未来を切り開く働き方の提案
- 第1回 「労働供給制約社会」がやってくる!