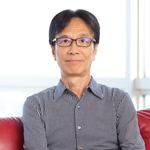第78回
「静かな退職」を防ぐ!中小企業ができる5つの具体策
一般社団法人パーソナル雇用普及協会 萩原 京二
1. はじめに
最近、最低限の業務だけをこなす「静かな退職」という現象が注目されています。これは大企業だけの問題ではなく、中小企業にも深刻な影響を与える可能性があります。「静かな退職」とは、従業員が実際に会社を辞めるわけではなく、心理的に退職状態になり、最低限必要な仕事だけをこなすようになる状態を指します。
あなたの会社でも、従業員がやる気を失い、必要最低限の仕事しかしていないと感じたことはありませんか?かつての熱意ある社員が、いつしか定時で帰宅し、新しいプロジェクトや提案を一切しなくなった...。そんな経験をしている経営者は少なくないでしょう。
本コラムでは、静かな退職の原因と、それを防ぐために中小企業が実践できる5つの具体策を紹介します。限られた経営資源の中でも実行可能な方法に焦点を当て、従業員のエンゲージメントを高める方法をお伝えします。
2. 静かな退職が中小企業にもたらす影響
「静かな退職」が中小企業に与える影響は、大企業以上に深刻なものとなり得ます。その理由を見ていきましょう。
・生産性の低下
従業員が積極的に働かないことで、組織全体の生産性が著しく低下します。特に中小企業では、一人ひとりが担う役割が大きいため、数名の従業員が「静かな退職」状態になるだけで、会社全体のパフォーマンスに直接影響します。
・チーム全体への悪影響
「やる気のある社員」と「静かに退職している社員」の間で業務負担の不均衡が生じます。結果として、意欲の高い社員への負担が増加し、彼らの士気も次第に低下してしまうリスクがあります。小さな組織ほど、この「負のスパイラル」は加速しやすいのです。
・人材流出リスク
モチベーション低下が続くと、最終的には実際の退職につながる可能性が高まります。中小企業では採用コストも大きな負担となるため、人材の流出は経営に直接的なダメージを与えます。
・中小企業特有の課題
中小企業は限られた人材で運営しているため、一人ひとりのパフォーマンス低下が企業全体に与える影響は大きくなります。また、大企業と比較して福利厚生や給与面で優位に立ちにくいという現実もあります。だからこそ、従業員のモチベーション維持には特別な配慮が必要なのです。
3. 静かな退職が起きる原因
「静かな退職」現象の背景には、現代社会における働き方や価値観の変化があります。これらを理解することで、より効果的な対策を講じることができるでしょう。
・価値観の変化
近年、特に若い世代を中心に、ワークライフバランスを重視する傾向が強まっています。仕事だけに人生を捧げるのではなく、プライベートの充実も同等に、あるいはそれ以上に価値を置く人が増えています。こうした価値観の変化を理解せずに旧来の「会社第一」の考え方を押し付けると、従業員は静かに離れていくでしょう。
・評価制度への不満
努力が正当に評価されないと感じることは、モチベーション低下の大きな要因です。特に中小企業では、評価制度が未整備だったり、経営者の主観に依存したりする場合が多く、従業員が不公平感を抱きやすい環境となっています。
・コミュニケーション不足
経営者や管理職との対話不足も大きな問題です。中小企業では「社長の考えていることが分からない」「自分の意見が届いていない」と感じる従業員も少なくありません。日々の業務に追われ、コミュニケーションが形骸化してしまうケースも見られます。
・過重労働
特に中小企業では、一人に多くの業務が集中しやすい傾向があります。「少数精鋭」が美徳とされる風土もありますが、過重な労働負担は従業員の心身の健康を損ない、やがて「これ以上頑張っても仕方がない」という諦めの気持ちにつながります。
4. 静かな退職を防ぐための5つの具体策
それでは、中小企業が実践できる具体的な対策を見ていきましょう。どれも大企業のような潤沢な予算がなくても実行可能なものばかりです。
1) 従業員との定期的な対話
最も重要なのは、従業員一人ひとりと定期的に対話する機会を設けることです。具体的には、月に一度の1on1ミーティングを実施し、業務上の課題だけでなく、キャリアの希望や悩みについても話し合いましょう。
中小企業の強みは、経営者と従業員の距離の近さです。この強みを活かし、経営者自らが積極的に声をかけることで、従業員は「自分の存在が認められている」と感じることができます。
【実践のポイント】
・1on1ミーティングは最低でも30分以上確保する
・業務報告だけでなく、従業員の希望や悩みにも耳を傾ける
・メモを取り、前回との変化を把握する
・話した内容に対して必ずアクションを起こし、フィードバックする
2) 公正で透明な評価制度を導入
成果や努力が正当に評価される仕組みを整えることは、モチベーション維持に不可欠です。中小企業だからといって、複雑な評価システムは必要ありません。むしろ、シンプルで分かりやすい評価基準を設定することが重要です。
【実践のポイント】
・目標設定は従業員と一緒に行い、納得感を高める
・数値化できる指標と定性的な評価をバランスよく組み合わせる
・評価結果は具体的な事例を挙げながらフィードバックする
・評価と報酬・昇進の連動を明確にする
3) 柔軟な働き方を提供
テレワークやフレックスタイム制など、可能な範囲で柔軟な働き方を導入しましょう。製造業など業種によっては全面的な導入が難しい場合もありますが、部分的にでも取り入れることで効果が期待できます。
【実践のポイント】
・まずは試験的に導入し、問題点を洗い出す
・業務の棚卸しを行い、テレワーク可能な業務とそうでない業務を整理する
・成果物や期限を明確にし、「見えない不安」を解消する
・有給休暇取得率の向上も並行して取り組む
4) キャリア成長支援
「この会社にいても成長できない」と感じることは、「静かな退職」の大きな要因です。社内研修やリスキリング(新しいスキル習得)プログラムを提供し、従業員に成長機会を与えましょう。
【実践のポイント】
・外部研修への参加費用を会社が負担する
・オンライン学習サービスを活用し、低コストで学習機会を提供
・社内での勉強会や情報共有会を定期的に開催する
・新しいスキルを活かせる業務機会を積極的に提供する
5) 職場環境と心理的安全性の向上
従業員同士が安心して意見交換できる環境づくりも重要です。「失敗を恐れずにチャレンジできる」「意見を言っても不利にならない」という心理的安全性が高い職場では、従業員のエンゲージメントも自然と高まります。
【実践のポイント】
・経営者自らが失敗を認め、学びを共有する姿勢を見せる
・定期的なチームビルディング活動を実施する
・オフィス環境(照明・温度・休憩スペースなど)の快適性を高める
・ハラスメント防止に関する明確なポリシーを設け、徹底する
5.おわりに
「静かな退職」はどんな企業にも起こり得る問題ですが、中小企業ならではの強み—アットホームな雰囲気や意思決定の速さ、柔軟性—を活かすことで効果的に対応することができます。
大切なのは、従業員一人ひとりを「かけがえのない存在」として尊重する姿勢です。評価制度や働き方改革も重要ですが、その根底には「人を大切にする」という価値観が不可欠です。
今日からできることから始めてみませんか?まずは従業員一人ひとりとの対話からスタートしましょう!「あなたにとって理想の働き方は何ですか?」「キャリアで実現したいことは何ですか?」—そんな質問から会話を始めるだけでも、大きな変化のきっかけになるはずです。
経営者として従業員とともに成長する姿勢こそが、「静かな退職」を防ぎ、持続可能な企業成長につながる鍵となるでしょう。
プロフィール

一般社団法人パーソナル雇用普及協会
代表理事 萩原 京二
1963年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒。株式会社東芝(1986年4月~1995年9月)、ソニー生命保険株式会社(1995年10月~1999年5月)への勤務を経て、1998年社労士として開業。顧問先を1件も持たず、職員を雇わずに、たった1人で年商1億円を稼ぐカリスマ社労士になる。そのノウハウを体系化して「社労士事務所の経営コンサルタント」へと転身。現在では、200事務所を擁する会員制度(コミュニティー)を運営し、会員事務所を介して約4000社の中小企業の経営支援を行っている。2023年7月、一般社団法人パーソナル雇用普及協会を設立し、代表理事に就任。「ニッポンの働き方を変える」を合言葉に、個人のライフスタイルに合わせて自由な働き方ができる「パーソナル雇用制度」の普及活動に取り組んでいる。
Webサイト:一般社団法人パーソナル雇用普及協会
- 第81回 【デジタル給与払い最前線】PayPay“100社突破”が突き付ける 中小企業の選択
- 第80回 50人未満でも義務化へ──中小企業が取り組むべきメンタルヘルス対策
- 第79回 「『3年以内離職率30%』を逆手に取る!中小企業の新人定着成功術」
- 第78回 「静かな退職」を防ぐ!中小企業ができる5つの具体策
- 第77回 育児介護休業法の改正が中小企業に与える影響
- 第76回 HR分野におけるAIの活用とその課題
- 第75回 変化する採用市場と学生・企業のあるべき姿勢
- 第74回 2025年の採用戦略:中小企業が勝ち抜くための5つの鍵
- 第73回 令和7年度の助成金最新情報
- 第72回 変革の時代:2025年労働基準法改正が描く新しい働き方の未来
- 第71回 法改正に対応!中小企業が知っておくべきカスタマーハラスメント対策のポイント
- 第70回 中小企業経営者のための「賃上げ支援助成金パッケージ活用術」
- 第69回 2025年春闘:中小企業の挑戦と変革の時
- 第68回 定年延長か継続雇用か ? データから見る高齢者雇用の最適解
- 第67回 2025年、退職代行サービス利用が過去最高に ~ 現代の労働環境が映し出す課題とは
- 第66回 2025年育児介護休業法改正と企業が行うべき対応
- 第65回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その3)
- 第64回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その2)
- 第63回 「年収の壁」から「労働時間」の壁へ移行する社会保険適用の新時代(その1)
- 第62回 女性活躍推進法の改正がもたらす未来と企業への影響
- 第61回 大企業でも導入が進む「パーソナル雇用制度」
- 第60回 最低賃金1500円時代における給与の決め方
- 第59回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策(その3)
- 第58回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策(その2)
- 第57回 顧客からの理不尽な要求にどう対応するか~カスタマーハラスメントの現状と対策
- 第56回 中小企業が注目すべきミドル世代の賃金上昇と転職動向~経験豊富な人材の採用でビジネス成長を加速
- 第55回 中小企業が賃金制度を考えるときに知っておきたい基本ポイント
- 第54回 2024年10月からの社会保険適用拡大、対応はお済みですか?
- 第53回 企業と競業避止契約の今後を考える
- 第52回 令和7年度 賃上げ支援助成金パッケージ:企業の成長と持続的な労働環境改善に向けて
- 第51回 解雇の金銭解決制度とその可能性 〜自民党総裁選における重要テーマ〜
- 第50回 令和7年度予算概算要求:中小企業経営者が注目すべき重要ポイントと支援策
- 第49回 給与のデジタル払いの導入とその背景
- 第48回 最低賃金改定にあたって注意すべきこと
- 第47回 最低賃金50円アップ時代に中小企業がやるべきこと
- 第46回 本当は怖い労働基準監督署の調査その4
- 第45回 本当は怖い労働基準監督署の調査(その3)
- 第44回 本当は怖い労働基準監督署の調査 その2
- 第43回 本当は怖い労働基準監督署の調査
- 第42回 初任給横並びをやめたパナソニックHD子会社の狙い
- 第41回 高齢化社会と労働力不足への対応:エイジフレンドリー補助金の活用
- 第40回 助成金を活用して人事評価制度を整備する方法
- 第39回 採用定着戦略サミット2024を終えて
- 第38回 2025年の年金制度改革が中小企業の経営に与える影響
- 第37回 クリエイティブな働き方の落とし穴:裁量労働制を徹底解説
- 第36回 昭和世代のオジサンとZ世代の若者
- 第35回 時代に合わせた雇用制度の見直し: 転勤と定年の新基準
- 第34回 合意なき配置転換は「違法」:最高裁が問い直す労働契約の本質
- 第33回 経営課題は「現在」「3 年後」「5 年後」のすべてで「人材の強化」が最多
- 第32回 退職代行サービスの増加と入社後すぐ辞める若手社員への対応
- 第31回 中小企業の新たな人材活用戦略:フリーランスの活用と法律対応
- 第30回 「ホワイト」から「プラチナ」へ:働き方改革の未来像
- 第29回 初任給高騰時代に企業が目指すべき人材投資戦略
- 第28回 心理的安全性の力:優秀な人材を定着させる中小企業の秘訣
- 第27回 賃上げラッシュに中小企業はどのように対応すべきか?
- 第26回 若者の間で「あえて非正規」が拡大。その解決策は?
- 第25回 「年収の壁」支援強化パッケージって何?
- 第24回 4月からの法改正によって労務管理はどう変わる?
- 第23回 4月からの法改正によって募集・採用はどう変わる?
- 第22回 人材の確保・定着に活用できる助成金その7
- 第21回 人材の確保・定着に活用できる助成金その6
- 第20回 人材の確保・定着に活用できる助成金その5
- 第19回 人材の確保・定着に活用できる助成金その4
- 第18回 人材の確保・定着に活用できる助成金その3
- 第17回 人材の確保・定着に活用できる助成金その2
- 第16回 人材の確保・定着に活用できる助成金その1
- 第15回 リモートワークと採用戦略の進化
- 第14回 「社員」の概念再考 - 人材シェアの新時代
- 第13回 企業と労働市場の変化の中で
- 第12回 その他大勢の「抽象企業」から脱却する方法
- 第11回 Z世代から選ばれる会社だけが生き残る
- 第10回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(後編)
- 第9回 9割の中小企業が知らない「すごいハローワーク採用」のやり方(前編)
- 第8回 中小企業のための「集めない採用」~ まだ穴のあいたバケツに水を入れ続けますか?
- 第7回 そもそも「正社員」って何ですか? - 新たな雇用形態を模索する時代へ
- 第6回 成功事例から学ぶ!パーソナル雇用制度を導入した企業の変革と成果
- 第5回 大手企業でも「パーソナル雇用制度」導入の流れ?
- 第4回 中小企業の採用は「働きやすさ」で勝負する時代
- 第3回 プロ野球選手の年俸更改を参考にしたパーソナル雇用制度
- 第2回 パーソナル雇用制度とは? 未来を切り開く働き方の提案
- 第1回 「労働供給制約社会」がやってくる!