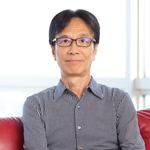第29回
新しい資本主義でのマーケティング
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

このところ新しい資本主義について考えています。資本主義が新しくなったとの言葉は、以前は「お金は金(金属:Au)だったので限られていた」ところ、今では「資本家が自由に作り出せると言えるほど自由度を増し、溢れかえった状況にある」という変化を示していると考えられます。買ってもらうとは、以前の資本主義では「限られたお金の争奪戦に勝つ」という意味合いで概ね説明できましたが、今はその枠組みでは説明しきれない現象が多く発生しています。今回は、新しい資本主義におけるマーケティングについて考えてみます。
旧来の資本主義での値付けとマーケティング
以前の資本主義では買ってもらうことは「限られたお金の争奪戦に勝つこと」と表現できるとは、どのような意味なのか?お金の総量が限られ、人々にとって必要不可欠な商品が必要最低限しかない状況だと「合理的な値付けであると説得できる」ことが「買ってもらえる理由」になったと考えられます。
では、合理的な値付けとは何か?宝石類のような希少性に価値がある商品ではなく、人々の労働によって生み出される商品であれば、原材料費に人々の働きの対価をもとに計算されたコスト及び受け入れられる利益の総合計であると考えられるでしょう(全ての供給者と需要者が、必要な情報を入手出来ている場合)。このような次第で従来の資本主義では経済学は、多くの供給者が様々に提供する商品について「標準的な商品」を前提とし、これに「コストの積み上げで定められた価格」が付されたとして理論を形成していました。
お金が政府の裁量で発行されるようになり、一方で商品がふんだんに手に入るようにもなって、取引される商品に占める生活必需品の割合が低下して、趣味や嗜好等に応える贅沢品の割合が増えてくると、マーケティング理論が発達するようになりました(厳密には、マーケティング理論はそれ以前からありました。全ての供給者・需要者が必要な情報を入手出来ている訳ではないので、逆に情報を提供することにより我が社商品を買ってもらうアプローチを目指す意味合いもあったと考えられます)。
贅沢品のマーケティングとは「我が社商品は標準的な商品よりも魅力的だ」と訴えることで、コスト積み上げ価格よりも高い価格でもって消費者に受け入れられることを狙うアプローチと表現できるでしょう。
新しい資本主義での値付けとマーケティング
資本家自身がお金を増やせる新しい資本主義では、コスト主義の必然性が薄れ、様々な価値観で価格を判断する余裕が生まれます。一方で供給側でも、生活必需品から贅沢品、その他の品(後ほどご説明します)までがふんだんに供給されるようになりました。
これにより値付けやマーケティングが更に踏み込んで質的変化を起こしています。「贅沢品」に留まらず生活必需品の中にも、コスト主義によらず値付けされる商品が生まれてきたのです。この動きを当初、オピニオンリーダー的な立場でリードしたのが資本家や高額所得者たちです。
皆さんもトヨタのハイブリッド車がハリウッドスターに認められて大人気になったことを覚えておられるでしょう。ハイブリッド車が燃費という経済的観点ではなく「地球に優しい」という価値観でもって認められたのです。
同様の現象は、例えば食品なら「体に害のある成分が一切入っていない(減らすことは容易で、これまでそれを謳って差別化した商品はあったが、一切入らないのは難しく当該商品が初めて)」などの商品自体の特性、または「商品を製造するために子供や低所得者から搾取していない。逆に手厚く分配し、これらの層あるいは先進途上国の発展に寄与している」などの商品以外の特性を持つ商品にも波及してきました。このような商品がコスト主義の束縛から抜け出て、他とは比較にならない、飛躍的に高い価格で買ってもらえるようになったのです。
ここで付言すると、以上のような動きの反動で、今までは積上げコストで売れていた生活必需品の中には、顧客から「価格に見合う価値を見出せない」と判断されるものが現れました。売れ残るか、積上げコスト以下の価格を付けて赤字覚悟で売るしかなくなったのです。
このような状況で今、新しい資本主義においては「商品の特徴や性能、品質、こだわりへの対応などが素晴らしい。それが○○○円で提供されるとは、十分に買う価値がある。是非とも手に入れたい」と認められる商品が売れるようになっています。その価値は多様で、商品に係るあるいは商品以外のあらゆる要素が関わっており、それが値付けとのバランスで顧客から判断されています。
この「お客に買われる商品の『付加価値付け』と『価格付け』を行うこと」が今におけるマーケティングの根幹機能になっています。非常に深遠な機能です。
本コラムの印刷版を用意しています
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、未来を掴んでみてください。
なお、冒頭の写真は写真ACから 城砂正春さんご提供によるものです。城砂正春さん、どうもありがとうございました。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた。総合研究所では先進的取組から地道な取組まで様ざまな中小企業を研究した。一方で日本経済を中小企業・大企業そして金融機関、行政などによる相互作用の産物であり、それが環境として中小企業・大企業、金融機関、行政などに影響を与えるエコシステムとして捉え、失われた10年・20年・30年の突破口とする研究を続けてきた。
独立後は中小企業を支える専門家としての一面の他、日本企業をモデルにアメリカで開発されたMCS(マネジメント・コントロール・システム論)をもとにしたマネジメント研修を、大企業も含めた企業向けに実施している。またイノベーションを量産する手法として「イノベーション創造式®」及び「イノベーション創造マップ®」をベースとした研修も実施中。
現在は、中小企業によるイノベーション創造と地域金融機関のコラボレーション形成について研究・支援態勢の形成を目指している。
【落藤伸夫 著書】
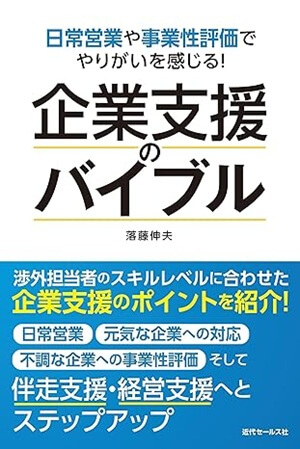
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions