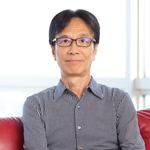第14回
人と機械の間を極める研究者 渡邊恵太さん(2)
株式会社ネオレックス 駒井 研司
■PCにも“日常の偶然性”を
人とコンピューターの関わりの研究に取り組む渡邊恵太さん。高校2年生のときに「誰のためのデザイン」という人生を変えた本に出会った。
--どんな本でしょう
「認知心理学者のドナルド・A・ノーマンが1990年に書いた本です。道具をうまく使えないのは人が悪いのではなく、道具のデザインが悪い。では誤解や誤動作を起こさないデザインをどう作るのか、という内容でした。出会った瞬間『やばい!』と思い、はまってしまいました。本どころかマンガも読まなかったのに、人生ではじめて400ページ近い大学生向けのような本を一気に読んだんです。そこから読書の苦手も革命的に変わり、意識も完全に切り替わりました。高校3年生の『課題研究』というカリキュラムの中で研究に没頭し、『モノの使いやすさとデザインの心理』というリポート論文も書きました」
--すごい衝撃だったんですね。大学進学は?
「研究に取り組んでいるとき、慶応大学SFCにヒューマンインターフェースの研究室があると知りました。大学でもどうしてもこの研究がやりたくてAO入試(受験生の個性を重視して書類や面接で選考する試験)を受験。面接で思いをぶつけたら入学できました。以来この研究を続け、17歳の頃からずっと変わりません」
--現在の「Webと日常生活の融合」というテーマは
「PCやWebにある情報に、従来と同じような感覚で触れられるようにする取り組みです。手書きのメモなら机の上やホワイトボードに残り、ふと目にすることがある。でもPCやWebに入力した情報にはなかなか出会う機会がない。人はくり返し目にしたものを覚えたり、たまたま触れたものから新たな発想を得たりします」
--わかりやすく例えると
「壁に貼った単語を自然に覚えたり、本棚に並んだ本のタイトルを見てアイデアが浮かんだり。コンピューターを使うと、こうした“日常の偶然性”から情報に触れ、そこから何かを得る機会が減ると考えたんです。意識しなくても能動的に関わらなくても、コンピューターの中の情報に出会える世界をつくる。そのために、コンピューターを生活の中に溶け込ませる方法を研究しています」(つづく)
【プロフィル】渡邊恵太 わたなべ・けいた 慶大湘南藤沢キャンパス(SFC)で学び、政策・メディア博士号取得。明大総合数理学部先端メディアサイエンス学科、専任講師。32歳。東京都出身。

2014年1月13日「フジサンケイビジネスアイ」掲載
- 第35回 自ら考え判断・行動する子供に 楢崎和正さん、松下武司さん(4)
- 第34回 できない子供を排除しない ラグビースクール講師 楢崎和正さん、松下武司さん
- 第33回 子供たちには声をかけて接する ラグビースクール講師 楢崎和正さん、松下武司さん
- 第32回 子供たちの人としての成長見守り ラグビースクール講師 楢崎和正さん、松下武司さん(1)
- 第31回 無理せず簡単なことから始める 雑誌編集長 山口裕之さん(最終回)
- 第30回 「太るための努力」をやめて痩せる 雑誌編集長 山口裕之さん(3)
- 第29回 低炭水化物ダイエットが主流に 雑誌編集長 山口裕之さん(2)
- 第28回 ダイエットの秘訣は楽しむこと 雑誌編集長 山口裕之さん(1)
- 第27回 自分を毎日採点 繰り返して習慣に クオンティファイド・セルフ(下)
- 第26回 多様な技術と組み合わせ楽しく応用 クオンティファイド・セルフ(中)
- 第25回 機器活用し自分の状態を客観視 クオンティファイド・セルフ(上)
- 第24回 信念が人脈・天職を呼ぶ 秘書参謀 星久人さん(最終回)
- 第23回 常にトップの立場で考え先を読む 秘書参謀 星久人さん(4)
- 第22回 思い付いたことをどんどん録音 秘書参謀 星久人さん(3)
- 第21回 念願の英国勤務から突然呼び戻し 秘書参謀 星久人さん(2)
- 第20回 今大きいかより、将来性 秘書参謀 星久人さん(1)
- 第19回 ITのアンバサダーに選ばれる営業マン 堀江賢司さん(最終回)
- 第18回 ITのアンバサダーに選ばれる営業マン 堀江賢司さん(3)
- 第17回 ITのアンバサダーに選ばれる営業マン 堀江賢司さん(2)
- 第16回 ITのアンバサダーに選ばれる営業マン
- 第15回 人と機械の間を極める研究者 渡邊恵太さん(最終回)
- 第14回 人と機械の間を極める研究者 渡邊恵太さん(2)
- 第13回 人と機械の間を極める研究者 渡邊恵太さん(1)
- 第12回 「将来」と「今」のバランス意識 対談 亀井美佳さん、山崎篤さん(最終回)
- 第11回 がむしゃらなだけでは評価されない 対談 亀井美佳さん、山崎篤さん(2)
- 第10回 義務でない目的は休みの醍醐味 対談 亀井美佳さん、山崎篤さん(1)
- 第9回 体調管理は自分より周囲のために 経営者・渡辺光五さん(最終回)
- 第8回 顧客満足 自分たちにとっての品質 経営者・渡辺光五さん(4)
- 第7回 当たり前のことを徹底してやった 経営者・渡辺光五さん(3)
- 第6回 大学に通いながら会社を切り盛り 経営者・渡辺光五さん(2)
- 第5回 楽しんで運営、気づけば経営者に 経営者・渡辺光五さん(1)
- 第4回 意識的に外へ出て刺激受ける 矢内文章さん(最終回)
- 第3回 劇には不確定な要素を入れる 矢内文章さん(3)
- 第2回 回り道しないといけない 矢内文章さん(2)
- 第1回 分かってもらうことの大変さ 矢内文章さん(1)