第13回
世界はアフターコロナに移行 日本はどうする
イノベーションズアイ編集局 経済ジャーナリストA
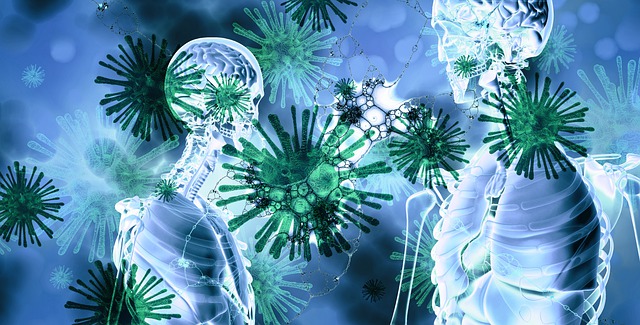
最近は、経済活動と感染防止の両立、ということがいわれているが、法的な位置づけを変更しない限り、抜本的には変わらない。その点、欧米は現実的だ。死亡率や重篤化率、ワクチンや治療薬の動向などを勘案して、制限を大幅に解除している。たとえば日本と同様に感染者数が拡大しているオーストラリアは、感染者の積極的な追跡をやめるなど、対策の大幅な緩和を断行した。コロナ対策の多くは規制などから自己責任に移行する。狙いは経済復興だ。
日本経済はだいぶ疲弊している。表面上は見えないが、赤字公債の多量発行と引き換えに莫大な費用がコロナ対策に投じられてきた。世界情勢の変化もあり、史上まれにみる原油高、穀物高だが、これに近年まれにみる円安が追い打ちをかけている。世界的にもまれな赤字大借金国である日本は、頼みの綱であった外国とのやり取りの中での収支である「経常収支」も赤字化した。コロナ対策はどうでもいい、と言っているわけではない。この世界の中で稼ぐ力さえなくなりつつあることに大きな不安を感じている。
日本人は自己責任意識に乏しい半面で、ルールは守る。そのルールがどんなものかに関わらず、守らない人にも厳しい。本質を追求することはあまりなく、どうでもよさそうな不毛な努力が盛大に展開されやすい。
日本ではここ10年、コーポレートガバナンスの拡充が進められてきた。当初は遅々として進まなかった仕組みづくりだが、東京証券取引所の上場基準やガイドラインなどの整備を通じ、いまでは大半の企業が“複数の社外取締役を置く”など準拠体制を整えている。コーポレートガバナンスを充実させることの目的は“企業が稼ぐ力をつける”ことだ。しかし、仕組みを整えても効果が出ていないところが多い。それもそのはず。“ルールに則り体制を作っただけ”だからだ。稼ぐ力などつくわけがない。まさに「仏作って魂入れず」という感じだ。
コロナ対策もルールのためのルールになっていないか。何のためのルールなのか。どういう結果を目指しているのか。きちんと考える時にきている。
経済ジャーナリスト A

















