第221回
企業立て直しのゴールを描く(売上実現)
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

前回、長引くコロナ禍やロシア・ウクライナ情勢等の影響を受けて売上・利益が減少、連続赤字ひいては債務超過に陥ってしまった企業が「会社を持続させたい。今はキャッシュがあるが、不足する頃には金融機関から融資を受けたい」と考えて事業計画を策定する場合には、金融機関の関心事を踏まえた内容とする必要があることを、財務数値の側面からご説明しました。今回は、売上をどのように計画していくかを、考えてみます。
資金調達を目指した事業計画とは
事業計画は、もしそれを自社内だけで活用する目的なら、どんな内容でも問題ありません。例えば「今後は売上の拡大は求めず、利益を半分にして地域と社員に配分する」と決めることになんらの問題はないのです。一方で、売上・利益が減少して連続赤字ひいては債務超過に陥った企業が持続化を目指して融資による資金調達を行おうとする場合の事業計画は、業績を改善して財務体質を強化する内容である必要があります。
ここで最初に念を押させて頂きます。「事業計画は、本来は企業が想いの通りに描くものだが、コロナ禍等による景気の落ち込みや事業環境の悪化が原因で資金調達が必要になったので、金融機関が満足する事業計画を策定することにした。この計画は『お金を借りるための方便』なのだから、それを守る必要はない。プロに作成させて提出、金融機関に受け取ってもらったら、こちらはゴミ箱行きで良い」と考えてはなりません。
将来に計画が実現できずに『信頼できない先だ』との印象を金融機関に与えるのは100害あって1理なしだからです。ましてや金融機関に「貸しやすい先だ」と判断してもらうために数字を操作する(粉飾)などもっての他で、「相手を騙して融資を受けた」と裁判沙汰になる可能性があります。
「とすると随分とハードルが高いぞ。計画には金融機関が『この会社は将来には売上・利益共に改善されて企業としての持続が可能な状況になっており、返済も可能と考えられる』あるいは『持続可能・返済可能なレベルに向かって着実に展開しており、悪化に転じる可能性は少ない』と考える数値計画を盛り込むという。今、赤字続きで債務超過になっている企業には、思いもつかないような数字だ。」その通りだと思います。
細分化することで、実現可能と明らかにしていく
「連続赤字・債務超過の企業が近未来に『持続可能・返済可能』と判断される計画を立てろとは、つまり見た人100人が100人とも「壮大な夢」と感想を漏らすような計画を立てろ、というようなものだ。矛盾している。」そのお気持ち、よく分かります。例えばある食品小売が、「特売を実施、チラシ等で広く宣伝して売上10%増を目指す。これにより損益分岐点を超えて黒字化を目指す」などと記載しても、金融機関からは「この計画、実現できますか?」と疑問視されるでしょう。
一方で、高いレベルの目標を実現して金融支援を獲得している企業もあります。そのような企業は、魔法を使っている訳ではありません。売上・利益向上に役立つことを一つ一つ(複数を組み合わせて)着実に行なっています。事業計画ではそれらを、売上拡大に資する取り組みとして細分化して記載し、納得を得ているのです。
売上は「一人当たり購入価格 × 顧客数」で表現できます。「一人当たり購入価格」は、「いつも購入する物品の単価を高める」、あるいは「いつも購入する物品以外のものを買ってもらう」方法で高められます。食品小売店なら、廉価品よりブランド品の方が「一味違う」と伝えて、より高い商品に手を伸ばしてもらえるかもしれません(これで2%増を期待)。今まで当店ではなく専門店(しかし、遠くて不便)で買っていたケーキ等をラインナップに加えられるかもしれません(3%増を期待)。
顧客数を増やすにも、例えば食品小売店なら「これまで主婦だけだったが、家族も呼び込む」あるいは「当店を利用していなかった顧客を呼び込む」方法が考えられます。お父さんに喜ばれる晩酌の酒やおつまみ等に加え、子供たちの人気キャラクターを冠した商品等をラインナップに加えられるかもしれません(2%増を期待)。キッズスペースを設けることで、「この店ならゆっくり買い物できるので、少し遠いけれど行ってみようか」と新規顧客を獲得できるかもしれません(3%増を期待)。
「店舗もお客も変わらないのだから、目新しいことはできない」と考えがちですが、必ずしもそう考える必要はありません。無理だと思っていた10%の売上拡大も、2%、3%拡大する策を組み合わせることで可能になるかもしれません。要素を細分化して考えることで、できることはまだあるはずであると気付ける可能性があります。
本コラムの印刷版を用意しています
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、資金調達する方法をしっかりと学んでみてください。
なお、冒頭の写真は 写真AC から mybears さんご提供によるものです。mybears さん、どうもありがとうございました。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた後、事業改善手法を身に付け業務・経営側面から支える専門家となる。現在は顧問として継続的に企業・経営者の伴走支援を行っている。顧問企業には財務改善・資金調達も支援する。
平成27年に「事業性評価」が金融庁により提唱されて以来、企業にも「事業を評価してもらいたい。現在の状況のみならず将来の可能性も見越して支援してもらいたい」との意識を持ち、アピールしてもらいたいと考えて『「事業性評価」が到来!あなたは資金調達できますか?』コラムを連載(2017年1月スタート)。当初は読者として企業経営者・支援者を対象していたが、金融機関担当者にも中小企業の事業性評価を支援してもらいたいと考え、2024年1月からは『「事業性評価」が到来!あなたは資金調達できますか?plus』として連載を再スタートさせた。
現在は金融機関職員研修も行うなど、事業改善と金融システム整備の両面からの中小企業支援態勢作りに尽力している。
【落藤伸夫 著書】
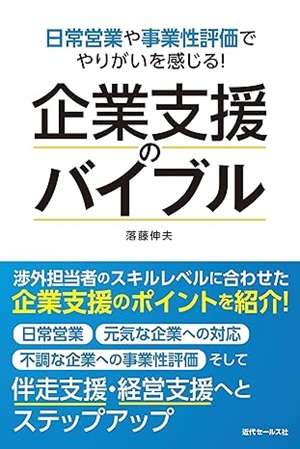
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions











