第168回
「戦略計画」とはどんな計画か
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

多くの中小企業にとって2020年は、新型コロナウイルス感染症の蔓延で事業活動が制約されるなど散々な年でした。半年前に2021年を迎えるにあたり「今年前半にはコロナ禍は沈静化し、春過ぎるあたりにはV字回復できるだろう」と期待していた経営者・企業人も多かったことでしょう。しかし半年経ち、その期待は裏切られました。東京では3回目の非常事態宣言が解除されても「まん延防止等重点措置」となっており、それで収束すると思いきや、リバウンドを心配する状況です。
このような状況で、時が過ぎるのを待ち、事業環境の回復から自社の業績も自然に元に戻ると期待するのは、あまり良い策とは思えません。自らの手で現状を打開するのが上策と考えられます。「今までとは違うことにトライする」ことで、自ら血路を開いていくのです。今回は、この点について考えてみましょう。
事業再構築における「戦略計画」
これまで中小企業は、例えば現事業を止めて新事業に乗り出すという大きなリスクは避けるのが定石でした。このため「今までと違うことにトライする」は、多くの企業にとって、今まで体験したことのない取組みだと考えられます。これを成功させるにはどうすれば良いか?
前回、新たな試みを成功させるために「戦略計画」がポイントになるとお話ししました。戦略計画とは、耳慣れない言葉かもしれません。「調べてみても、よくわからないぞ」という声も聞こえてきそうです。筆者は「戦略計画」は、形式ではなく内容だと考えています。「今までとは違うことに取組むことを、無謀ではなく『価値あるトライ』にできる内容が書き込まれた計画」です。
「抽象的に過ぎて、よく分からない」との声が聞こえそうですね。戦略にはある意味、無数の方法がありますが、今年、話題になっている「事業再構築」から考えてみましょう。ある飲食店が惣菜販売に舵を切ったとします。今までの飲食店営業での売上・利益の目処は立ちますが、惣菜販売は、提供する「もの」は似ているとはいえ、顧客の購買動機や場面が全く違うので、そう簡単には売上・利益目処は立たないでしょう。そのような事情でか「チラシを作って店頭で配布したり、近所に配達する。それで足りなかったらキャンペーンを打つ。次はTVコマーシャルを検討する。できることは何でもやる」という計画をよく見かけますが、戦略的とは言えません。
この場合「飲食店での顧客の半分を惣菜店に引き寄せて売上をあげると共に、これら顧客の来店頻度を高め、口コミで顧客を広げて売上に繋げる」方法を探ることで、戦略的な取り組みを企画できるかもしれません。例えば、飲食店で誕生日によく利用されたメニューを再現、それを自宅で楽しめるようパッケージ化して誕生日に届けるサービスを準備して、以前の顧客にアプローチします。過去に誕生日で利用してくれた日時が分かっているなら、企画する1ヶ月前に案内状を送れます。実際に利用したお客には割引券を送って来店を促します。「お友達を紹介してくれたら半年以内のホームパーティー利用の割引チケット」を配布、顧客の幅を広げると共に、もともと年に1度しか使わなかった顧客に2度、3度とホームパーティー利用する理由を作ってもらいます。アンケートから惣菜やホームパーティーで一緒に利用する商品をリサーチ、自社では対応できない商品も一緒に提供できる他店と連携できます。これは、ダイレクトメールを送ることができる対象者を増やすことにも繋がります。
製品に込められた「戦略計画」の例
戦略性は、事業再構築の例で挙げたようにアクションに込めるだけでなく、製品にも込めることができます。その代表例はアマゾン社が提供しているKindleです。Kindleが以前にSONYが発売していた電子書籍リーダー、Librieに触発されて開発されたことを知る人は少なくないでしょう。しかし今や電子書籍リーダーとしてLibrieを思い出す人はほとんどなく、Kindleが一般的です。なぜ、そうなったか?それはLibrieは書籍を電子機器に保存し閲覧することに集中していたが、Kindleは電子書籍を購入することにまで徹底的にこだわったからです。アマゾンは、顧客が簡単に電子書籍を購入できるようKindleに通信回線(3G)を搭載しました。「これをやればコストはかかるけれど、顧客はこちらを選ばざるを得なくなる」という要素を製品に加えておくことで、新製品開発を戦略的な取組みにしたのです。
「中小企業は資源が少ないので、戦略を考える暇はない」との声を聞くことがあります。前段は正しい指摘ですが、後半は間違っています。「戦略なく、リアルな資源を浪費しながらPDCAを回すのは難しい」が正しい指摘です。では、どうすれば良いのか?まずは戦略計画を立てましょう。「これをやれば顧客はこちらを選ばざるを得なくなる」策を考え、計画に盛り込むのです。それが中小企業の生き残る道だといっても、過言ではありません。
本コラムの印刷版を用意しています
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、資金調達する方法をしっかりと学んでみてください。
なお、冒頭の写真は写真ACから 實悠希 さんご提供によるものです。實悠希 さん、どうもありがとうございました。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた後、事業改善手法を身に付け業務・経営側面から支える専門家となる。現在は顧問として継続的に企業・経営者の伴走支援を行っている。顧問企業には財務改善・資金調達も支援する。
平成27年に「事業性評価」が金融庁により提唱されて以来、企業にも「事業を評価してもらいたい。現在の状況のみならず将来の可能性も見越して支援してもらいたい」との意識を持ち、アピールしてもらいたいと考えて『「事業性評価」が到来!あなたは資金調達できますか?』コラムを連載(2017年1月スタート)。当初は読者として企業経営者・支援者を対象していたが、金融機関担当者にも中小企業の事業性評価を支援してもらいたいと考え、2024年1月からは『「事業性評価」が到来!あなたは資金調達できますか?plus』として連載を再スタートさせた。
現在は金融機関職員研修も行うなど、事業改善と金融システム整備の両面からの中小企業支援態勢作りに尽力している。
【落藤伸夫 著書】
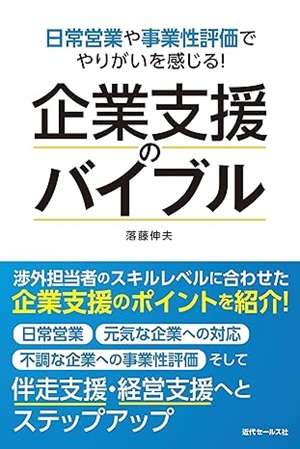
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions











