第240回
今年の振り返り(輝かしい来年の足掛かりとなる夢)
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

2022年の振り返りも、今回で終了とします。最後に、来年を輝かしい年とするため、今年を足掛かりとする方法を考えたいと思います。
「夢を実現する」の意味
皆さんは「夢を実現する」と言うと、どうお感じになるでしょうか?「確かに夢を見ていた時代もあるけれど、今やそんな時期ではない。厳しい事業環境下、現実を見るしかない」と言われる方が多いかと思います。そのお考え、とてもよく分かります。企業経営を考えるとき、現実が出発点でなければ「只の絵空事」だからです。但しその言葉が「苦しい現状を打開するのは難しい。不可能だ」という意味合いがあるなら、その考えには反対です。今よりも余程苦しい事業環境下(例:第2次大戦中・戦後)でも多くの企業が生き残り、その後に力強く発展を遂げました。今の状況から「もうだめだ」と考えてしまうのは、本当にもったいないと思います。
では、自社の持続・発展を願うなら、何が必要か?「夢を描く」ことが必要です。夢を描かないで、自社が持続・発展できる可能性はほとんどありません。夢を描くことが、自社が持続・発展できる出発点です。まさに「夢しか実現しない」と言えます。
「それはおかしい。『夢なんて実現しない』というのが常識だ」と言われる方も、おられるかもしれません。ここでいう夢とは、現実と対比される「架空」などの意味ではありません。例えば「私は火星に国を打ち立て、国王になりたい」という夢は実現しません。一方で、ここでいう夢とは「自分がありたい姿を明確に、生き生きと鮮やかに描いたもの」という意味です。「現状を打破してこんな形の将来を実現したい」との現実に即した夢は、実現できる可能性があります(大いにあります)。
ここで「会社を持続・発展させたい」という願望を持っている人がいたとしましょう。一人はそう言うだけで「夢」は描いていません。もう一人は「実現したい会社の姿をビジュアルに、生き生きと鮮やかに描いた」とします。どちらが実現できるか?後者に決まっていますね。この意味で「夢しか実現しない」と言えるのです。
夢がなぜ実現に繋がるのか
なぜ夢を明確に描いた方が良いのでしょうか?第1に、自分にとってブレない目標になるからです。「以前にお客様が言っていた要望を新製品として実現しよう」と明確にイメージすれば、「やっぱり値引しようか?」との迷いを断ち切れます。
第2は、夢の実現に向けた取組が分かるからです。実現したい新製品が明確にイメージできれば、その実現に必要な行動を計画できるでしょう。
第3は、自分のモチベーションが高まるからです。「事業が上手くいかず、何とかしなければならない。でも、まず何から始めて良いのか分からない」という状態だと、実行のモチベーションは高まりようがありません。実現したい姿と、そのために必要な行動を明確に、生き生きと鮮やかに描けば、「よし、実行しよう」との気持ちが高まります。
第4は、関係者の応援が得られるからです。皆さんが「お客様の要望を実現したい」と言うだけなら、力を貸すとか資金を提供するなど具体的に応援してくれる人はいないでしょう。「新製品開発する」と明確に示されると「この夢に乗った!支援する!」と決心できます。
将来を切り拓く夢を描きましょう
こう考えると「実現に繋げる夢」を描くとは、多くの中小企業にとって、既存事業の改善、あるいは新製品開発などの事業再構築を目指す事業計画を作成することだと、お分かり頂けるでしょう。コロナ禍による行動制限などに苦しめられ、この一年はロシア・ウクライナ戦争により拍車がかかった物資不足・物価高騰にも苦しめられた少なからぬ企業が、事業改善や事業再構築に向けた事業計画を作成、実践して変化を遂げました。「夢を描いて実現する、夢しか実現しない」を地でいったのです。
「自分の夢を明確に描く大切さは分かった。しかし事業計画の策定となると、なかなか難しい。以前に取り組んで上手くいかなかった経験もあるので、どうしても前向きになれない。誰か相談に乗ってくれないだろうか」と思われるなら、地域の「よろず支援拠点」あるいは 取引金融機関などにご相談ください。StrateCutionsでもご相談に乗っていますのでご遠慮なくご連絡ください。
ではみなさん、良いお年をお迎えください。
本コラムの印刷版を用意しています
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、資金調達する方法をしっかりと学んでみてください。
なお、冒頭の写真は 写真AC から fujiwara さんご提供によるものです。fujiwara さん、どうもありがとうございました。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた後、事業改善手法を身に付け業務・経営側面から支える専門家となる。現在は顧問として継続的に企業・経営者の伴走支援を行っている。顧問企業には財務改善・資金調達も支援する。
平成27年に「事業性評価」が金融庁により提唱されて以来、企業にも「事業を評価してもらいたい。現在の状況のみならず将来の可能性も見越して支援してもらいたい」との意識を持ち、アピールしてもらいたいと考えて『「事業性評価」が到来!あなたは資金調達できますか?』コラムを連載(2017年1月スタート)。当初は読者として企業経営者・支援者を対象していたが、金融機関担当者にも中小企業の事業性評価を支援してもらいたいと考え、2024年1月からは『「事業性評価」が到来!あなたは資金調達できますか?plus』として連載を再スタートさせた。
現在は金融機関職員研修も行うなど、事業改善と金融システム整備の両面からの中小企業支援態勢作りに尽力している。
【落藤伸夫 著書】
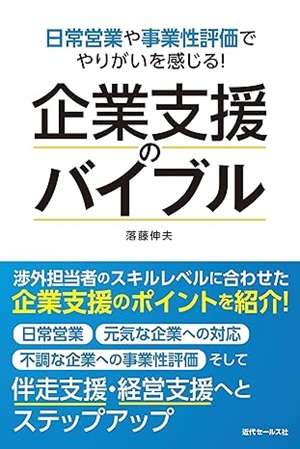
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions











