第187回
自社の儲け方を考える
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

コロナ禍で思うような事業活動ができなかった企業が多かったせいか、年末商戦が前倒しになっていると感じます。大規模店舗の店頭に飾られるクリスマスツリーは、数年前までは12月に入ってから設置されていたように記憶していますが、今年は既に何箇所かで見かけることができました。「小売業は簡単だな、クリスマスなどの季節に乗じれば販売促進できるのだから。」そうでしょうか?前回、儲けにフォーカスした戦略を練らなければ成功例をコピーしたとしても失敗する可能性があること、成功の鍵となる儲け方は成功例のコピーではなく自社で考える必要があることについて考えました。今回はこの点を、もう少し深掘りしましょう。
様々な「儲け方」の例
例えとして、小売業の「儲け方」について考えてみましょう。「簡単だよ、安く仕入れて高く売る」だ。仰る通りですが、それで満足したのでは今までの殻を破ることはできないでしょう。ある企業は「薄利多売」で、単位当たりの自社取り分を少なめに留めることで多くの顧客の心を捉え、結果的には大きな利益を得ようとする戦略を採っています。逆に、真価を理解できる一握りの顧客に気に入ってもらい、高価な商品を買ってもらうことで大きな利益を得ようとする戦略の企業もあります。
その中間にある商品の典型的な戦略として差別化があります。昭和から平成の前半では機能の拡大や性能の向上などがメインだったところ、平成も後半になるとデザインなども重視されるようになりました。また以前なら「この製品は性能的にもデザイン的にも海外の○○ブランドに限る」など単純に認知されていた印象ですが、今は立地の良い場所に華やかな店舗を設置すると共にアフターサービスも充実させるなど総合的な対応力を身に付け、ブランドとして結実させている例もあります。
ビジネスモデルを工夫している例もあります。ある商品では、本体価格は抑えて消耗品で利益を得るビジネスモデルが採られています。別の商品では、本体を利用するソフトウエア等は無料化・低料金化することで高価な本体を購入するビジネスモデルとなっています。これまで通り本体もソフトウエア等も有料で販売しているが、今まで店頭で購入しなければならなかったソフトウエア等をオンラインで購入可能とすることで、それを活用できる本体を買い直させ、別途ソフトウエア等も購入するよう促すビジネスモデルを採っている企業もあります。
ベストな儲け方を探し出す
「選択肢が多いのは分かった。では、いろいろ試行錯誤していこう。」トライする積極性は素晴らしいですが、中小企業は試行錯誤する時間も資源も限られています。それに例えば薄利多売と厚利少売を交互に試したら顧客から「この会社は誰にどんなベネフィットを与えようとするのか分からない」と、愛想をつかされかねません。無闇な試行錯誤ではなく賢い戦略が必要です。
「どうしたら賢く戦略が立てられるのか?」中小企業の場合、ターゲット顧客と自らの資源(持てる人材・機械設備等・ノウハウ等)との組み合わせで考えることが勧められます。最も良いお客様になりそうな対象が「この商品は良い。これを提供する会社は信頼できるので取引したい。さらには他に紹介したい」と思ってもらえるよう目指すのです。「ターゲットを絞れとの提案だな。しかし大企業は間口を広げて成功している。逆は、自らチャンスを潰すことにならないか。」その疑問はもっともですが、間口を広げるのは大企業の戦略、中小企業はターゲットを絞ってこそ効果的にアプローチできます。
様々な「儲け方」から最善を選びブラッシュアップする
自社の最も良いお客様になりそうな対象が決まったら、そのお客様が「この商品は良い」あるいは「これを提供する会社は信頼できる」と言ってくれる事業の仕方を考えます。例えばパン屋から、住宅地・商業地・ビジネス街の顧客に合わせて揃えるべき商品を考えるべきことが理解できるでしょう。またそれをどのように売るか?こちらは当社の資源も考慮に入れる必要があります。薄利多売あるいは高付加価値のどちらが良いのかは、お客様の好みもありますが、一方で当社の人材・機械設備等・ノウハウ等によるところが大きいのです。大量生産する設備がなく、それを揃える資金も十分でない一方で腕の良い職人がいるなら高付加価値路線が適当でしょう。
そこまで決まると自社の「儲け方」を詰めて考えます。例に挙げたパン屋なら「少し高いが美味しいパンがある」と口コミを期待する方法や、チラシで広告する方法があります。SNSも利用できます。これらのマーケティング策に時間と資金を投入するか、しないかは実は「儲け方」を決める第一歩です。今では定額制(サブスク)も利用できるかも知れません。お客様が喜び、自社でも十分な利益を出せ、継続していける「儲け方」を考えていくのです。ぜひ取り組んでください。支援が必要な場合には、StrateCutionsでもご相談に応じています。
本コラムの印刷版を用意しています
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、資金調達する方法をしっかりと学んでみてください。
なお、冒頭の写真は 写真AC から PhotoNetwork さん ご提供によるものです。PhotoNetwork さん、どうもありがとうございました。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた後、事業改善手法を身に付け業務・経営側面から支える専門家となる。現在は顧問として継続的に企業・経営者の伴走支援を行っている。顧問企業には財務改善・資金調達も支援する。
平成27年に「事業性評価」が金融庁により提唱されて以来、企業にも「事業を評価してもらいたい。現在の状況のみならず将来の可能性も見越して支援してもらいたい」との意識を持ち、アピールしてもらいたいと考えて『「事業性評価」が到来!あなたは資金調達できますか?』コラムを連載(2017年1月スタート)。当初は読者として企業経営者・支援者を対象していたが、金融機関担当者にも中小企業の事業性評価を支援してもらいたいと考え、2024年1月からは『「事業性評価」が到来!あなたは資金調達できますか?plus』として連載を再スタートさせた。
現在は金融機関職員研修も行うなど、事業改善と金融システム整備の両面からの中小企業支援態勢作りに尽力している。
【落藤伸夫 著書】
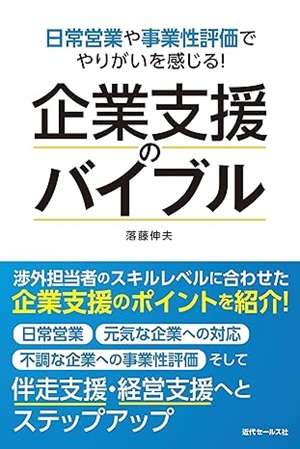
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions











