第296回
まず社員の共感を得て顧客に波及させる
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

今月は「共感」について考えています。競争が激しい事業環境下、自社を選んでもらうのは簡単ではありません。「そんな製品があるのだな。それを作っている会社があるのだな」と認知されても、選んでもらうための道のりが長すぎるのです。そのほとんどが忘却される中で、自社は覚えてもらうために何ができるか?その一つに「共感」があります。今回は波及により共感を得ていく方法について考えてみます。
競合に埋もれないように感情を揺さぶる
モノが溢れる時代、顧客は何を理由に選んでいるのか?機能や性能、デザインなどで好みのものを選ぶというアプローチがあります。今は次から次へと「良さそうなモノ」が市場に出回るので、選ぶことが楽しみな顧客には嬉しい世の中ですが、供給者としては厳しい事業環境です。人気ある商品カテゴリーでは競合の参入が絶えないので、競争は激化するばかりです。このような状況下「この製品は、私の願いを体現している。この会社の考えや行動は、私の気持ちを満たしている」と認めてもらうことで購買行動に繋がります。
共感とは、他人の意見や感情等に心揺さぶられて同意すると共に、それを共有することが快いために関係性を持続させようとの気持ちが働く状況と言えるでしょう。このため企業は、自分の意見や感情等を表明しなければ共感は得られません。ミッションや経営理念、ビジョンとして表現する他、商品(製品)・サービス、付加的なサービス、店舗、社員の言動、顧客や社会へのフォローなど、可能な手段をできるだけ活用して(全て活用して)、自社の目指す境地など(共感ポイント)を表現できます。
一方で、共感を自社ビジネスと両立させるのは並大抵ではありません。ほとんどの企業が成功していない、あるいは「諦めている」と言ってよいほどです。しかし、共感を得ることなく選ばれるのも茨の(困難な)道です。成長企業の多くが「生活の利便性」、「健康や美の保持・向上」、「社会等への思いやり」、「お財布に優しい低価格」などでの共感を軸としていることを鑑みると、全力を尽くして取り組む価値のあるアプローチと言えそうです。
社員から共感を得て、次に顧客にアプローチする
ビジネスとの両立が難しい「共感」を確立している企業は何を行っているのか?まず社員からの共感を勝ち取っています。会社と社員は、昔は対立関係にあり「社員は、会社から搾取されていると感じる関係」でした。会社と社員の対話は以前は「ボーナス闘争」などと表現されていたほどです。
しかし実は会社と社員の関係は、対立である必要はありません。共感し合える関係も可能で、実現している会社もあります。インターネットで検索すると、世界的に有名なホテルチェーンをはじめとして、日本企業の名前も挙がっています。リスト見ると、それら企業は顧客の共感も得ていると分かるでしょう。
なぜ社員の共感を先にすべきか?会社に成功体験が生まれるからです。社員の共感を得るのは簡単ではありません。数多くの試行錯誤が必要です。しかし社員の反応は、顧客の反応よりもはるかにダイレクトです。直接に意見を聞けますし、PDCAを回すスピードは顧客の場合より数倍も早いでしょう。こうやって遂に共感を持ってもらえると、成功体験をもとに、コミュニケーションが難しい顧客にもアプローチできるようになります。
また社員の共感を勝ち得ると、それが社外にも伝播するようになります。会社の経営理念やミッション、ビジョン等に共感する社員は、接客時にもそれらが目指す雰囲気を醸し出すでしょう。まずは社員毎に雰囲気や態度が大きく変わることなく、一つの方向性を持っていることに驚くと思われます。社員と接する体験をベースに、顧客は企業に共感できるようになるのです。
社員の共感を先に得るとなぜ、顧客との共感がビジネスと両立するのでしょうか?会社の構成員である社員が会社に共感しているとは、会社が真の意味で共感に値する存在になったことを意味します。一方で社員が共感せず、顧客だけ共感していたら、それは「張りぼて」にすぎません。実体のない共感を構築・維持しようとするので無理をして、ビジネスにならないのです。
実体のある共感なら、対話をしてビジネスが成り立つ落し処を定めることができます。それゆえ社員と顧客の両方から共感を得ることが、企業にとって真の存立基盤となります。
本コラムの印刷版を用意しています
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、資金調達する方法をしっかりと学んでみてください。
【筆者へのご相談等はこちらから】
https://stratecutions.jp/index.php/contacts/
なお、冒頭の写真はCopilot デザイナーにより作成したものです。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた後、事業改善手法を身に付け業務・経営側面から支える専門家となる。現在は顧問として継続的に企業・経営者の伴走支援を行っている。顧問企業には財務改善・資金調達も支援する。
平成27年に「事業性評価」が金融庁により提唱されて以来、企業にも「事業を評価してもらいたい。現在の状況のみならず将来の可能性も見越して支援してもらいたい」との意識を持ち、アピールしてもらいたいと考えて『「事業性評価」が到来!あなたは資金調達できますか?』コラムを連載(2017年1月スタート)。当初は読者として企業経営者・支援者を対象していたが、金融機関担当者にも中小企業の事業性評価を支援してもらいたいと考え、2024年1月からは『「事業性評価」が到来!あなたは資金調達できますか?plus』として連載を再スタートさせた。
現在は金融機関職員研修も行うなど、事業改善と金融システム整備の両面からの中小企業支援態勢作りに尽力している。
【落藤伸夫 著書】
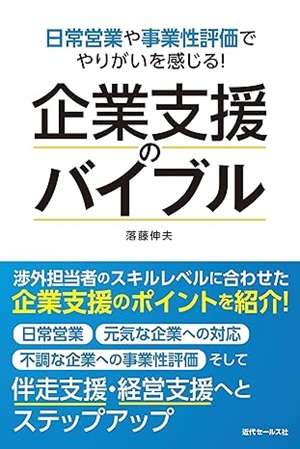
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions
- 第297回 トランプ関税の激震に備える
- 第296回 まず社員の共感を得て顧客に波及させる
- 第295回 企業は何に「共感」を持ってもらえるか
- 第294回 企業が大切にしたい「共感」
- 第293回 生き残りを模索する企業からコツを学ぶ
- 第292回 地方で生き残りを模索する企業から学ぶ
- 第291回 話し相手になる計画書を作成する
- 第290回 目指すべき水準の目標を立てる
- 第289回 夢が実現する経路を描く
- 第288回 会社が元気になれる「夢」を描く
- 第287回 改善を3重構造にする
- 第286回 資金調達から事業改善への決心に繋げる
- 第285回 巨大企業はなぜ経営方針を変更したのか
- 第284回 巨大企業経営方針からの学び
- 第283回 資本性ローン活用に向けた計画作り
- 第282回 黒字倒産回避に向けた資本性ローン活用
- 第281回 黒字倒産回避のため使える制度(年末まで)
- 第280回 黒字倒産しないために計画に盛り込む要素
- 第279回 黒字倒産を回避できる事業計画の主要素
- 第278回 黒字倒産を回避できる事業計画の作り方
- 第277回 黒字倒産の回避に必要となる事業計画
- 第276回 黒字倒産の2つのメカニズムと回避方法
- 第275回 倒産増加の現状を考える
- 第274回 伴走支援型特別保証の伴走支援とは何か
- 第273回 伴走支援とは何か
- 第272回 中小企業からリレバンを行う
- 第271回 コロナ借換保証の最後のチャンスを捉える
- 第270回 「再生支援の総合的対策」への対処法
- 第269回 コロナ資金繰り支援の延長を活用する
- 第268回 金融監督指針改正の金融機関渉外担当者への影響
- 第267回 金融監督指針改正の目指すところを探る
- 第266回 事業環境変化対応の相談相手を増やす
- 第265回 中小企業政策転換の波に乗れる会社になる
- 第264回 政策転換期も生き抜く会社になる
- 第263回 支援が資金繰りから再生支援に移行する意味
- 第262回 中小企業の存在意義となる需要・供給要因
- 第261回 中小企業存在意義の在処を考えてみる
- 第260回 まだまだある「自己診断の罠」
- 第259回 「自己診断の罠」とは何か
- 第258回 「コロナ後」を生き抜くために
- 第257回 「コロナ後」という特別時代に突入?!
- 第256回 「平時」は以前とは同じではない?!
- 第255回 「平時に戻った」という意味
- 第254回 ほどほど病を克服して資金調達を再トライする
- 第253回 「ほどほどで良い」意識の罠を避ける
- 第252回 雰囲気マネジメントで「息切れ倒産」に対処する
- 第251回 雰囲気をマネジメントする必要性
- 第250回 タフさを実現する「雰囲気」を作る
- 第249回 しなやかさを実現する「タフさ」とは
- 第248回 朝令暮改に適した組織にするには
- 第247回 危機時に必要な朝令暮改を実現する
- 第246回 ウイズコロナ時代の経営で考えるべきこと
- 第245回 ウイズコロナ時代に出口戦略を考える
- 第244回 自助努力を促すコロナ借換保証とする(提案)
- 第243回 「コロナ借換保証が利用できない企業」に思うこと
- 第242回 利き腕は事業改善
- 第241回 事業改善と資金繰りの「両利き経営」を目指す
- 第240回 今年の振り返り(輝かしい来年の足掛かりとなる夢)
- 第239回 今年の振り返り(事業改善への取組)
- 第238回 事業再構築補助金活用での資金調達難
- 第237回 事業再構築補助金が採択されない理由
- 第236回 事業性評価への対応(事業改善の事業性)
- 第235回 事業性評価への対応(事業環境の事業性)
- 第234回 将来を見越す
- 第233回 中小企業対策を期待しつつ自助努力する
- 第232回 5方よしの発想を取り入れる
- 第231回 創発で斬新なソリューションを生む
- 第230回 協力し合う職場作り
- 第229回 現場を巻き込み方向合わせをシミュレーションする
- 第228回 企業立て直しの定性的目標(人の成長)
- 第227回 企業立て直しの定性的目標(顧客満足)
- 第226回 中小企業活性化パッケージNEXTが発表されました
- 第225回 企業立て直しの定性的目標(顧客満足)
- 第224回 雨の日に傘を借りて土砂降りに見舞われたら
- 第223回 企業立て直しの定性的目標(貢献を掲げる)
- 第222回 企業立て直しの心持ち(事業での貢献)
- 第221回 企業立て直しのゴールを描く(売上実現)
- 第220回 企業立て直しのゴールを描く(財務側面)
- 第219回 戦略・ビジョンで取組を成功させる
- 第218回 なぜ上手くいかないのか(合理的道筋がない)
- 第217回 なぜ上手くいかないのか(みんな事にしない)
- 第216回 なぜ上手くいかないのか(自分事にしない)
- 第215回 今期が天下分け目の正念場かもしれません
- 第214回 金融庁による審査支援に関する報道
- 第213回 事業改善に必要な2つのメンタリィ
- 第212回 事業改善のナッジ(成功のきっかけ)
- 第211回 事業改善をどのように目指すか
- 第210回 事業改善を目指すべき場合とは
- 第209回 決算発表時に事業改善・再構築を宣言する
- 第208回 どのようにイノベーションを考えるか
- 第207回 OODAでどんな結論を描いていくか
- 第206回 OODAでどのように考えていくか
- 第205回 起こすべき変化をどのように考えていくか
- 第204回 中小企業活性化パッケージを機能させるために
- 第203回 金融支援の活用について
- 第202回 中小企業活性化パッケージの目的(推察)
- 第201回 中小企業活性化パッケージが発表されました
- 第200回 事業再構築が必要な理由
- 第199回 事業再構築を改めて考えてみる
- 第198回 融資口利き事件からの教訓
- 第197回 企業のチャレンジを計画として形にする
- 第196回 模範からの学びをブラッシュアップする
- 第195回 新たな試みとはどんな試みか
- 第194回 事業環境分析を行う2つの眼
- 第193回 新たな試みを始めるため自社を分析する
- 第192回 まず何を考えると事態の好転に繋がるのか
- 第191回 2022年を輝かしい年にするために
- 第190回 事業環境の変化を把握する
- 第189回 上手くいかない時の対処方針案
- 第188回 ストレッチした目標を立てる意義
- 第187回 自社の儲け方を考える
- 第186回 儲かる改善策を練る方法
- 第185回 改善策の実効性を検証する
- 第184回 今、一歩踏み出してみる
- 第183回 何時まで大丈夫か?実は今です!
- 第182回 燃料切れにならないうちに
- 第181回 ガバナンス体制の整備
- 第180回 財務基盤の強化とは
- 第179回 事業承継できる財務基盤
- 第178回 会社と経営者の関係を見直す
- 第177回 事業承継できる会社になる
- 第176回 事業承継について考える
- 第175回 「将来は現在の延長にある」を疑ってみる
- 第174回 「目の前の仕事を全力で」良いのか?
- 第173回 会社を守る「積極経営」を
- 第172回 多すぎる借入に勇気を出して立ち向かう
- 第171回 「確実に成果が出る計画」にするには
- 第170回 「実行確実性」を示す
- 第169回 「戦略計画」を生きた計画にする
- 第168回 「戦略計画」とはどんな計画か
- 第167回 「今までと違うことをやる」を成功させる
- 第166回 「打つ手がない」と思った時に行えること
- 第165回 事業性評価のため企業が行うべきこと
- 第164回 融資審査「枠組み」の意義
- 第163回 StrateCutionsが提案する事業性評価枠組み
- 第162回 事業性評価はなぜ浸透しなかったか
- 第161回 事業性評価支援士養成講座がスタート
- 第160回 K字型回復時代のマネジメント
- 第159回 K字型回復時代に必要なマインドシフト
- 第158回 K字型回復の事業環境で生き残る
- 第157回 伴走支援型特別保証を事業性評価にする方法案
- 第156回 伴走支援型特別保証に事業性評価を期待する
- 第155回 自分がいないと困る人・企業を創造する
- 第154回 「地域に生きるピース」として販路拡大を
- 第153回 止血と構想の重要性
- 第152回 事業性評価で金融機関が見ていること
- 第151回 事業再構築補助金でアフターコロナに備える
- 第150回 「地域で顧客を創造する」構図を考える
- 第149回 「志で顧客を創造」で事業性を創る
- 第148回 自己資本増強共済窓口を民間金融機関に
- 第147回 自己資本増強共済の創設を提案します
- 第146回 新年度の特別融資は事業性評価となる?!
- 第145回 事業性評価相談センターの機能(提案)
- 第144回 謹賀新年:事業再構築元年に
- 第143回 社会視点での中小企業論を望む
- 第142回 資金繰り表を作っていますか
- 第141回 事業性評価相談センター創設を要望します
- 第140回 「雨の日に取り上げる」教訓を今に活かす
- 第139回 事業性評価の審査を受ける意味
- 第138回 「特別な冬」に備える
- 第137回 コロナ特別長期保証の審査支援体制
- 第136回 コロナ特別長期保証を望む
- 第135回 コロナ特別長期貸付の審査
- 第134回 コロナ特別長期貸付の特徴
- 第133回 コロナ特別長期貸付を提案します
- 第132回 地方銀行は多すぎるか(3)事業性評価できることが存在意義になる
- 第131回 地方銀行は多すぎるか(2)地方銀行のポンプ機能
- 第130回 地方銀行は多すぎるか(1)
- 第129回 (人混みを避けて)街に出よう
- 第128回 新しい資本性ローンを検討する
- 第127回 事業計画のもと、会社の力を合わせる
- 第126回 事業計画を張子の虎にしないために
- 第125回 戦略を考えた次にやること:言語化・数値化
- 第124回 トレンドを活用した戦略を考える
- 第123回 カンフル剤に頼らない経営を考える
- 第122回 雨の日に傘を借りた後は事業改善で応える
- 第121回 コロナ対策資金を再度、申し込む場合
- 第120回 今からコロナ対策資金に申し込む場合の留意点
- 第119回 事業改善の方向性
- 第118回 自分が遂げるべき「進化」を考える
- 第117回 ビジネスモデルの転換も視野に入れる
- 第116回 資金調達したら事業改善をスタートさせる
- 第115回 事業改善の意味するもの・異なるもの
- 第114回 次に来るかもしれない試練に備える
- 第113回 支援制度にビジョン・整合性を求む
- 第112回 民間金融機関活用新制度を評価する
- 第111回 コロナ特別短期保証の提案
- 第110回 コロナ特別短期貸付の提案
- 第109回 特別貸付・特別保証で断られる理由
- 第108回 特別貸付・特別保証で減額される理由
- 第107回 こんな時期にこそ社員のモチベーション
- 第106回 調達した資金を有効利用する
- 第105回 資金繰り特別支援への準備(融資希望額を考える)
- 第104回 信用保証を利用して資金調達する
- 第103回 コロナ被害に対応する(資金調達)
- 第102回 事業性評価が「事業改善評価」の場合
- 第101回 税理士と決算を整える
- 第100回 決算書を見直す
- 第99回 金融の変化に対応する
- 第98回 資金調達に必要な「将来を見通す力」
- 第97回 新時代を迎え、対応する(新年ご挨拶)
- 第96回 <緊急版>金融検査マニュアル廃止・新時代へ!
- 第94回 BCPで自衛する
- 第93回 日本公庫融資を通じた災害復旧支援
- 第92回 信用保証を通じた災害復旧支援
- 第91回 緊急時の資金調達方法を頭に入れる
- 第90回 景気低迷前に資金調達準備する!
- 第89回 景気低迷前に事業改善する!
- 第88回 景気低迷への備えは万全ですか?
- 第87回 「お化け」に怯えない!
- 第86回 「我が身を助ける」事業承継計画と「助けない」計画
- 第85回 「続ける!」意思を表明しないと相手にされない!?
- 第84回 中小企業の対応方向性
- 第83回 金融機関と信用保証の連携とは
- 第82回 信用保証制度見直しの影響
- 第81回 税理士ができる支援
- 第80回 金融円滑化法利用企業が待っている
- 第79回 税理士と「雨の日」に備える
- 第78回 期待される税理士の役割
- 第77回 金融検査マニュアル廃止時代の「税理士の選び方」
- 第76回 「事業性評価」依頼が失敗した時
- 第75回 会社の不調は誰のせい?
- 第74回 中小企業に求められる臨機応変
- 第73回 金融検査マニュアル廃止時代に生きる
- 第72回 忘年会か、記年会か
- 第71回 事業性を上手く表現する
- 第70回 資金調達できる!日頃の行動を考える
- 第69回 年末の資金調達を考える
- 第68回 コンサルティングをうまく活用する
- 第67回 情報を隠すか、開示するか
- 第66回 金融機関との付き合い方を考える
- 第65回 いつものことを、同じでなくする
- 第64回 「不況業種」と言われたら
- 第63回 資金繰りを計画する
- 第62回 創業資金を調達する
- 第61回 信用保証以外の調達策「マル経融資」を活用する
- 第60回 信用保証制度見直しによる予想される影響と対策(2)
- 第59回 信用保証制度見直しによる予想される影響と対策(1)
- 第58回 信用保証制度見直しに対応する(3)
- 第57回 信用保証制度見直しに対応する(2)
- 第56回 信用保証制度見直しに対応する(1)
- 第55回 ものづくり補助金を活用する
- 第54回 メインバンクを持つべきか?
- 第53回 金融機関に、中小企業に歩み寄ってもらう
- 第51回 「晴れの日に傘を貸して雨の日に取り上げる」の教訓
- 第50回 金融機関とのコミュニケーションを深める
- 第49回 信用保証はどこへ向かうのか?
- 第48回 超特急で事業性評価融資を依頼する
- 第47回 補助金活用で経営改善の姿勢を見せる
- 第46回 戦略とマネジメント
- 第45回 金融機関が事業性評価融資を提案する場合
- 第44回 残念な事業計画書
- 第43回 年末資金調達の準備を始める
- 第42回 「資金を調達すると同時に経営改善を目指す」セミナー(お知らせもあります)
- 第41回 金融機関の審査方法
- 第40回 取引する金融機関を戦略的に検討する
- 第39回 金融機関の考えを知る
- 第38回 金融機関に受け入れられなかった場合
- 第37回 計画策定のプロセス
- 第36回 実際にご支援した事業計画書の例
- 第35回 事業性評価融資を依頼するための事業計画書
- 第34回 事業性評価融資を依頼する
- 第33回 言葉遣いを気にしてみる
- 第32回 企業が伝えたいことと金融機関が知りたいこと
- 第31回 中小企業金融の行方
- 第30回 専門家の助けを借りる
- 第29回 儲かる構図を作り上げる
- 第28回 金融機関を安心させるコミュニケーション
- 第27回 日頃のコミュニケーションで貸し剥がされない企業になる
- 第26回 IT導入補助金経営計画書を活用する
- 第25回 金融機関は経営者について何を見ているか?
- 第24回 経営力向上計画をバネにする(下)
- 第23回 経営力向上計画策定をバネにする(上)
- 第22回 経営力向上計画に取り組む
- 第21回 どのタイミングで金融機関を訪れるか
- 第20回 金融機関に伝えたいことを伝える
- 第19回 金融機関からの質問に答える
- 第18回 金融機関が質問する意図
- 第17回 金融機関とのコミュニケーション
- 第16回 「支援したい」と思わせる事業計画書を作成する(後編)
- 第15回 「支援したい」と思わせる事業計画書を作成する(中編)
- 第14回 「支援したい」と思わせる事業計画書を作成する(前編)
- 第13回 今までは常識だったが、今は意味合いが薄れたアプローチ
- 第12回 金融機関の特性に対応した行動を取る(コミュニケーション編)
- 第11回 金融機関の特性に対応した行動を取る(金融基礎編)(後編)
- 第10回 金融機関の特性に対応した行動を取る(金融基礎編)(前編)
- 第9回 金融機関の特性に対応した行動を取る(日頃の行動編)
- 第8回 事業計画を作成して資金調達に成功した例
- 第7回 事業計画書で経営改善の意思を示す
- 第6回 金融庁森信親長官インタビューから
- 第5回 借入したかったら経営改善に努力するというスタンス
- 第4回 金融と経営支援の一体的な推進
- 第3回 中小企業金融政策の転換理由とは?
- 第2回 今起きている中小企業金融の変化、そして求められている対応の変化
- 第1回 新年を迎えるにあたって一年の計画











