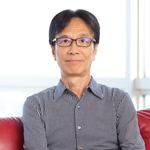第156回
伴走支援型特別保証に事業性評価を期待する
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

4月に入り、新年度が始まりました。とは言え、新型コロナウイルス感染症は第4波を心配する状況で、経済の回復にあまり大きな希望を持てません。インバウンドを期待する観光業などで先が見通せないのは相変わらずで、通勤客を顧客とする飲食業などは、コロナ禍が例え収束しても以前の活況が帰ってくると期待するのは難しい状況です。多くの中小企業にとって厳しい新年度のスタートとなりました。このような状況下、政府は「伴走支援型特別保証制度」を発表しました。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html
「伴走支援型信用保証制度」の概要
伴走支援型信用保証制度の概要は以下の通りです(中小企業庁Webサイト:4月1日現在)
・上限金額:4,000万円
・貸付期間:10年以内(据置期間:5年以内)
・金利:金融機関所定
・保証料率0.2%(国による補助前は原則0.85%)
・要件:セーフティネット保証要件(売上減少等)
経営行動計画書作成(企業)
継続的な伴走支援(金融機関)
経営行動計画書はサンプルも掲載されています。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo02.pdf
「伴走支援型信用保証」を事業性評価に!
この保証制度案内を始めて見た時、金融機関に「事業性評価の推進」を、そして中小企業に「資金調達のタイミングで事業改善の決意」を提案してきた筆者は「我が意を得たり!」と感じました。しかし今は、落ち着いて今後を見守ろうと考えています。この制度で事業性評価が上手く機能するかを、見極めるのです。
筆者が事業性評価にこだわる理由をお話しましょう。昨年秋以降、多くの中小企業から「会社を持続させる資金調達がままならない」という声が聞かれていました。春から夏にかけてコロナ特別融資・保証を受けた後、秋以降はセーフティネット保証などの要件を満たしていても審査が通らないというのです。この理由は、金融機関(信用保証協会を含む)は、融資や保証の制度で定める限度額以外に、企業毎に限度額を設定しているからです。例えば信用保証一般枠は無担保保証と普通保証の合計で2億8千万円ですが、全ての企業がこの限度一杯まで保証を受けられる訳ではありません。事業規模や財務体質、従前の借入実績などをもとに、企業に見合った限度額が設定されるのです。
ある企業の資金調達事情を例に考えてみましょう。その企業に対して金融機関は融資(保証)限度を5,000万円と考え、一昨年末まで実際にその限度まで利用していたとします。その中で夏にコロナ特別保証として2,000万円を申し込み、融資を得ることができました。その後もコロナ禍が続いたので更に1,000万円の申し込みを行った場合に、金融機関(信用保証協会)は承諾できるでしょうか?従前の考え方に基づく限り、それは難しいと思います。この企業に対して、設定した限度額(5,000万円)を大きく超える融資(保証)を既に行っているからです。コロナ禍で企業の財務体質が悪化したことを考えると、これ以上は難しいでしょう。
では、どうすればこの企業が持続化に必要な資金調達ができるのか?現在、金融機関は金融検査マニュアル(令和元年12月廃止)に基づく信用格付に準拠して融資判断していると考えられます。企業の財務体質を主に評価する思考ロジックに基づき「当該企業への融資限度は5,000万円だ」と判断している状況下、プラスアルファの与信が可能になるには、新たな思考ロジックを加えるしかありません。その一つ(現状、唯一と考えられる)として事業性評価が挙げられます。企業が有する「事業性」を評価して、「プラスして1,000万円の追加支援も可能だ」と判断するのです。
「それを行うのが『伴走支援』ではないか!金融機関が『伴走支援すれば企業の事業性が高まるので融資できる』と判断するよう促しているのだ。」仰る通りです。政策は、まさにそれを目指していると思われます。すると、伴走支援する金融機関は「自分が伴走支援すれば、企業はしっかり走ってくれるのか」を確認したいと考えるでしょう。将来、「我が金融機関の伴走支援型信用保証に係る代位弁済率が異様に高い」ことは避けたいからです。
「そんなこと、どうやって確認するのか?」事業性評価が鍵になります。伴走支援型特別保証が成功するか否かは、金融機関が適切に事業性評価できるか否かにかかっているのです。筆者はもちろん、この試みが成功することを願っています。
<本コラムの印刷版を用意しています>
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、資金調達する方法をしっかりと学んでみてください。
なお、冒頭の写真は写真ACから Makoto410 さんご提供によるものです。Makoto410 さん、どうもありがとうございました。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた後、事業改善手法を身に付け業務・経営側面から支える専門家となる。現在は顧問として継続的に企業・経営者の伴走支援を行っている。顧問企業には財務改善・資金調達も支援する。
平成27年に「事業性評価」が金融庁により提唱されて以来、企業にも「事業を評価してもらいたい。現在の状況のみならず将来の可能性も見越して支援してもらいたい」との意識を持ち、アピールしてもらいたいと考えて『「事業性評価」が到来!あなたは資金調達できますか?』コラムを連載(2017年1月スタート)。当初は読者として企業経営者・支援者を対象していたが、金融機関担当者にも中小企業の事業性評価を支援してもらいたいと考え、2024年1月からは『「事業性評価」が到来!あなたは資金調達できますか?plus』として連載を再スタートさせた。
現在は金融機関職員研修も行うなど、事業改善と金融システム整備の両面からの中小企業支援態勢作りに尽力している。
【落藤伸夫 著書】
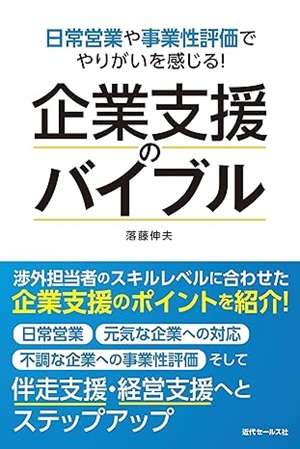
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions